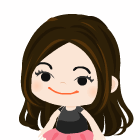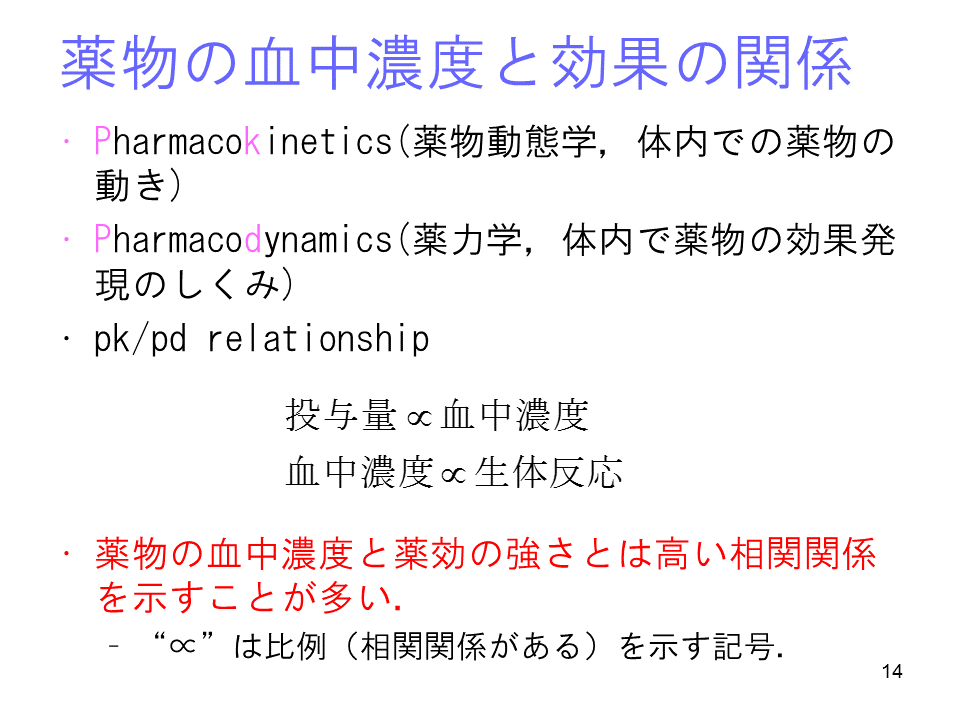●ステロイド9)処方された薬の服用時間を厳守する理…についたコメント
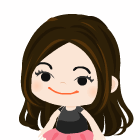
◆ junさん
2月に抜歯した時のことを思い出しました~。
痛み止めは1種類だから全然違うけれど、頓服で1日3回まで、服用は4時間は空けることってことでしたが、4時間毎に3回飲んでしまうと12時間で飲み切ってしまうので、綺麗に8時間毎に飲むことにして、薬が4~5時間で切れるので、3時間くらいは痛くて寝てる日々でした。
先生には「痛かったら1日4回飲んでもいいよ」と言われたんですけど、潰瘍性大腸炎だと鎮痛剤は避けたい薬なので、なんとか3回で頑張りました~。
あと、私が入院した病院では、年老いたりして自分で薬の管理をするのが難しい人以外は、自分で管理してそれぞれの時間に飲むスタイルでした。
弱ってた私は顆粒の封をなかなか開けられなかったりして苦労しました💦
◆ けい
痛み止めが切れた3時間って3回もあった? 夜の痛みは特に辛かったのでは? よく耐えた!というか、選択の余地なし?
わたしが親知らずの抜歯をしたときは、痛み止めの薬を使い続けることができたので、幸い痛かった思い出はありません。それよりも、長時間の治療で足が冷たくなり、そちらのほうが辛かったです。
日本の病院では、薬のスケジュール、自分で管理するんですね。なるほど。看護婦さんも忙しいし。
薬の封を開けられないほどに弱っていた。指に力が入れられないほどだった。それでも、からだは回復し、ちゃんと退院できた。
ヒトの病気を乗り越えるための回復力ってすごい。
お互い、からだ、いたわりましょう。
▼ 鎮痛剤と難病
潰瘍性大腸炎/クローン病の痛みには鎮痛剤を使ってはいけない。そのことは知っていましたが、歯の痛み止めも要注意ということには気がつきませんでした。
厚労省の薬情報で確認してたら、まさにその通りでした。使用の際は、薬剤師に要確認です。
鎮痛剤の要注意の事項で、意味不明だった個所がありました。
消化性潰瘍のなかに潰瘍性大腸炎/クローン病が含まれるかどうかです。
こちらの厚労省の説明によると、消化性潰瘍と潰瘍性大腸炎/クローン病は、異なる症状です。
→消化性潰瘍
胃や十二指腸の粘膜が荒れること
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
●アスピリン
解熱鎮痛消炎剤
9.1.1 消化性潰瘍の既往歴のある患者
消化性潰瘍を再発させることがある。
*記載には、潰瘍性大腸炎/クローン病の表記なし。
●アセトアミノフェン
解熱鎮痛剤
9.1.3 消化性潰瘍又はその既往歴のある患者
症状が悪化又は再発を促すおそれがある
*記載には、潰瘍性大腸炎/クローン病の表記なし。
●ロキソプロフェン
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAID)
鎮痛・抗炎症・解熱剤
9.1.1 消化性潰瘍の既往歴のある患者
潰瘍を再発させることがある。
*記載には、潰瘍性大腸炎/クローン病の表記なし。
この薬は、消化性潰瘍とは別に、潰瘍性大腸炎/クローン病の項目あり。
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者
本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もある。[2.1、11.1.3参照]
9.1.2 消化性潰瘍の既往歴のある患者
消化性潰瘍を再発させることがある。[11.1.3参照]
9.1.3 血液の異常又はその既往歴のある患者(重篤な血液の異常のある患者を除く)
血液の異常を悪化又は再発させるおそれがある。[2.2、11.1.2参照]
9.1.4 出血傾向のある患者
血小板機能低下が起こることがあるので、出血傾向を助長するおそれがある。
9.1.5 心機能異常のある患者(重篤な心機能不全のある患者を除く)
プロスタグランジン合成阻害作用による水・ナトリウム貯留傾向があるため、心機能異常を悪化させるおそれがある。[2.5参照]
9.1.6 高血圧症のある患者(重篤な高血圧症のある患者を除く)
プロスタグランジン合成阻害作用による水・ナトリウム貯留傾向があるため、血圧を上昇させるおそれがある。[2.6参照]
9.1.7 気管支喘息のある患者(アスピリン喘息又はその既往歴のある患者を除く)
アスピリン喘息でないことを十分に確認すること。気管支喘息の患者の中にはアスピリン喘息患者も含まれている可能性があり、それらの患者では喘息発作を誘発させることがある。[2.8、11.1.8参照]
9.1.8 感染症を合併している患者
必要に応じて適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与すること。感染症を不顕性化するおそれがある。
9.1.9 全身性エリテマトーデス(SLE)の患者
SLE症状(腎障害等)を悪化させるおそれがある。[11.1.6参照]
9.1.10 混合性結合組織病(MCTD)の患者[11.1.6参照]
9.1.11 潰瘍性大腸炎の患者
他の非ステロイド性消炎鎮痛剤で症状が悪化したとの報告がある。
9.1.12 クローン病の患者
他の非ステロイド性消炎鎮痛剤で症状が悪化したとの報告がある。
以下ほぼ同文
▼ アセトアミノフェン
▼ ロキソプロフェン