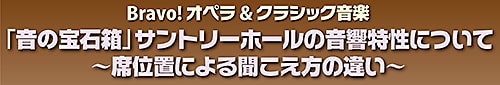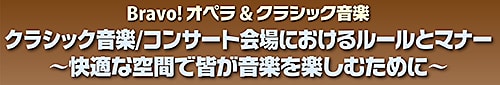文京シビックホール 夜クラシック Vol.10
川久保賜紀(ヴァイオリン)&村治奏一(ギター)
2016年11月11日(金)19:30〜 文京シビックホール・大ホール S席 1階 1列 28番 2,250円(セット券)
ヴァイオリン:川久保賜紀
ギター:村治奏一*
【曲目】
ドビュッシー:『ベルガマスク組曲』より「月の光」
モリコーネ:ニュー・シネマ・パラダイス
パガニーニ:ヴァイオリンとギターのためのカンタービレ ニ長調 作品17
パガニーニ:ヴァイオリンとギターのための協奏的ソナタ イ長調 作品61
タレガ:アルハンブラの思い出(ギター・ソロ)*
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
1.簿の踊り 2.飾り紐の踊り 3.足踏みの踊り 4.ブチュム(角笛)の踊り
5.ルーマニア風ポルカ 6.速い踊り
ピアソラ:オブリビオン(忘却)
ピアソラ:タンゴの歴史
1.酒場1900 2.カフェ1930 3.ナイトクラブ1960 4.現代のコンサート
《アンコール》
ファリャ:『スペイン民謡舞曲』より「ホタ」
文京シビックホール(公益社団法人文京アカデミー)が主催する「夜クラシック」シリーズは、一流アーティストによるリサイタルまたは室内楽のコンサートを年間に4回開催する。「夜」という名の通りちょっと遅めの19時30分スタートで休憩を含めて90分間というコンサート。今年のシリーズはすべて金曜日の夜だったので、週末の仕事帰りに、ちょっと気取ってクラシックの名曲を素晴らしい演奏で・・・というコンセプトである。
今期(2016/2017シーズン)は本日が第2回になる。実は年4回のセット券を買っていたのだが、前回は所用が出来て行けなかったので、今日が初参加となった。
今回はヴァイオリンの川久保賜紀さんとギターの村治奏一さんとのデュオ・リサイタルである。このお二人のデュオは何度も聴いているし、曲目もほとんどいつも似たようなものなので、すっかりお馴染みになってしまっている。ただ、これまでは会場は小さなホールばかりだったが、今回は異例の大ホールである。空間の大きさがまったく違う世界になるので、響きも全然違ってくるし、演奏の仕方も変わってくるはず。その点で、いつもとは違った新鮮な演奏を聴かせてくれるのではないかと、期待するものであった。
文京シビックホールは、東京フィルハーモニー交響楽団の「響きの森」シリーズ(こちらも年間4回)をかなり以前から聴いているので、お馴染みになっているが、実はこの大ホールでのリサイタル(あるいは室内楽)は経験がない。もちろん1800名入る2階構造の大ホールでのリサイタルというのには、いささか無理があろう。もともとこのホールは、多目的ホールなのでやむを得ないことだが、残響が少なくオーケストラでさえ音がすっぽ抜けてしまうようなところがある。とくに今回は楽器としては音量の小さいギターとヴァイオリンのデュオなので、後方の席まではギターの音はうまくは届かないと思われる。そこで、ギターについてのみ、マイクを立てて音を拾い、小さなアンプ・スピーカーをギタリスト席の後ろに置いて、わずかに拡声をしていた。おそらく、ある程度離れた席(ホール1階の中央辺り)では、気にならない程度にバランス良く聞こえていたはずである。
私はと言えば、いつものように最前列だったので、奏一さんのギターが鳴り出したときに、不自然な音量に感じてしまった。ギターはこんなに大きな音はしない(自分でも多少演奏するのでよく分かる)。一方で賜紀さんは大ホール故にいつもよりは大きな音を出すような演奏をしていたようだ。それでもヴァイオリンとギターの音量バランスはうまく取れていたので、ナルホド、アンプ・スピーカーのちょっとした効果がかなり有効に効いているようであった。
1曲目はドビュッシーの「月の光」。ホールの照明をステージを含めてすべて落とし、暗闇の中を賜紀さんと奏一さんが静かに登場し、おもむろに演奏が始まった。夜をイメージするこの曲は、この「夜クラシック」シリーズのテーマ曲になっている。静かにつま弾かれるギターの分散和音に乗せて、細く線を引くように賜紀さんのヴァイオリンが入ってくる。冷たい光が闇を照らし、うっすらと浮かび上がる木々や池の上を風が静かに吹き抜けていく。肩の力が抜けた自然な柔らかさの演奏で、大きなホールの空間に広がっていく音が、あたかも夜空に浮かぶ月の光が無限の空間に広がっていくようなイメージ。情景が目に浮かぶようであった。
お二人のトークを挟んで、2曲目はモリコーネの「ニュー・シネマ・パラダイス」。1988年公開のイタリア映画『Nuovo Cinema Paradiso』の映画音楽としてヒットした曲(英語表記のカタカナにしてしまうとやや興ざめ??)。映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ(1928〜)の代表作のひとつである。原曲はクラシック・ギター2本のために書かれたギター二重奏だが、今日はもちろんヴァイオリンとギターで、賜紀さんの編曲も少しかわえられた演奏だとか。クラシック音楽専門で映画音楽などは無縁という人でも、聴いてみれば、あぁ、あの曲か・・・・と言うくらいに知られたメロディが出てくる。そういう曲であるから、ヴァイオリンの方はゆったりとして美しいが単純な旋律を繰り返すだけで、とくに技巧的な部分などはない。しかし、そうなると表現力が重要になってくるわけだが、賜紀さんのレベルの旋律の歌わせ方は、普通の映画音楽の演奏レベルを遥かに凌駕している。大らかに歌い、流れるようなレガートを効かせ、繊細で微妙なニュアンスで描かれる音楽世界。単純であるが故に、これ以上はないというくらい、美しい演奏だ。

続いてパガニーニの「ヴァイオリンとギターのためのカンタービレ ニ長調 作品17」。悪魔に魂を売り渡してヴァイオリン演奏技術を手に入れたと言われたほどの超絶技巧の持ち主だったパガニーニ(1782〜1840)だが、実はギタリストでもあり、とくに1800年〜1805年にギターの曲を多く作曲しているという。この「カンタービレ」の作曲年代は不明で、ピアノ伴奏曲として作られたようだが、ギター伴奏版とともに人気の高い曲である。その名の通り歌うような息の長い甘美な旋律が、流れるような技巧的なパッセージに装飾されていて、ロマンティシズム溢れる小品だ。
賜紀さんの演奏は、小さなホールで演奏する時よりも全体に音を大きく出していて、また大きなホール故に、音が朗々と響いていた。演奏自体も丁寧に弾いている感じでヴィブラートを豊かに効かせ、レガートも流れるよう。この大らかな歌わせ方こそが賜紀さんの真骨頂で、温かみのある音色と上品な響きがこの曲にピッタリ。また装飾的な速いパッセージも残響の中に一瞬閉じ込められるくらいの速さであったが、私にはすべての音符が正確に演奏されているのを聴き取ることができた。これは最前列ならではの利点だ。素晴らしい演奏だったと思う。
前半の最後は、同じパガニーニの「ヴァイオリンとギターのための協奏的ソナタ イ長調 作品61」。この「ソナタ・コンチェルタンテ」は1803年の作とされ、パガニーニがギターのための作品にもチカラを注いでいた時期に当たる。そのためか、ヴァイオリンとギターが同等に扱われていて、両者の掛け合いがあたかもヴァイオリニストとギタリストが対話するような雰囲気を醸し出す。この頃のパガニーニはギタリストの女性と恋仲だったと伝えられていて、なるほど優しげなギターのパートに比べると、ヴァイオリン・パートの方が情熱的に感じられる。一般的には音域から言ってもヴァイオリンが女性でギターが男性の方がイメージしやすいが、この曲はどうみてもヴァイオリンがパガニーニ自身を表しているように聞こえる。
第1楽書は冒頭から賜紀さんのヴァイオリンが鋭い立ち上がりで情熱的に聴かせてくる。それを奏一さんのギターがふわりと受け止める。第2主題のヴァイオリンは優しげな愛情表現のように優しい音色に変わる。展開部はあたかも恋人同士の対話のように、主客が目まぐるしく入れ替わる。この曲での賜紀さんの演奏は、いつもよりは鋭くエッジを立てて押し出してくる。対する奏一さんのギターは丸い音色で優しい。
第2楽章は短調に転じて、もの悲しい主題をヴァイオリンとギターが交互に弾く。愛し合う男女の未来に不運な要素が見え隠れしているのだろうか。対話しているようだといっても、異なる意見をぶつけ合っているのではなく、将来への不安を語り合っているようである。
第3楽章は、一転して明るく陽気な主題によるロンド。賜紀さんのヴァイオリンがぐっと明るい音色に変わり、弾むようなリズム感と、躍動的なフレージングが素敵。奏一さんのギターもとてもリズミカルでギターの持つ本来の陽性の部分と、スペインとは違う、イタリアっぽい明るさが素晴らしい演奏だ。
賜紀さんが語るには、パガニーニはヴァイオリンとギターの曲をたくさん書いているので、もっと色々な曲を紹介していきたいという。旋律を自由度高く歌わせることにかけては天下一品の賜紀さんだから、イタリア・オペラのアリアのような美しい旋律を書くパガニーニをもっともっと聴かせて欲しいものだ。

後半は、予定されていたプログラムに急遽追加するカタチで、奏一さんのギター・ソロで、お馴染みの「アルハンブラの思い出」が演奏された。奏一さんはこの曲を演奏する際には2小節だけ分散和音だけの前奏を加える。そして主旋律が美しいトレモロで紡ぎ出されていく。奏一さんはどちらかといえばテンポを揺らす方の演奏で、トレモロの主旋律を歌謡的に歌わせるのが特徴。上品でロマンティック。とても素敵な演奏だ。アンプ・スピーカーがなければ後方席までこの繊細な音色が届いたかどうか。
再び賜紀さんが登場して2曲目はバルトークの「ルーマニア民俗舞曲」。こちらも賜紀さんとしてはお馴染みのレパートリーで、ギター伴奏でも、ピアノ伴奏でも、しばしばプログラムに載せている。ハンガリー生まれのバルトークが、当時はハンガリー領だったルーマニアの各地から集めた民謡・舞曲を素材として、1915年に6曲のピアノ用小品にまとめた。その後管弦楽版にも編曲されている。後になってヴァイオリニストのセーケイ・ゾルターンがヴァイオリンとピアノ用に編曲したのが1926年のこと。今日の演奏は、それをさらにヴァイオリンとギター用に編曲にしたものということになる。
第1曲の「棒の踊り」では冒頭の奏一さんのギターが思ったよりも力強く低音と和音を押し出し、賜紀さんのヴァイオリンも力強く低弦で主題を弾く。主題が中音域に上がって行くと重音を艶やかに響かせるのが印象的だった。第2曲「飾り紐の踊り」ではヴァイオリンが自由度高く気ままに踊るよう。第3曲「足踏みの踊り」はヴァイオリンがフラジオレットだけで民族調の音楽を奏でるが、これは意外に難しいところ。第4曲「角笛の踊り」はロマン性豊かな曲想の美しい旋律が賜紀さんのヴァイオリンで艶っぽく語られていく。かなり色っぽく表情豊かな演奏である。第5曲「ルーマニア風ポルカ」と第6曲「速い踊り」はつながっていて、村人達が熱狂的に踊り狂っている様子を、軽快で躍動的なリズム感の賜紀さんのヴァイオリンが跳ねるように踊り、奏一さんのギターがそれを煽るようにリズムを刻む。全部合わせても7分程度の曲なのだが、ヴァイオリンがそれぞれの曲でまったく異なる色彩と表情を細やかに弾き分けているのにもかかわらず、全体をルーマニアの民族調の色合いにまとめ上げている。このようなところに賜紀さんのヴァイオリンの奥深いところがある。前半のパガニーニとは色彩感がまるで違う。それでいて、旋律が大らかに歌うところは共通したイメージも創り上げている。それこそが賜紀さんの個性というものだろう。
続いて舞台はアルゼンチンへと飛び、ピアソラの「オブリビオン(忘却)」という曲。こちらも元は映画音楽として書かれた曲で、1984年、イタリア映画『エンリコ4世』の中の挿入曲である。あいにくとその映画はまったく知らないが、曲の方は誰もがどこかで聴いたことがあるはず。感傷的でロマンティックな旋律が殊の外美しく、賜紀さんのヴァイオリンもすすり泣くような、息の長い旋律をヴィブラートをたっぷり効かせて、濃厚なニュアンスを込めていく。ギターのパートも非常に濃厚なロマンティシズムを湛えていて、奏一さんの上品な音色がむしろしつこさを打ち消していて、美しい響きを創りあげていた。
最後は同じピアソラで「タンゴの歴史」。アルゼンチン生まれのアストル・ピアソラ(1921〜1992)は、もとはバンドネオン奏者として名を馳せた人。つまりアルゼンチン・タンゴの演奏家だったが、パリに留学して西洋クラシック音楽の作曲法を学び、アルゼンチンに戻って伝統的なタンゴをクラシック音楽と融合させ世界に広めた。この曲は、元はフルートとギターのために書かれた曲であり、4つの楽章から成る。内容は標題通りで、1900年頃の酒場(Bordel=売春宿)で流行っていたタンゴ、1930年頃は当時流行のカフェでタンゴが流れ、1960年にはナイトクラブが主流になる。1990年のタンゴは現代音楽と化しコンサート会場でしか演奏されない・・・・といった風に20世紀の「タンゴの歴史」が描かれているのである。
第1楽章「酒場1900」はヴァイオリンのソロから始まるが、賜紀さんはアドリブを効かせて自由度の高いソロを聴かせる。それを受ける奏一さんもノリが良い。やがて伝統的なタンゴのリズムに収束していき、二人が息の合った軽快なリズム感で、ちょっと陰の射す陽気さの酒場(売春宿)に流れるタンゴが描かれて行く。
第2楽章「カフェ1930」はギターの序奏が、頽廃的で行き場のない世界観を描き出していく。ヴァイオリンの主旋律も悲観的なイメージが強い。演奏も湿り気を帯びた色彩感で、しっとりとした佇まいを見せる。中間部になると明るい曲想に変わり、不安感の中にも陽が射す時もあるのだとでも言いたげだ。ヴァイオリンもギターのこのような情感の変化を鮮やかな音色の変化で描き分けている。
第3楽章「ナイトクラブ1960」になると、タンゴは夜の世界に沈殿していく。見せかけの陽気さと虚飾に満ちた世界観。音楽は夜の世界のイメージを濃厚に漂わせながら、表向きはロマンティシズムを主張する。ふたりの演奏はそういった情感、あるいは情景をリアルに描き出している。
第4楽章「現代のコンサート」は、タンゴが無調で変拍子の現代音楽に進化(退化?)している様子を描く。それでも何となくタンゴに聞こえるのはさすがにピアソラならでは。賜紀さんの演奏する現代音楽はほとんど聴く機会がないのだが、この楽章のように現代音楽「風」に創られた曲であっても素晴らしい感性を発揮して、明瞭で鮮やかな演奏を聴かせてくれたのはさすがである。
今日のコンサートは「夜」がテーマだった(わけではない?)が、内容はヴァイオリンとギターによる音楽の世界紀行といったものになっていた。ドビュッシー(フランス)に始まり、モリコーネ(20世紀のイタリア)、パガニーニ(19世紀のイタリア)、バルトーク(ハンガリー/ルーマニア)、そしてピアソラ(アルゼンチン)という風に世界を回った。
そしてアンコールはスペインに飛び、ファリャの『スペイン民謡舞曲』から「ホタ」。本来の長さのコンサートであれば『スペイン民謡舞曲』も全曲演奏するところだろう。「ホタ」はヴァイオリンのピツィカートがギターのようにリズムを刻むかと思えば、歌謡的な旋律を大らかに歌いだす。その対比も鮮やかだし、ギターのパートもさすがに本国のスペインという感じがして、情熱的なのに感傷的で美しい演奏であった。
終演後は恒例のサイン会・・・・がなかった。実はこの日、大阪から賜紀さんファン仲間のKさんが聴きに来ていたので、お会いしないまま帰るのもちょっと寂しい、ということで、楽屋にお邪魔してみることに。もちろん係の人に了承を得てのことである。終演後のステージの裏側を通り抜けて(これも得がたい体験だ)楽屋に向かうと、何人かの面会者が訪れていた。ホールの撤収時刻は迫っていたようだが、いつものサイン会とは違って、急かされることなくゆっくりとお話しすることができて、とても嬉しい一時であった。Kさんも大阪から来た甲斐があったと大喜びであった。
賜紀さんは世界でもトップ・クラスのヴァイオリニストだといえるが、私たちのような者にも気さくに接してくれる。そのふんわりとしたお人柄が演奏にもよく表れている。今日は、大らかに歌うパガニーニや、土の香りのする民族調のバルトーク、エキゾチックなピアソラ、情熱的なファリャなど、文化の異なる様々な音楽を多彩な音色やリズム感を見事に使い分けて演奏してくれたわけだが、全体を通してみれば、楽曲の本質には深く迫りながらも優しくてエレガントな「川久保賜紀流」の演奏になっていて、それが何よりも魅力的なのである。

 ← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
川久保賜紀(ヴァイオリン)&村治奏一(ギター)
2016年11月11日(金)19:30〜 文京シビックホール・大ホール S席 1階 1列 28番 2,250円(セット券)
ヴァイオリン:川久保賜紀
ギター:村治奏一*
【曲目】
ドビュッシー:『ベルガマスク組曲』より「月の光」
モリコーネ:ニュー・シネマ・パラダイス
パガニーニ:ヴァイオリンとギターのためのカンタービレ ニ長調 作品17
パガニーニ:ヴァイオリンとギターのための協奏的ソナタ イ長調 作品61
タレガ:アルハンブラの思い出(ギター・ソロ)*
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
1.簿の踊り 2.飾り紐の踊り 3.足踏みの踊り 4.ブチュム(角笛)の踊り
5.ルーマニア風ポルカ 6.速い踊り
ピアソラ:オブリビオン(忘却)
ピアソラ:タンゴの歴史
1.酒場1900 2.カフェ1930 3.ナイトクラブ1960 4.現代のコンサート
《アンコール》
ファリャ:『スペイン民謡舞曲』より「ホタ」
文京シビックホール(公益社団法人文京アカデミー)が主催する「夜クラシック」シリーズは、一流アーティストによるリサイタルまたは室内楽のコンサートを年間に4回開催する。「夜」という名の通りちょっと遅めの19時30分スタートで休憩を含めて90分間というコンサート。今年のシリーズはすべて金曜日の夜だったので、週末の仕事帰りに、ちょっと気取ってクラシックの名曲を素晴らしい演奏で・・・というコンセプトである。
今期(2016/2017シーズン)は本日が第2回になる。実は年4回のセット券を買っていたのだが、前回は所用が出来て行けなかったので、今日が初参加となった。
今回はヴァイオリンの川久保賜紀さんとギターの村治奏一さんとのデュオ・リサイタルである。このお二人のデュオは何度も聴いているし、曲目もほとんどいつも似たようなものなので、すっかりお馴染みになってしまっている。ただ、これまでは会場は小さなホールばかりだったが、今回は異例の大ホールである。空間の大きさがまったく違う世界になるので、響きも全然違ってくるし、演奏の仕方も変わってくるはず。その点で、いつもとは違った新鮮な演奏を聴かせてくれるのではないかと、期待するものであった。
文京シビックホールは、東京フィルハーモニー交響楽団の「響きの森」シリーズ(こちらも年間4回)をかなり以前から聴いているので、お馴染みになっているが、実はこの大ホールでのリサイタル(あるいは室内楽)は経験がない。もちろん1800名入る2階構造の大ホールでのリサイタルというのには、いささか無理があろう。もともとこのホールは、多目的ホールなのでやむを得ないことだが、残響が少なくオーケストラでさえ音がすっぽ抜けてしまうようなところがある。とくに今回は楽器としては音量の小さいギターとヴァイオリンのデュオなので、後方の席まではギターの音はうまくは届かないと思われる。そこで、ギターについてのみ、マイクを立てて音を拾い、小さなアンプ・スピーカーをギタリスト席の後ろに置いて、わずかに拡声をしていた。おそらく、ある程度離れた席(ホール1階の中央辺り)では、気にならない程度にバランス良く聞こえていたはずである。
私はと言えば、いつものように最前列だったので、奏一さんのギターが鳴り出したときに、不自然な音量に感じてしまった。ギターはこんなに大きな音はしない(自分でも多少演奏するのでよく分かる)。一方で賜紀さんは大ホール故にいつもよりは大きな音を出すような演奏をしていたようだ。それでもヴァイオリンとギターの音量バランスはうまく取れていたので、ナルホド、アンプ・スピーカーのちょっとした効果がかなり有効に効いているようであった。
1曲目はドビュッシーの「月の光」。ホールの照明をステージを含めてすべて落とし、暗闇の中を賜紀さんと奏一さんが静かに登場し、おもむろに演奏が始まった。夜をイメージするこの曲は、この「夜クラシック」シリーズのテーマ曲になっている。静かにつま弾かれるギターの分散和音に乗せて、細く線を引くように賜紀さんのヴァイオリンが入ってくる。冷たい光が闇を照らし、うっすらと浮かび上がる木々や池の上を風が静かに吹き抜けていく。肩の力が抜けた自然な柔らかさの演奏で、大きなホールの空間に広がっていく音が、あたかも夜空に浮かぶ月の光が無限の空間に広がっていくようなイメージ。情景が目に浮かぶようであった。
お二人のトークを挟んで、2曲目はモリコーネの「ニュー・シネマ・パラダイス」。1988年公開のイタリア映画『Nuovo Cinema Paradiso』の映画音楽としてヒットした曲(英語表記のカタカナにしてしまうとやや興ざめ??)。映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ(1928〜)の代表作のひとつである。原曲はクラシック・ギター2本のために書かれたギター二重奏だが、今日はもちろんヴァイオリンとギターで、賜紀さんの編曲も少しかわえられた演奏だとか。クラシック音楽専門で映画音楽などは無縁という人でも、聴いてみれば、あぁ、あの曲か・・・・と言うくらいに知られたメロディが出てくる。そういう曲であるから、ヴァイオリンの方はゆったりとして美しいが単純な旋律を繰り返すだけで、とくに技巧的な部分などはない。しかし、そうなると表現力が重要になってくるわけだが、賜紀さんのレベルの旋律の歌わせ方は、普通の映画音楽の演奏レベルを遥かに凌駕している。大らかに歌い、流れるようなレガートを効かせ、繊細で微妙なニュアンスで描かれる音楽世界。単純であるが故に、これ以上はないというくらい、美しい演奏だ。

続いてパガニーニの「ヴァイオリンとギターのためのカンタービレ ニ長調 作品17」。悪魔に魂を売り渡してヴァイオリン演奏技術を手に入れたと言われたほどの超絶技巧の持ち主だったパガニーニ(1782〜1840)だが、実はギタリストでもあり、とくに1800年〜1805年にギターの曲を多く作曲しているという。この「カンタービレ」の作曲年代は不明で、ピアノ伴奏曲として作られたようだが、ギター伴奏版とともに人気の高い曲である。その名の通り歌うような息の長い甘美な旋律が、流れるような技巧的なパッセージに装飾されていて、ロマンティシズム溢れる小品だ。
賜紀さんの演奏は、小さなホールで演奏する時よりも全体に音を大きく出していて、また大きなホール故に、音が朗々と響いていた。演奏自体も丁寧に弾いている感じでヴィブラートを豊かに効かせ、レガートも流れるよう。この大らかな歌わせ方こそが賜紀さんの真骨頂で、温かみのある音色と上品な響きがこの曲にピッタリ。また装飾的な速いパッセージも残響の中に一瞬閉じ込められるくらいの速さであったが、私にはすべての音符が正確に演奏されているのを聴き取ることができた。これは最前列ならではの利点だ。素晴らしい演奏だったと思う。
前半の最後は、同じパガニーニの「ヴァイオリンとギターのための協奏的ソナタ イ長調 作品61」。この「ソナタ・コンチェルタンテ」は1803年の作とされ、パガニーニがギターのための作品にもチカラを注いでいた時期に当たる。そのためか、ヴァイオリンとギターが同等に扱われていて、両者の掛け合いがあたかもヴァイオリニストとギタリストが対話するような雰囲気を醸し出す。この頃のパガニーニはギタリストの女性と恋仲だったと伝えられていて、なるほど優しげなギターのパートに比べると、ヴァイオリン・パートの方が情熱的に感じられる。一般的には音域から言ってもヴァイオリンが女性でギターが男性の方がイメージしやすいが、この曲はどうみてもヴァイオリンがパガニーニ自身を表しているように聞こえる。
第1楽書は冒頭から賜紀さんのヴァイオリンが鋭い立ち上がりで情熱的に聴かせてくる。それを奏一さんのギターがふわりと受け止める。第2主題のヴァイオリンは優しげな愛情表現のように優しい音色に変わる。展開部はあたかも恋人同士の対話のように、主客が目まぐるしく入れ替わる。この曲での賜紀さんの演奏は、いつもよりは鋭くエッジを立てて押し出してくる。対する奏一さんのギターは丸い音色で優しい。
第2楽章は短調に転じて、もの悲しい主題をヴァイオリンとギターが交互に弾く。愛し合う男女の未来に不運な要素が見え隠れしているのだろうか。対話しているようだといっても、異なる意見をぶつけ合っているのではなく、将来への不安を語り合っているようである。
第3楽章は、一転して明るく陽気な主題によるロンド。賜紀さんのヴァイオリンがぐっと明るい音色に変わり、弾むようなリズム感と、躍動的なフレージングが素敵。奏一さんのギターもとてもリズミカルでギターの持つ本来の陽性の部分と、スペインとは違う、イタリアっぽい明るさが素晴らしい演奏だ。
賜紀さんが語るには、パガニーニはヴァイオリンとギターの曲をたくさん書いているので、もっと色々な曲を紹介していきたいという。旋律を自由度高く歌わせることにかけては天下一品の賜紀さんだから、イタリア・オペラのアリアのような美しい旋律を書くパガニーニをもっともっと聴かせて欲しいものだ。

後半は、予定されていたプログラムに急遽追加するカタチで、奏一さんのギター・ソロで、お馴染みの「アルハンブラの思い出」が演奏された。奏一さんはこの曲を演奏する際には2小節だけ分散和音だけの前奏を加える。そして主旋律が美しいトレモロで紡ぎ出されていく。奏一さんはどちらかといえばテンポを揺らす方の演奏で、トレモロの主旋律を歌謡的に歌わせるのが特徴。上品でロマンティック。とても素敵な演奏だ。アンプ・スピーカーがなければ後方席までこの繊細な音色が届いたかどうか。
再び賜紀さんが登場して2曲目はバルトークの「ルーマニア民俗舞曲」。こちらも賜紀さんとしてはお馴染みのレパートリーで、ギター伴奏でも、ピアノ伴奏でも、しばしばプログラムに載せている。ハンガリー生まれのバルトークが、当時はハンガリー領だったルーマニアの各地から集めた民謡・舞曲を素材として、1915年に6曲のピアノ用小品にまとめた。その後管弦楽版にも編曲されている。後になってヴァイオリニストのセーケイ・ゾルターンがヴァイオリンとピアノ用に編曲したのが1926年のこと。今日の演奏は、それをさらにヴァイオリンとギター用に編曲にしたものということになる。
第1曲の「棒の踊り」では冒頭の奏一さんのギターが思ったよりも力強く低音と和音を押し出し、賜紀さんのヴァイオリンも力強く低弦で主題を弾く。主題が中音域に上がって行くと重音を艶やかに響かせるのが印象的だった。第2曲「飾り紐の踊り」ではヴァイオリンが自由度高く気ままに踊るよう。第3曲「足踏みの踊り」はヴァイオリンがフラジオレットだけで民族調の音楽を奏でるが、これは意外に難しいところ。第4曲「角笛の踊り」はロマン性豊かな曲想の美しい旋律が賜紀さんのヴァイオリンで艶っぽく語られていく。かなり色っぽく表情豊かな演奏である。第5曲「ルーマニア風ポルカ」と第6曲「速い踊り」はつながっていて、村人達が熱狂的に踊り狂っている様子を、軽快で躍動的なリズム感の賜紀さんのヴァイオリンが跳ねるように踊り、奏一さんのギターがそれを煽るようにリズムを刻む。全部合わせても7分程度の曲なのだが、ヴァイオリンがそれぞれの曲でまったく異なる色彩と表情を細やかに弾き分けているのにもかかわらず、全体をルーマニアの民族調の色合いにまとめ上げている。このようなところに賜紀さんのヴァイオリンの奥深いところがある。前半のパガニーニとは色彩感がまるで違う。それでいて、旋律が大らかに歌うところは共通したイメージも創り上げている。それこそが賜紀さんの個性というものだろう。
続いて舞台はアルゼンチンへと飛び、ピアソラの「オブリビオン(忘却)」という曲。こちらも元は映画音楽として書かれた曲で、1984年、イタリア映画『エンリコ4世』の中の挿入曲である。あいにくとその映画はまったく知らないが、曲の方は誰もがどこかで聴いたことがあるはず。感傷的でロマンティックな旋律が殊の外美しく、賜紀さんのヴァイオリンもすすり泣くような、息の長い旋律をヴィブラートをたっぷり効かせて、濃厚なニュアンスを込めていく。ギターのパートも非常に濃厚なロマンティシズムを湛えていて、奏一さんの上品な音色がむしろしつこさを打ち消していて、美しい響きを創りあげていた。
最後は同じピアソラで「タンゴの歴史」。アルゼンチン生まれのアストル・ピアソラ(1921〜1992)は、もとはバンドネオン奏者として名を馳せた人。つまりアルゼンチン・タンゴの演奏家だったが、パリに留学して西洋クラシック音楽の作曲法を学び、アルゼンチンに戻って伝統的なタンゴをクラシック音楽と融合させ世界に広めた。この曲は、元はフルートとギターのために書かれた曲であり、4つの楽章から成る。内容は標題通りで、1900年頃の酒場(Bordel=売春宿)で流行っていたタンゴ、1930年頃は当時流行のカフェでタンゴが流れ、1960年にはナイトクラブが主流になる。1990年のタンゴは現代音楽と化しコンサート会場でしか演奏されない・・・・といった風に20世紀の「タンゴの歴史」が描かれているのである。
第1楽章「酒場1900」はヴァイオリンのソロから始まるが、賜紀さんはアドリブを効かせて自由度の高いソロを聴かせる。それを受ける奏一さんもノリが良い。やがて伝統的なタンゴのリズムに収束していき、二人が息の合った軽快なリズム感で、ちょっと陰の射す陽気さの酒場(売春宿)に流れるタンゴが描かれて行く。
第2楽章「カフェ1930」はギターの序奏が、頽廃的で行き場のない世界観を描き出していく。ヴァイオリンの主旋律も悲観的なイメージが強い。演奏も湿り気を帯びた色彩感で、しっとりとした佇まいを見せる。中間部になると明るい曲想に変わり、不安感の中にも陽が射す時もあるのだとでも言いたげだ。ヴァイオリンもギターのこのような情感の変化を鮮やかな音色の変化で描き分けている。
第3楽章「ナイトクラブ1960」になると、タンゴは夜の世界に沈殿していく。見せかけの陽気さと虚飾に満ちた世界観。音楽は夜の世界のイメージを濃厚に漂わせながら、表向きはロマンティシズムを主張する。ふたりの演奏はそういった情感、あるいは情景をリアルに描き出している。
第4楽章「現代のコンサート」は、タンゴが無調で変拍子の現代音楽に進化(退化?)している様子を描く。それでも何となくタンゴに聞こえるのはさすがにピアソラならでは。賜紀さんの演奏する現代音楽はほとんど聴く機会がないのだが、この楽章のように現代音楽「風」に創られた曲であっても素晴らしい感性を発揮して、明瞭で鮮やかな演奏を聴かせてくれたのはさすがである。
今日のコンサートは「夜」がテーマだった(わけではない?)が、内容はヴァイオリンとギターによる音楽の世界紀行といったものになっていた。ドビュッシー(フランス)に始まり、モリコーネ(20世紀のイタリア)、パガニーニ(19世紀のイタリア)、バルトーク(ハンガリー/ルーマニア)、そしてピアソラ(アルゼンチン)という風に世界を回った。
そしてアンコールはスペインに飛び、ファリャの『スペイン民謡舞曲』から「ホタ」。本来の長さのコンサートであれば『スペイン民謡舞曲』も全曲演奏するところだろう。「ホタ」はヴァイオリンのピツィカートがギターのようにリズムを刻むかと思えば、歌謡的な旋律を大らかに歌いだす。その対比も鮮やかだし、ギターのパートもさすがに本国のスペインという感じがして、情熱的なのに感傷的で美しい演奏であった。
終演後は恒例のサイン会・・・・がなかった。実はこの日、大阪から賜紀さんファン仲間のKさんが聴きに来ていたので、お会いしないまま帰るのもちょっと寂しい、ということで、楽屋にお邪魔してみることに。もちろん係の人に了承を得てのことである。終演後のステージの裏側を通り抜けて(これも得がたい体験だ)楽屋に向かうと、何人かの面会者が訪れていた。ホールの撤収時刻は迫っていたようだが、いつものサイン会とは違って、急かされることなくゆっくりとお話しすることができて、とても嬉しい一時であった。Kさんも大阪から来た甲斐があったと大喜びであった。
賜紀さんは世界でもトップ・クラスのヴァイオリニストだといえるが、私たちのような者にも気さくに接してくれる。そのふんわりとしたお人柄が演奏にもよく表れている。今日は、大らかに歌うパガニーニや、土の香りのする民族調のバルトーク、エキゾチックなピアソラ、情熱的なファリャなど、文化の異なる様々な音楽を多彩な音色やリズム感を見事に使い分けて演奏してくれたわけだが、全体を通してみれば、楽曲の本質には深く迫りながらも優しくてエレガントな「川久保賜紀流」の演奏になっていて、それが何よりも魅力的なのである。