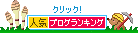4月も半ばを過ぎ、大学でもそろそろ本格的に講義が始まった頃かもしれません。法学の世界でよく出て来る言葉に「通説・判例」という言葉があります。通説とは、学界(・実務)の大方の人が従っている学説(・理論)のことを指します(なお、拙稿「『学説』を学ぶ」参照)。
定義の上では非常に簡単ですが、実際の見極めは容易ではありません。その一番の理由は、当該分野の全構成員がそれについて何らかの著述をしているというわけではないからです。また、対して関心のない分野であれば、「それでいいや」というような、人任せのような態度がないとも言えません。
法理論は、自然科学のような、「この世の真理」とは違うといわれているように、伝統的に「学派」が存在しています。パッと上げると、東大・京大・慶應・早稲田などがそれぞれ学派を形成しており、その重鎮がどのような学説に賛成しているかによって、その学説の「力」を判断することが少なくありません。つまり、これらの学派の重鎮の多くが賛成している学説が「通説」だとされることも少なくないのです。
そうすると、本当の意味での「通説」が何なのかは分かりません。実際に、ある書籍では当該の学説が「通説」だと書かれているのに、他の書籍では「有力説」と書かれていることもあります。
このような状況は、ますます学説の重要性を、とりわけ法学学習者から奪ってしまうように思われます。なぜなら、多くの法学学習者は、眼前の試験などを気にしているのであって、そこまでに積み上げられてきた人間の叡智なるものには大して関心を払っていないように見えるからです。そうだとすれば、法学の学習は、「条文の暗記」を否定するだけで、「判例の暗記」を否定できなくなってしまいますし、それは結局のところ、法学を「つまらない学問」化させてしまうだけです。
さらにめんどくささを感じさせるのは、分野を限った「○○での通説」という言葉の存在であり、例えば、「民法学説での通説」とか、「実務上の通説」とか、「学界上の通説」という言葉が存在しているところです。それは、通説が、学理上の「普通」なのであって、その意味で「枠はめ」を可能とするからです。つまり、ある集団においては「普通」であるが、他の集団ではそうではないということがあり得るのです(拙稿「常識・非常識」参照)。
このように見てくると、「通説」という言葉がいかに危うい基礎の上に成り立っているかということが分かるかと思います。しかし、学習段階においてこの言葉からは逃れられません。だからこそ、「通説」という言葉を使うのには、一定の配慮が必要なのです。