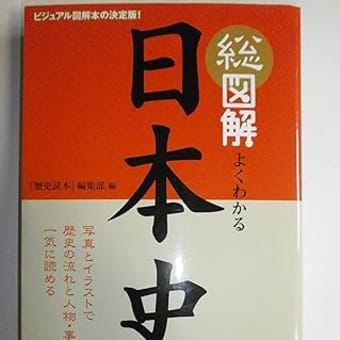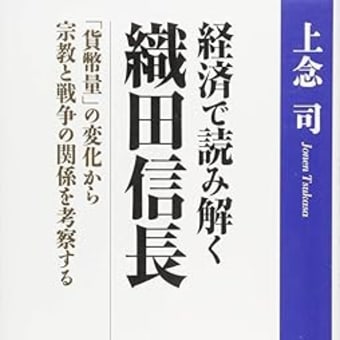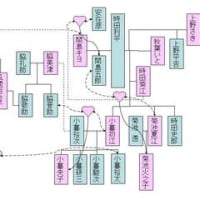心の底に浸みこむような、記憶に残りそうな小説である。
登場人物は多くない、中心になるのは執事のスティーブンス、1920年ころに勤めていたのがダーリントンホールと呼ばれる大邸宅、その主ダーリントン卿、そして小説でいう現在の館の主は新しく邸宅を購入したというアメリカ人ファラディー。物語はダーリントン卿が健在だった第一次世界大戦後の世界の秩序を定めようとしている時代に、英国人であるダーリントン卿が、古くからの友人がいたドイツになんとか早く立ち直ってほしいと尽力する姿を、自分の執事としての活躍した時代と重ね合わせて追想する。
その時に執事のパートナーとして活躍し、そして執事との間にある種の緊張感と連帯感を感じていたミス・ケントン。そのミス・ケントンから手紙をもらったスティーブンスは、現在の邸宅における人出不足を解消したいということを口実に、主人のフォードを借りてミス・ケントンの現在の嫁ぎ先まで数日の旅をして、二十数年ぶりに会って話をする、という内容。
旅の中で、スティーブンスは自分が長く勤めてきたダーリントンホールでの様々なできごとと、執事としての振る舞いや考え方はどうあるべきかを考える。主人あっての執事、いかに自分の考えと異なっていても、主人の意向が何といっても最優先、自分の父親の死に目に立ち会えないとしても。執事の仕事を優先してきたことを思い出す。父が卒中で倒れた日は、まさにご主人が開催する重要な会議の真っ最中、その勤めを果たし終えたことを自分の執事としての誇りに思っている。ダーリントン卿は、ドイツの復興が世界の平和につながるという信念から会議を主催していた、そのお手伝いができる自分は、執事としての最高を仕事ができていると信じる。
その時に女中頭をしていたのがミス・ケントン、彼女は執事として立派に働くスティーブンスを尊敬しており、心を惹かれながらも、自分も女中頭という責任を果たすためには、執事という立場のスティーブンスと一緒になるなどということは考えることもできないという観念をもっていた。それでも、心は惹かれる。思いを告げることなく、別の人と結婚して離れた場所に暮らしてきたミス・ケントン。出会ってミス・ケントンはその頃の自分の思いをスティーブンスに打ち明ける。
ミス・ケントンの告白に、スティーブンスはハッと気が付く。自分も隠してきたはずの思いがここにあったことを。しかし、ミス・ケントンも幸せそうな結婚生活を送り、自分もすでに高齢、人生の夕暮れに差し掛かっている。旅の終わりに桟橋の向こうに落ちる夕日を眺めて、過ぎ去ってしまった自分の人生を振り返るスティーブンス。夕方の眺めは一日の中でも格別に美しい時間であること、自分に言い聞かせる。
テレビドラマなどの陳腐な言い回しでいえば仕事と恋。それにしても「日の名残り」、なんという切ないお話なんだろう。イギリスにおける執事、という職業のもつ意味を深くは理解できないまでも、想像はできる。小説の中には、立派な職業であるという信念とともに、旅で出会った人から、「立派な車に乗った紳士」と評価される一方、「どなたかの召使だったのではないか」とも推測されるスティーブンス。その執事という仕事に一生をかけて打ち込んできた自分の一生である。悔いのあるはずがない。
ノーベル賞受賞のニュースを聞いて、ちょっとミーハーな気もしたが読んだことのない作家の小説をKindle版を購入した。私と同じ年だというこの作家の日本への思いを書いたという他の作品、ぜひ読んでみたい。