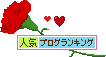「雪玉投げはスンジョ君に負けないから。」
「お前にオレが負けるはずがない。」
オレは負けるはずがない。
負けるはずはないが子供のような遊びに不慣れなオレと、遊びなれているハニの子供みたいに雪玉投げを楽しんでみるのもいいかもしれない。
「いい大人が、恥ずかしくないのかしら。」
ハニと過ごした時間を思い出していた時、それを止めるような言葉に今自分のそばにいる人が誰なのか気が付かせられた。
「そう思いません?」
広い空き地に積もった雪を、大学生くらいのカップルが雪玉投げをして遊んでいた。
「大学時代、オレも雪玉投げをしましたよ。」
待ち合わせの時に話していたミヒュンの様子から、今まで知っていた彼女と違った感じがしたからなのか、それともハニとの思い出の雪玉投げを思い出していた時に聞いた彼女の言葉にムッとしたのかミヒュンの言葉に冷たく言い返した。
さすがにスンジョはまずかったと思い、作り笑顔で横を向いてすぐに言葉を続けた。
「たまには子供に戻ってみるのもいいですよ。いつも背伸びをして、人に表面だけを見てもらうのは疲れます。」
ミヒュンは無言だった。
姉に負けたくないという思いで、子供のころから背伸びをしていた。
いい子でいたい、姉のようにほめられたい。
結局、姉には勝つ事も前を歩く事も出来ない。
子供が親を抜けないように、兄弟も年下の者が年上の者をどう頑張っても全てにおいて追い越す事など出来ないのだから。
「オレは小さいころから手がかからない子供だと、周囲の人から言われていた。最初はそれが嬉しかったが、次第にそれが当たり前の事で、こうでなければいけないと言う型にはまる考えになっていた。一見それが完璧な人間とされていても、そうではない事に気が付く。完璧でいる事に疲れたと思った時、たまには子供に戻ってバカになるのもいいと教えてくれた人が出て来た。」
「お前にオレが負けるはずがない。」
オレは負けるはずがない。
負けるはずはないが子供のような遊びに不慣れなオレと、遊びなれているハニの子供みたいに雪玉投げを楽しんでみるのもいいかもしれない。
「いい大人が、恥ずかしくないのかしら。」
ハニと過ごした時間を思い出していた時、それを止めるような言葉に今自分のそばにいる人が誰なのか気が付かせられた。
「そう思いません?」
広い空き地に積もった雪を、大学生くらいのカップルが雪玉投げをして遊んでいた。
「大学時代、オレも雪玉投げをしましたよ。」
待ち合わせの時に話していたミヒュンの様子から、今まで知っていた彼女と違った感じがしたからなのか、それともハニとの思い出の雪玉投げを思い出していた時に聞いた彼女の言葉にムッとしたのかミヒュンの言葉に冷たく言い返した。
さすがにスンジョはまずかったと思い、作り笑顔で横を向いてすぐに言葉を続けた。
「たまには子供に戻ってみるのもいいですよ。いつも背伸びをして、人に表面だけを見てもらうのは疲れます。」
ミヒュンは無言だった。
姉に負けたくないという思いで、子供のころから背伸びをしていた。
いい子でいたい、姉のようにほめられたい。
結局、姉には勝つ事も前を歩く事も出来ない。
子供が親を抜けないように、兄弟も年下の者が年上の者をどう頑張っても全てにおいて追い越す事など出来ないのだから。
「オレは小さいころから手がかからない子供だと、周囲の人から言われていた。最初はそれが嬉しかったが、次第にそれが当たり前の事で、こうでなければいけないと言う型にはまる考えになっていた。一見それが完璧な人間とされていても、そうではない事に気が付く。完璧でいる事に疲れたと思った時、たまには子供に戻ってバカになるのもいいと教えてくれた人が出て来た。」
胸のあたりで、ハニの指輪が素肌に感じた。
ハニがいなければ、今のミヒュンのように雪玉投げをしているカップルを、くだらない奴らだと思っていたかもしれない。
「その人は、その指輪の人?」
シャツの下にある指輪は、ミヒュンには見えないがスンジョがいつも何かの時に手で触れているのは知っていた。
「そうです・・オレに人として必要な事を教えてくれた女性です。」
ハニがいなければ、今のミヒュンのように雪玉投げをしているカップルを、くだらない奴らだと思っていたかもしれない。
「その人は、その指輪の人?」
シャツの下にある指輪は、ミヒュンには見えないがスンジョがいつも何かの時に手で触れているのは知っていた。
「そうです・・オレに人として必要な事を教えてくれた女性です。」