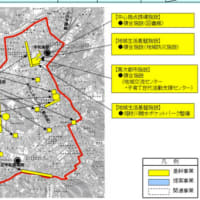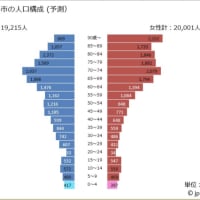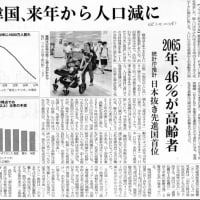【読書日記から15】
1) Collins「Pocket Arabic Dictionary」(Harper Collins, 2011)=
これは丸の内丸善で買った新書サイズの「英・ア辞書」で、ギリシア語が字引を引きながらなんとか読めるようになったので、アラビア語に挑戦しようと思っている。現代アラビア語には欧米語や日本が入っているので、思ったほど単語は難しくない。面倒なのはアラビア文字だ。
で、あれは右から左に書くが、辞書も英語引きの部分は左からページ番号が振られ、ア英の部分は裏表紙から始まるページ番号が振られている。(縦書きの日本語本と同じ。)
英語側は218頁で終り、アラビア語側は247頁で終わる。両者の中間に、英語とアラビア語で書かれた文法解説がある、という何とも不思議な辞書だ。
英語で書かれた文法編を読むと、「アラビア語には不定冠詞がなく、定冠詞がないものは不定詞である。名詞の前には定冠詞アル(al)がつく」と書かれている。だから固有名詞でもアルが付くのか、と納得できた。
そこで英語の「アルコール(alcohol)」を引くと、アラビア語では「コホル(kohol)」とある。「ははーん」 とピンときた。これに定冠詞をつけるとalkoholとなるから、西洋人が間違えたのだな、と分かったのである。エイズ(AIDS)はAl-eiidz、空手はkaraatihとなっている。最後から2番目の音節にアクセントが置かれているのは、ラテン語と同じである。
アルは定冠詞であると同時に、名詞を後に伴いラテン語的に形容詞をつくるにも用いられるようだ。例外的にクレジットカードは、「信用」が「イートマン」、カードが「カルト」で、「カルト・イートマン」となる。この場合はアルが付かない。
病気は「マラド」でラテン語と同じ。アルツハイマー病は「マラド・アルツハイマー」となる。固有名詞はスペインのことは「イスバーニャ」というのに、日本は「アル・ジャバ−ニュ」というのも面白い。印欧語のp音はアラビア語ではb音に変化しているものが多い。
アラビア・アルファベット最初の文字は、フェニキア文字と同じで「アレフ」という。
(フェニキア文字ではV,アラビア文字ではLと書く。Vを逆さまにして横一を加えるとAになり、これがギリシア・アルファベットのΑ=アルファになる。)
フェニキア文字のアレフは家畜の「牛」を意味していた。これはVに牛の角を意味する横棒のある象形文字が起源である。北フェニキア文字ではAとなりアナトリア地方をへて、イオニア経由でアテネに入った。砂漠地帯のアラビアには南フェニキア文字のVのままで伝わった。Vを変形させてLになったのである。
「オウム」の後継団体「アレフ」はフェニキア語にちなむ。もともと「オウム」は「A-Um」のカタカナ表記で、「アルファとオメガ」=「始まりと終わり」を意味している。梵語では「アウム:阿吽」という。)
ギリシア語のオメガ(Ω)に相当する最後の文字が、アラビア語では、Sの下に点が二つついた文字でYに相当し、「イヤーyear」のyという音になる。
この辞書の前半部は、英語からアラビア語の英語スペルとアラビア語スペルが引け、後半部はアラビア綴りから、アラビア語発音と該当する英単語が引けるようになっている。
「サン(太陽)文字」と「ムーン(月)文字」(発音する文字が太陽文字、発音しない文字が月文字)というのがあるのには驚いたが、よく考えたらフランス語のHを無声(アッシュ・ミュエ)で発音するか、有声で発音するかの違いと同じだ。日本語にも同様な現象があり、「土肥」をDohiと発音する場合と、Doiと読む場合がある。思ったより、アラビア語は易しそうだ。
2)前嶋信次:『アラビアの医術』(平凡社ライブラリー、1996/5)=
『アラビアン・ナイト』全18巻と別巻「アラジンと魔法のランプ・アリババと48人の盗賊」をアラビア語原本から訳出するという大業を達成した前嶋には、こういう中世アラビアの医学・医術についての本もある。
これにアラビア医学の万能薬「テリアカ(Theriaca)」のことが書いてある。
万能解毒剤として開発されたテリアカ(アラビア語「ティヤカ」)が「万能薬」とされ、インドをへて中国に伝わり「底也伽」ないし「底野迦」と標記されるようになり、日本にも伝えられて、平安時代の医書『医心方』にも記載されているという。
古代のギリシア諸国は、アテネとスパルタの間の「永久戦争」ペロポネソス戦争で疲弊した後、マケドニア王国に征服された。征服したのはアレクサンダーの父、フィリッポス二世王である。BC334年に始まったアレクサンダーのインド遠征が10年続き、彼がペルシアの首都バビロンで急死した後、後継の武将たちの「ディアドコイ戦争」が続き、アレクサンダー帝国はエジプト、シリア、ペルシア、小アジア、ギリシアなどに分裂し、「ヘレニズム時代」が始まった。
この時、ギリシア諸国の学者たちは多く、先進国シリアやエジプトに移住した。前1世紀にローマが帝国化して東に領土を広げ、ギリシア、マケドニアを併合すると、この傾向はさらに強まった。
この頃、小アジアのペルガモン王国を併合しポントス王国の王となっていたのが、ミトリダテス6世である。在位56年間、うちローマとの戦争が40年という。ミトリダテスは毒薬による暗殺を恐れ、毒物とその解毒法について研究を重ねた。
ミトリダテスの毒殺対処法の基本は、「毒をもって毒を制する」もので、普段から各種の毒薬を少量服用し、「身体に耐性をつける」ものだった。また57種の薬草などを混合して万能解毒剤「テリアカ(Theriaka)」を開発した。これは「大テリアカ」とも呼ばれる。この手のものにはあと、「小テリアカ」とミトリダテスにちなむ「ミトリダテアェ」がある。砂糖はまだ知られていなかったが、ミトリダテアェ(解毒剤)は、植物や蜂蜜の糖類を利用して毒を吸着させ、無効にするものであったらしい。化学でいう「アマドリ反応」である。
ローマ皇帝ネロは暗殺を恐れていた。その侍医クレタのアンドロマコスがテリアカをより改良し、その知見は古代医学の集大成家ガレヌスに受け継がれたという。
語源的にはギリシア語のtherionは「獣」を意味し、theriakaは「獣の咬み傷」に対する薬のことだった。解毒を意味するアンチドート(Antidote)が、ギリシア語のanti-(抗して)とdodonai(与える、投与する)との結合から成り立っているのと、少し異なる。
独裁者が医学・医療を好み、自ら健康法を唱道する例は、アレクサンダー大王やヒトラーにもみられる。ヒトラーは、自らは不眠症で睡眠剤の常用者だったが、禁酒・禁煙を唱えて周囲にもそれを強いた。ネロもミトリダテスも同様である。『日本書紀』には、武烈天皇が妊婦の腹を割いて胎児を見たとか、罪人の生爪を抜いて芋を掘らしたとか、罪人をダム湖の溝に寝かせて鉄砲水で流されてくるのを刺し殺したとか、残酷奇抜な話が書いてあるが、これも独裁者のある種の好奇心とからんでいる可能性がある。
万病薬テリアカがあるに対して、万病治療法パナケア(Panacea)がある。パナケアはもともとは医神アスクレピオスの娘であり、アスクレピオスの代理人である蛇の世話をしたという。そういうわけで、今でも医術のシンボルは世界的に「木の杖に巻き付いた蛇」になっている。呉市には「老人介護施設パナケイア」というのがある。理事長は医学史に詳しい人であろう。
語源的にはtheriacaのther-はTherapia(治療)とも語根が共通しており、初め「外傷の特効薬」の意味だったが、次第に「毒消し」(アンチドート)の意味でも用いられるようになった。
ヨーロッパの中世になると、病気を予防するという思想も生まれ、「万病を予防し、治療する」 「パナケイア(pana-keia)」が探し求められた。Pana(すべて)+keia(cure:治癒させる)というギリシア語からのラテン造語である。14世紀における西欧でのペスト大流行は、人々を恐怖のどん底に追いやり、合理的な思想が失われ、オカルト的、魔術的なものが受け容れられやすくなっていた。
世界史的に見ると、アラビア医学は、西ローマ帝国が滅んだ5世紀から12世紀の中世ルネサンスまで、ギリシアの科学や医学を保存し発展させる役割を果たしたが、ガレヌスの神秘主義がそのまま受け継がれ、ルネサンス期にアラブ医学文献がスペインのコルドバなどでラテン語に翻訳される際に、さらにイスラーム神秘主義の思想が入りこんだことは疑えないだろう。
ここで梶田昭『医学の歴史』(講談社学術文庫, 2003/9)の話を挿入する。
これはわずか360ページの文庫本だが、1万年前の人類のあけぼのから「戦争の世紀」20世紀までの医学の変遷を、分かりやすく衒学的でなく述べた大変な名著だ。
アラビアの医術はテリアカだけでなく、植物、動物、鉱物を、医薬として積極的に活用したので知られる。まだ抽出法が未発達で、せいぜい煮沸、発酵程度の化学処理しかできなかったが、当時の薬種商が扱っていた品目を見て、宝石と各地の土の粉末や石油までが医薬品材料として扱われていて驚いたことがある。まさに「化学はアラビアの地から始まったな」と思った。
(この表の視覚的イメージは残っており、3ページわたっていたのだが、本の名前を忘れてしまったので、書棚から本が見つからない。読んだ時に「読書目録」の「内容要約欄」にメモしておけばよかった。)
前嶋本の解説を三木亘(中東歴史生態学者)という人が書いているが、日本でも1973年頃はテリアカがまだ売られていて、滋賀県甲賀の置き薬屋で買ったそうだ。練り薬が貝殻の容器に入っていたという。戦中や戦後すぐの練り薬(薬用クリーム)はハマグリの貝殻に入っていたのを記憶しているが、高度成長期にも貝殻が使われていたとは知らなかった。伝統の秘薬だから、その方に効き目があったのだろう。
さて話を戻す。万病治療法(パナケイア)も万病特効薬(テリアカ)も存在するはずがない。
薬はその化学成分が効くので、ここでの化学成分とは水に溶けた化学分子のことである。薬となる化学分子は細胞表面にある受容体と特異的に立体化学的に結合する。それによってある特定の細胞や器官に薬理学的反応が起こるのである。すべての細胞に非特異的に反応するものは、タンパク質を非特異的に変性させるホルマリンや、細胞外濃度を高めることでナトリウム・ポンプを停止させるカリウム・イオンのようなものしかない。青酸カリは胃粘膜の細胞により吸収されないと効果を発揮しないが、ホルマリンもカリウムも注射すれば即死する。
そういう「ありえない薬」や非合理な治療法が流行することを、梶田は丸山真男『日本政治思想史研究』(東大出版会、1952)における、「政治がなりたつ社会的状況の2限界」という理論のアナロジーを用いて見事に説明している。丸山理論はおよそ次のようになる。
<世の中が安定していて、秩序に信頼が支配的である間は、政治は必要とされない。反対に社会変動により既存の支配体制に動揺が生じると、敏感な思想家に危機の感情が生まれ、「政治の季節」がやってくる。
その逆に、社会が混乱と腐敗により絶望的な段階に至ると、もう「政治」の出る幕がなくなり、社会からの逃避と頽廃が主流となる。
「政治」が有効に機能するのは、この二つの限界の間においてのみである。>
私は丸山のこの本を読んでいないが、梶田の記述から自己流の理解をすると、危機意識を感じているのが安倍晋三という政治家であり、若手右派の思想家中野剛志であろう。
他方、「逃避と頽廃」現象は、多発する高校生・中学生による殺人事件や「後妻業」で次々と夫を毒殺したとされる事件に端的に表れている。
この丸山の考え方に依拠して、梶田は「政治」を「医学」と読み換え、
<人間は健康で、心身共に体調がよい間は、社会思想において「秩序が信頼される」のと同様に、俗信や常識に依拠して生活している。しかし社会的危機が発生した場合に政治が必要とされるように、身心の危機に際して「医学」を求める。この希求には「科学に対する期待」と同時に「願望」が含まれている。
もし身心の危機が医学により解消されず、一層危機が深まり「混乱」の状態になると(例えば進行がんで余命告知を受けるなど)、合理的思考が再び影を潜め、「呪術・宗教」に頼るようになる。>という。
これは社会的頽廃に際して、オウム真理教などのオカルトが流行るのと同じである。現在も、若者による不可解な殺人事件が多発しているのは、やはり社会的危機の表れだろう。不治の病を宣告されて、神仏に頼ったり、いかがわしい「代替療法」や「民間治療」に走る患者は多い。STAP細胞がブームになったのは、メディアが「不老不死も夢ではない」などと煽ったからである。
梶田は
<医療は、病気ないし死から免れようとする人間の本能的欲求に応えようとするが、それを科学的に実現する能力との間に、絶望的な隔たりがある。それをなんとかして埋めようとする過程が、医療史ないし医学史であった>という医学史家、川喜田愛郎の指摘を受けて、
<もともと医学には「悩む(patior)」ことの学という意味と「癒やす(medeor)」ことの学という二面性があった。悩みは現実であり癒しは理想だが、medeorが名詞化したmedicinaが主流となり「医学(medicine)」という「理想」が勝利した。他方、patiorという「現実」の研究の方はpathologia(病理学)が引き受けた。(この「病理学」は広義のもので、寄生虫学、細菌学、ウイルス学、法医学、病態生理学などを含む。)
だが医学にとっても病理学にとっても、荷が重すぎた。できることは「悩み」に対する「慰め」なのに、たまにしかできない「癒し(medeor→medicine)」を看板に掲げたところに、医学の宿命的な辛さがある。> という。
梶田のこの書は深い思索の産物であり、全体が見事に統一されている。そこには病理学だけに偏した「悪しき専門分化」はない。これを読んだ後か、あるいは手許に置いて、前嶋の『アラビアの医術』を読むと、前嶋の博識が立体的、総合的に理解できるだろうと思う。
3)一坂太郎:『吉田松陰とその家族:兄を信じた妹たち』(中公新書、2014/10)=
NHK大河ドラマを当て込んで出版された本だ。手持ち本は年末に買った初版本だが、いまは増し刷を重ねているだろう。ドラマとの関係で余計な副題がついているが、基本は松蔭の短かった一生を描き、その中に家族の話や同輩や弟子たちのことがわかりやすく、よく書き込まれている。
当時の長州藩下級武士の暮らしの有り様、萩城下の地図、松蔭の生家杉家の家系図、次男だったの杉家から代々縁がある吉田家に養子に入ったこと、実の妹が久坂玄瑞と結婚したこと、実兄梅太郎の娘が乃木家に嫁いだこと、叔父文之進が玉木家に養子に入っており、玉木文之進であること(玄瑞は「禁門の変」で、文之進は「萩の乱」でともに破れて自殺)がわかる。
(家系図は左に年長者を書くのに、これは逆になっている。「系図学」は西洋からの輸入学問だから、左から書くのが正しい。)
年表もあり、理解を助けるのに役立つ。
吉田松陰の著書には『講孟余話』、『松蔭書簡集』(以上岩波文庫)、遺著『吉田松陰・留魂録』(古川薫:全訳注、講談社学術文庫)がある。「留魂録」には、古川による伝記が含まれている。
下関の作家古川薫は文章がくどいので、「史伝・吉田松陰」は読まなかった。
だから松陰のアメリカ密行の失敗と野山獄への幽閉、「松下村塾」開講の話と、江戸伝馬町の牢屋に入れられ、29歳で斬首され(切ったのは山田浅右衛門)、死骸を小塚原刑場に捨てられた話が、いきさつ、経時的な進行など、どうもよく理解できていなかった。
今回、この一坂本を読んで事情が腑に落ちた。浦賀でペリー艦隊の船に乗り込もうとして失敗、萩送りになり野山獄に送られ、後に実家の杉家に幽閉された。
ところが、「安政の大獄」が始まり、再び容疑者として江戸送りになった松陰は、幕府取り調べ役人が攘夷に好意的であると誤解し、京都で過激派浪士摘発を指揮している老中間部詮勝の暗殺計画を自白してしまった。これが、大老伊井が直接筆を執り「島送り」を「殺」に、処分を書きかえる決定的理由になった。
こうして本気で「攘夷」を実行しようと考えた主だった連中は、佐久間象山、高杉晋作、坂本龍馬などみな死んでしまった。「大政奉還」に成功した生き残り組は、いざ自分たちが権力の座につくと、「維新開国」と称して幕末の幕府の政策を受け継いで発展させた。つまり180度主張を変えたわけで、立派な裏切りだ。
松陰の『留魂録』に処刑前日に書いた「今日死を決するの安心は、四時の循環において得る所あり」で始まる有名な文言がある。四時は春夏秋冬の季節をいう。植物の一生から死生観を学んだというのだ。人生を「禾稼(かか=稲のこと)」になぞらえて、春の種まき、夏の苗植え、秋の稲刈りがあり、冬は穀物として蓄えられるという4つの季節がある。
だけれども「人寿定まりなし、禾稼のかならず四時を経るが如きにはあらず。十歳にして死するものは、十歳中おのずから四時あり」という。
奇書『人間臨終図鑑』(徳間書店、1986:現、徳間文庫, 全4冊)で古今東西800余人の「死に様」を記載した山田風太郎は、「十代で死んだ八百屋お七、アンネ・フランク、天草四郎、藤村操、ジャンヌ・ダルクから始まり、みなそれぞれに人生が完結している。もうちょっと生かしておきたかったのは織田信長だけだ」と述べている。
言葉は異なるが、松陰と「戦中派天才老人」風太郎は、期せずして同じ死生観に到達している。風太郎も渉猟濫読の人だったから『留魂録』は、読んだにちがいないと思う。しかし図鑑の松陰の死についての記載からは、この文言に影響を受けたとはうかがわれない。
松陰の遺体は四斗樽に入れられ、小塚原に捨てられた。弟子の桂小五郎や伊藤俊輔(博文)らが死体を引き取りに行ったら、首なしの松陰の遺体は棺の中に坐り、自分の首を膝に抱えていたという。これが1859年、今より160年前には、日本も「イスラム国」と同じことをやっていたわけだ。ベッカリアが『犯罪と刑罰』を書いて死刑の不当性を訴え、イタリア北部の小国サン・マリノが初の死刑廃止に踏み切ったのが1848年、松陰の処刑の11年前だ。以来ヨーロッパのEU加盟国は、すべて死刑を全廃した。
日本の死刑判決における誤診率は1%以上ある。「病気腎移植」による、がん持ち込みの危険性どころではない高率だ。だが、最近の総理府世論調査によると、国民の80%が死刑賛成だという。「イスラム国」では、判決を下した人間が自ら処刑を行うからまだましだ。
日本では「死刑執行人」は拘置所の「刑務官」という他人だから、平気なのだろう。「極刑に!」と叫ぶ遺族を処刑台に呼び、落とし台のレバーを引っ張らせてやるがいい。さぞかし復讐心が満足させられることだろう。
この本は、そういうことも考えさせてくれる。吉田松陰という人は、残された肖像画や実兄、実弟、実妹、実母の写真を見ると、面長で鼻筋が高く、いわゆる「長州顔」ではない。蒙古ヒダも肉親の多くに欠損しており、縄文系=古モンゴロイド系ではないかと思われる。
楽しく読める、お薦めの一冊だ。
4)長澤和也:『魚介類に寄生する生物』(成山堂書店、2001/4)=
例の「イワシの味噌煮」缶詰にいた「寄生虫?」の正体を突きとめるために、アマゾンに注文しておいた本だが、やっと届いた。もう脊髄と中腎という結論が出た後だが、晩酌をしながらひととおり目を通した。わかりやすい文章で写真や図解も多く、索引もありよい本だ。
著者は1952年生まれで、東京水産大の「増殖学科」を卒業した後、東大農学系大学院で農学博士をもらっている。北海道水産試験場勤務の後、キール大海洋研に留学し、帰国後は農水省「遠洋水産研」で働いている。
本書では軟体動物の貝類、イカ・タコ類と節足動物のエビ・カニ・シャコ類、原索動物のホヤ類、それに脊椎動物では硬骨魚類と軟骨魚類の寄生虫が扱われている。
イワシやサバに寄生する「環形動物」がいるかと思ったら、ゴカイの仲間(多毛類)の中に、カニに寄生するものがいるそうだ。
非常に面白いと思ったのはフィロネーマ(たぶんPhilonemaという学名だと思う。Philo-:好む、nema:糸の合成語だろう)という線虫がいて、淡水期にベニザケに寄生する。だが、海に下ったベニザケは海洋中で1〜4年を過ごし、成体にならないと元の淡水に戻らない。もし
フィロネーマが通常のライフサイクルを営んでいると、海水中で産卵しなければならないが、この幼虫は海水では生きられないし、ベニザケに感染できない。
そこでこの線虫は冬眠に入って、宿主が成熟するまで発育を停止するのだそうだ。まあ、冷凍卵子のようなものだろう。で、ベニザケが成熟し、生殖準備活動に入り、川を遡上し始めるとサケが出す性ホルモンが目覚まし時計となり、線虫も眼を覚まして生殖準備活動に入るのだそうだ。フィロネーマの中間宿主はケンミジンコで、湖水域でこれを食ったベニザケに感染し、新たなライフサイクルが始まるというわけだ。こういう風に宿主のライフサイクルにシンクロナイズする寄生虫は、他にもいるにちがいない。
ヒトに感染する魚介類由来の寄生虫としては、線虫のアニサキスが圧倒的に多い。特に「イカの刺身」が危ないとは知らなかった。冷凍物なら大丈夫だそうだ。
180ページ程度の本だが、プラクティカルな知識に充ちているので、開業医さんのオフィスにも一冊あると、患者が「先生これ何?」と持ち込んできた時に、うろたえないですむだろう。
約20冊の、より詳しい参考書があげてあるのもよい。
1) Collins「Pocket Arabic Dictionary」(Harper Collins, 2011)=
これは丸の内丸善で買った新書サイズの「英・ア辞書」で、ギリシア語が字引を引きながらなんとか読めるようになったので、アラビア語に挑戦しようと思っている。現代アラビア語には欧米語や日本が入っているので、思ったほど単語は難しくない。面倒なのはアラビア文字だ。
で、あれは右から左に書くが、辞書も英語引きの部分は左からページ番号が振られ、ア英の部分は裏表紙から始まるページ番号が振られている。(縦書きの日本語本と同じ。)
英語側は218頁で終り、アラビア語側は247頁で終わる。両者の中間に、英語とアラビア語で書かれた文法解説がある、という何とも不思議な辞書だ。
英語で書かれた文法編を読むと、「アラビア語には不定冠詞がなく、定冠詞がないものは不定詞である。名詞の前には定冠詞アル(al)がつく」と書かれている。だから固有名詞でもアルが付くのか、と納得できた。
そこで英語の「アルコール(alcohol)」を引くと、アラビア語では「コホル(kohol)」とある。「ははーん」 とピンときた。これに定冠詞をつけるとalkoholとなるから、西洋人が間違えたのだな、と分かったのである。エイズ(AIDS)はAl-eiidz、空手はkaraatihとなっている。最後から2番目の音節にアクセントが置かれているのは、ラテン語と同じである。
アルは定冠詞であると同時に、名詞を後に伴いラテン語的に形容詞をつくるにも用いられるようだ。例外的にクレジットカードは、「信用」が「イートマン」、カードが「カルト」で、「カルト・イートマン」となる。この場合はアルが付かない。
病気は「マラド」でラテン語と同じ。アルツハイマー病は「マラド・アルツハイマー」となる。固有名詞はスペインのことは「イスバーニャ」というのに、日本は「アル・ジャバ−ニュ」というのも面白い。印欧語のp音はアラビア語ではb音に変化しているものが多い。
アラビア・アルファベット最初の文字は、フェニキア文字と同じで「アレフ」という。
(フェニキア文字ではV,アラビア文字ではLと書く。Vを逆さまにして横一を加えるとAになり、これがギリシア・アルファベットのΑ=アルファになる。)
フェニキア文字のアレフは家畜の「牛」を意味していた。これはVに牛の角を意味する横棒のある象形文字が起源である。北フェニキア文字ではAとなりアナトリア地方をへて、イオニア経由でアテネに入った。砂漠地帯のアラビアには南フェニキア文字のVのままで伝わった。Vを変形させてLになったのである。
「オウム」の後継団体「アレフ」はフェニキア語にちなむ。もともと「オウム」は「A-Um」のカタカナ表記で、「アルファとオメガ」=「始まりと終わり」を意味している。梵語では「アウム:阿吽」という。)
ギリシア語のオメガ(Ω)に相当する最後の文字が、アラビア語では、Sの下に点が二つついた文字でYに相当し、「イヤーyear」のyという音になる。
この辞書の前半部は、英語からアラビア語の英語スペルとアラビア語スペルが引け、後半部はアラビア綴りから、アラビア語発音と該当する英単語が引けるようになっている。
「サン(太陽)文字」と「ムーン(月)文字」(発音する文字が太陽文字、発音しない文字が月文字)というのがあるのには驚いたが、よく考えたらフランス語のHを無声(アッシュ・ミュエ)で発音するか、有声で発音するかの違いと同じだ。日本語にも同様な現象があり、「土肥」をDohiと発音する場合と、Doiと読む場合がある。思ったより、アラビア語は易しそうだ。
2)前嶋信次:『アラビアの医術』(平凡社ライブラリー、1996/5)=
『アラビアン・ナイト』全18巻と別巻「アラジンと魔法のランプ・アリババと48人の盗賊」をアラビア語原本から訳出するという大業を達成した前嶋には、こういう中世アラビアの医学・医術についての本もある。
これにアラビア医学の万能薬「テリアカ(Theriaca)」のことが書いてある。
万能解毒剤として開発されたテリアカ(アラビア語「ティヤカ」)が「万能薬」とされ、インドをへて中国に伝わり「底也伽」ないし「底野迦」と標記されるようになり、日本にも伝えられて、平安時代の医書『医心方』にも記載されているという。
古代のギリシア諸国は、アテネとスパルタの間の「永久戦争」ペロポネソス戦争で疲弊した後、マケドニア王国に征服された。征服したのはアレクサンダーの父、フィリッポス二世王である。BC334年に始まったアレクサンダーのインド遠征が10年続き、彼がペルシアの首都バビロンで急死した後、後継の武将たちの「ディアドコイ戦争」が続き、アレクサンダー帝国はエジプト、シリア、ペルシア、小アジア、ギリシアなどに分裂し、「ヘレニズム時代」が始まった。
この時、ギリシア諸国の学者たちは多く、先進国シリアやエジプトに移住した。前1世紀にローマが帝国化して東に領土を広げ、ギリシア、マケドニアを併合すると、この傾向はさらに強まった。
この頃、小アジアのペルガモン王国を併合しポントス王国の王となっていたのが、ミトリダテス6世である。在位56年間、うちローマとの戦争が40年という。ミトリダテスは毒薬による暗殺を恐れ、毒物とその解毒法について研究を重ねた。
ミトリダテスの毒殺対処法の基本は、「毒をもって毒を制する」もので、普段から各種の毒薬を少量服用し、「身体に耐性をつける」ものだった。また57種の薬草などを混合して万能解毒剤「テリアカ(Theriaka)」を開発した。これは「大テリアカ」とも呼ばれる。この手のものにはあと、「小テリアカ」とミトリダテスにちなむ「ミトリダテアェ」がある。砂糖はまだ知られていなかったが、ミトリダテアェ(解毒剤)は、植物や蜂蜜の糖類を利用して毒を吸着させ、無効にするものであったらしい。化学でいう「アマドリ反応」である。
ローマ皇帝ネロは暗殺を恐れていた。その侍医クレタのアンドロマコスがテリアカをより改良し、その知見は古代医学の集大成家ガレヌスに受け継がれたという。
語源的にはギリシア語のtherionは「獣」を意味し、theriakaは「獣の咬み傷」に対する薬のことだった。解毒を意味するアンチドート(Antidote)が、ギリシア語のanti-(抗して)とdodonai(与える、投与する)との結合から成り立っているのと、少し異なる。
独裁者が医学・医療を好み、自ら健康法を唱道する例は、アレクサンダー大王やヒトラーにもみられる。ヒトラーは、自らは不眠症で睡眠剤の常用者だったが、禁酒・禁煙を唱えて周囲にもそれを強いた。ネロもミトリダテスも同様である。『日本書紀』には、武烈天皇が妊婦の腹を割いて胎児を見たとか、罪人の生爪を抜いて芋を掘らしたとか、罪人をダム湖の溝に寝かせて鉄砲水で流されてくるのを刺し殺したとか、残酷奇抜な話が書いてあるが、これも独裁者のある種の好奇心とからんでいる可能性がある。
万病薬テリアカがあるに対して、万病治療法パナケア(Panacea)がある。パナケアはもともとは医神アスクレピオスの娘であり、アスクレピオスの代理人である蛇の世話をしたという。そういうわけで、今でも医術のシンボルは世界的に「木の杖に巻き付いた蛇」になっている。呉市には「老人介護施設パナケイア」というのがある。理事長は医学史に詳しい人であろう。
語源的にはtheriacaのther-はTherapia(治療)とも語根が共通しており、初め「外傷の特効薬」の意味だったが、次第に「毒消し」(アンチドート)の意味でも用いられるようになった。
ヨーロッパの中世になると、病気を予防するという思想も生まれ、「万病を予防し、治療する」 「パナケイア(pana-keia)」が探し求められた。Pana(すべて)+keia(cure:治癒させる)というギリシア語からのラテン造語である。14世紀における西欧でのペスト大流行は、人々を恐怖のどん底に追いやり、合理的な思想が失われ、オカルト的、魔術的なものが受け容れられやすくなっていた。
世界史的に見ると、アラビア医学は、西ローマ帝国が滅んだ5世紀から12世紀の中世ルネサンスまで、ギリシアの科学や医学を保存し発展させる役割を果たしたが、ガレヌスの神秘主義がそのまま受け継がれ、ルネサンス期にアラブ医学文献がスペインのコルドバなどでラテン語に翻訳される際に、さらにイスラーム神秘主義の思想が入りこんだことは疑えないだろう。
ここで梶田昭『医学の歴史』(講談社学術文庫, 2003/9)の話を挿入する。
これはわずか360ページの文庫本だが、1万年前の人類のあけぼのから「戦争の世紀」20世紀までの医学の変遷を、分かりやすく衒学的でなく述べた大変な名著だ。
アラビアの医術はテリアカだけでなく、植物、動物、鉱物を、医薬として積極的に活用したので知られる。まだ抽出法が未発達で、せいぜい煮沸、発酵程度の化学処理しかできなかったが、当時の薬種商が扱っていた品目を見て、宝石と各地の土の粉末や石油までが医薬品材料として扱われていて驚いたことがある。まさに「化学はアラビアの地から始まったな」と思った。
(この表の視覚的イメージは残っており、3ページわたっていたのだが、本の名前を忘れてしまったので、書棚から本が見つからない。読んだ時に「読書目録」の「内容要約欄」にメモしておけばよかった。)
前嶋本の解説を三木亘(中東歴史生態学者)という人が書いているが、日本でも1973年頃はテリアカがまだ売られていて、滋賀県甲賀の置き薬屋で買ったそうだ。練り薬が貝殻の容器に入っていたという。戦中や戦後すぐの練り薬(薬用クリーム)はハマグリの貝殻に入っていたのを記憶しているが、高度成長期にも貝殻が使われていたとは知らなかった。伝統の秘薬だから、その方に効き目があったのだろう。
さて話を戻す。万病治療法(パナケイア)も万病特効薬(テリアカ)も存在するはずがない。
薬はその化学成分が効くので、ここでの化学成分とは水に溶けた化学分子のことである。薬となる化学分子は細胞表面にある受容体と特異的に立体化学的に結合する。それによってある特定の細胞や器官に薬理学的反応が起こるのである。すべての細胞に非特異的に反応するものは、タンパク質を非特異的に変性させるホルマリンや、細胞外濃度を高めることでナトリウム・ポンプを停止させるカリウム・イオンのようなものしかない。青酸カリは胃粘膜の細胞により吸収されないと効果を発揮しないが、ホルマリンもカリウムも注射すれば即死する。
そういう「ありえない薬」や非合理な治療法が流行することを、梶田は丸山真男『日本政治思想史研究』(東大出版会、1952)における、「政治がなりたつ社会的状況の2限界」という理論のアナロジーを用いて見事に説明している。丸山理論はおよそ次のようになる。
<世の中が安定していて、秩序に信頼が支配的である間は、政治は必要とされない。反対に社会変動により既存の支配体制に動揺が生じると、敏感な思想家に危機の感情が生まれ、「政治の季節」がやってくる。
その逆に、社会が混乱と腐敗により絶望的な段階に至ると、もう「政治」の出る幕がなくなり、社会からの逃避と頽廃が主流となる。
「政治」が有効に機能するのは、この二つの限界の間においてのみである。>
私は丸山のこの本を読んでいないが、梶田の記述から自己流の理解をすると、危機意識を感じているのが安倍晋三という政治家であり、若手右派の思想家中野剛志であろう。
他方、「逃避と頽廃」現象は、多発する高校生・中学生による殺人事件や「後妻業」で次々と夫を毒殺したとされる事件に端的に表れている。
この丸山の考え方に依拠して、梶田は「政治」を「医学」と読み換え、
<人間は健康で、心身共に体調がよい間は、社会思想において「秩序が信頼される」のと同様に、俗信や常識に依拠して生活している。しかし社会的危機が発生した場合に政治が必要とされるように、身心の危機に際して「医学」を求める。この希求には「科学に対する期待」と同時に「願望」が含まれている。
もし身心の危機が医学により解消されず、一層危機が深まり「混乱」の状態になると(例えば進行がんで余命告知を受けるなど)、合理的思考が再び影を潜め、「呪術・宗教」に頼るようになる。>という。
これは社会的頽廃に際して、オウム真理教などのオカルトが流行るのと同じである。現在も、若者による不可解な殺人事件が多発しているのは、やはり社会的危機の表れだろう。不治の病を宣告されて、神仏に頼ったり、いかがわしい「代替療法」や「民間治療」に走る患者は多い。STAP細胞がブームになったのは、メディアが「不老不死も夢ではない」などと煽ったからである。
梶田は
<医療は、病気ないし死から免れようとする人間の本能的欲求に応えようとするが、それを科学的に実現する能力との間に、絶望的な隔たりがある。それをなんとかして埋めようとする過程が、医療史ないし医学史であった>という医学史家、川喜田愛郎の指摘を受けて、
<もともと医学には「悩む(patior)」ことの学という意味と「癒やす(medeor)」ことの学という二面性があった。悩みは現実であり癒しは理想だが、medeorが名詞化したmedicinaが主流となり「医学(medicine)」という「理想」が勝利した。他方、patiorという「現実」の研究の方はpathologia(病理学)が引き受けた。(この「病理学」は広義のもので、寄生虫学、細菌学、ウイルス学、法医学、病態生理学などを含む。)
だが医学にとっても病理学にとっても、荷が重すぎた。できることは「悩み」に対する「慰め」なのに、たまにしかできない「癒し(medeor→medicine)」を看板に掲げたところに、医学の宿命的な辛さがある。> という。
梶田のこの書は深い思索の産物であり、全体が見事に統一されている。そこには病理学だけに偏した「悪しき専門分化」はない。これを読んだ後か、あるいは手許に置いて、前嶋の『アラビアの医術』を読むと、前嶋の博識が立体的、総合的に理解できるだろうと思う。
3)一坂太郎:『吉田松陰とその家族:兄を信じた妹たち』(中公新書、2014/10)=
NHK大河ドラマを当て込んで出版された本だ。手持ち本は年末に買った初版本だが、いまは増し刷を重ねているだろう。ドラマとの関係で余計な副題がついているが、基本は松蔭の短かった一生を描き、その中に家族の話や同輩や弟子たちのことがわかりやすく、よく書き込まれている。
当時の長州藩下級武士の暮らしの有り様、萩城下の地図、松蔭の生家杉家の家系図、次男だったの杉家から代々縁がある吉田家に養子に入ったこと、実の妹が久坂玄瑞と結婚したこと、実兄梅太郎の娘が乃木家に嫁いだこと、叔父文之進が玉木家に養子に入っており、玉木文之進であること(玄瑞は「禁門の変」で、文之進は「萩の乱」でともに破れて自殺)がわかる。
(家系図は左に年長者を書くのに、これは逆になっている。「系図学」は西洋からの輸入学問だから、左から書くのが正しい。)
年表もあり、理解を助けるのに役立つ。
吉田松陰の著書には『講孟余話』、『松蔭書簡集』(以上岩波文庫)、遺著『吉田松陰・留魂録』(古川薫:全訳注、講談社学術文庫)がある。「留魂録」には、古川による伝記が含まれている。
下関の作家古川薫は文章がくどいので、「史伝・吉田松陰」は読まなかった。
だから松陰のアメリカ密行の失敗と野山獄への幽閉、「松下村塾」開講の話と、江戸伝馬町の牢屋に入れられ、29歳で斬首され(切ったのは山田浅右衛門)、死骸を小塚原刑場に捨てられた話が、いきさつ、経時的な進行など、どうもよく理解できていなかった。
今回、この一坂本を読んで事情が腑に落ちた。浦賀でペリー艦隊の船に乗り込もうとして失敗、萩送りになり野山獄に送られ、後に実家の杉家に幽閉された。
ところが、「安政の大獄」が始まり、再び容疑者として江戸送りになった松陰は、幕府取り調べ役人が攘夷に好意的であると誤解し、京都で過激派浪士摘発を指揮している老中間部詮勝の暗殺計画を自白してしまった。これが、大老伊井が直接筆を執り「島送り」を「殺」に、処分を書きかえる決定的理由になった。
こうして本気で「攘夷」を実行しようと考えた主だった連中は、佐久間象山、高杉晋作、坂本龍馬などみな死んでしまった。「大政奉還」に成功した生き残り組は、いざ自分たちが権力の座につくと、「維新開国」と称して幕末の幕府の政策を受け継いで発展させた。つまり180度主張を変えたわけで、立派な裏切りだ。
松陰の『留魂録』に処刑前日に書いた「今日死を決するの安心は、四時の循環において得る所あり」で始まる有名な文言がある。四時は春夏秋冬の季節をいう。植物の一生から死生観を学んだというのだ。人生を「禾稼(かか=稲のこと)」になぞらえて、春の種まき、夏の苗植え、秋の稲刈りがあり、冬は穀物として蓄えられるという4つの季節がある。
だけれども「人寿定まりなし、禾稼のかならず四時を経るが如きにはあらず。十歳にして死するものは、十歳中おのずから四時あり」という。
奇書『人間臨終図鑑』(徳間書店、1986:現、徳間文庫, 全4冊)で古今東西800余人の「死に様」を記載した山田風太郎は、「十代で死んだ八百屋お七、アンネ・フランク、天草四郎、藤村操、ジャンヌ・ダルクから始まり、みなそれぞれに人生が完結している。もうちょっと生かしておきたかったのは織田信長だけだ」と述べている。
言葉は異なるが、松陰と「戦中派天才老人」風太郎は、期せずして同じ死生観に到達している。風太郎も渉猟濫読の人だったから『留魂録』は、読んだにちがいないと思う。しかし図鑑の松陰の死についての記載からは、この文言に影響を受けたとはうかがわれない。
松陰の遺体は四斗樽に入れられ、小塚原に捨てられた。弟子の桂小五郎や伊藤俊輔(博文)らが死体を引き取りに行ったら、首なしの松陰の遺体は棺の中に坐り、自分の首を膝に抱えていたという。これが1859年、今より160年前には、日本も「イスラム国」と同じことをやっていたわけだ。ベッカリアが『犯罪と刑罰』を書いて死刑の不当性を訴え、イタリア北部の小国サン・マリノが初の死刑廃止に踏み切ったのが1848年、松陰の処刑の11年前だ。以来ヨーロッパのEU加盟国は、すべて死刑を全廃した。
日本の死刑判決における誤診率は1%以上ある。「病気腎移植」による、がん持ち込みの危険性どころではない高率だ。だが、最近の総理府世論調査によると、国民の80%が死刑賛成だという。「イスラム国」では、判決を下した人間が自ら処刑を行うからまだましだ。
日本では「死刑執行人」は拘置所の「刑務官」という他人だから、平気なのだろう。「極刑に!」と叫ぶ遺族を処刑台に呼び、落とし台のレバーを引っ張らせてやるがいい。さぞかし復讐心が満足させられることだろう。
この本は、そういうことも考えさせてくれる。吉田松陰という人は、残された肖像画や実兄、実弟、実妹、実母の写真を見ると、面長で鼻筋が高く、いわゆる「長州顔」ではない。蒙古ヒダも肉親の多くに欠損しており、縄文系=古モンゴロイド系ではないかと思われる。
楽しく読める、お薦めの一冊だ。
4)長澤和也:『魚介類に寄生する生物』(成山堂書店、2001/4)=
例の「イワシの味噌煮」缶詰にいた「寄生虫?」の正体を突きとめるために、アマゾンに注文しておいた本だが、やっと届いた。もう脊髄と中腎という結論が出た後だが、晩酌をしながらひととおり目を通した。わかりやすい文章で写真や図解も多く、索引もありよい本だ。
著者は1952年生まれで、東京水産大の「増殖学科」を卒業した後、東大農学系大学院で農学博士をもらっている。北海道水産試験場勤務の後、キール大海洋研に留学し、帰国後は農水省「遠洋水産研」で働いている。
本書では軟体動物の貝類、イカ・タコ類と節足動物のエビ・カニ・シャコ類、原索動物のホヤ類、それに脊椎動物では硬骨魚類と軟骨魚類の寄生虫が扱われている。
イワシやサバに寄生する「環形動物」がいるかと思ったら、ゴカイの仲間(多毛類)の中に、カニに寄生するものがいるそうだ。
非常に面白いと思ったのはフィロネーマ(たぶんPhilonemaという学名だと思う。Philo-:好む、nema:糸の合成語だろう)という線虫がいて、淡水期にベニザケに寄生する。だが、海に下ったベニザケは海洋中で1〜4年を過ごし、成体にならないと元の淡水に戻らない。もし
フィロネーマが通常のライフサイクルを営んでいると、海水中で産卵しなければならないが、この幼虫は海水では生きられないし、ベニザケに感染できない。
そこでこの線虫は冬眠に入って、宿主が成熟するまで発育を停止するのだそうだ。まあ、冷凍卵子のようなものだろう。で、ベニザケが成熟し、生殖準備活動に入り、川を遡上し始めるとサケが出す性ホルモンが目覚まし時計となり、線虫も眼を覚まして生殖準備活動に入るのだそうだ。フィロネーマの中間宿主はケンミジンコで、湖水域でこれを食ったベニザケに感染し、新たなライフサイクルが始まるというわけだ。こういう風に宿主のライフサイクルにシンクロナイズする寄生虫は、他にもいるにちがいない。
ヒトに感染する魚介類由来の寄生虫としては、線虫のアニサキスが圧倒的に多い。特に「イカの刺身」が危ないとは知らなかった。冷凍物なら大丈夫だそうだ。
180ページ程度の本だが、プラクティカルな知識に充ちているので、開業医さんのオフィスにも一冊あると、患者が「先生これ何?」と持ち込んできた時に、うろたえないですむだろう。
約20冊の、より詳しい参考書があげてあるのもよい。