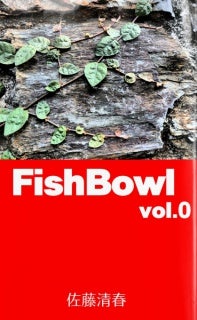彼らは中学生の頃からのつきあいだった。斎藤美以子と佐伯周と佐藤強士――名字がサ行であったために彼らは近くの席に座らされることになった。ただそれだけのことだったけれど、彼らはそれからずっと友人として過ごすことになった。
名字がサ行であること以外に彼らにはあまり共通点がなかった。周はその頃から背が高く性格も快活ですぐにクラスの人気者になった。強士は背が低く口数も少なく、いつもなにかしらの本を読んでいた。美以子はおとなしい性格だったものの二人によく注意した。
「周くん、ちょっと浮かれすぎ」とか、
「強士くん、もうちょっと楽しそうにできないの?」とだ。
その美以子はほっそりとしていて、同級生の女子の中では突出して背が高かった。手脚もすらりと伸び、肌の色は透きとおるように白い。ただ、周や強士に注意するときには頬が赤く染まった。彼女は三人でいるときにだけ過剰であったり過少である周や強士をたしなめた。しかし、普段の美以子はその容姿が目立つものであるにもかかわらず、あるいはそうであったためにひっそりと目立たぬようにしていた。強士も周もそのことには気づいていた。放っておくと自分たちの知らぬ間に美以子は消えてなくなってしまうのではないか――二人ともそう思うことがあった。
もちろん、それは半分以上ほど冗談のようなものだった。彼らはまだ充分すぎるほど幼く、それこそ過剰に物事を捉えるという癖を持っていたのだ。美以子にたいして思うことは自分についても同様に感じることだった。なにかのきっかけで自らが著しく変化をし、果てには存在を消してしまうかもしれない。強士も周もそのような怖れを持つことがあった。怖れがあるぶん、彼らはそれを冗談に包みこみ直視しないようにしていたのだ。ひとりでいると怖れは彼らをとらえた。だから、誰かにそばにいて欲しかった。
彼らの生まれた町には大きな川が流れていた。試験前にはその土手を歩いて図書館に通い、夏休みにはプールに行ったりした。幾度かは他のクラスメイトやそれぞれの部活の友人なんかもまじえて集団で行ったのだけど、そういう場合でもいつのまにか三人だけでかたまってしまうことになった。美以子はひとりで所在なさげにしていることが多く、周と強士はそれに気づくと吸い寄せられるかのように近づいていった。他の連中と離れ三人だけになると彼らはきちんと胸の奥から呼吸できているのを感じた。どうしてそうなるのかはわからなかった。しかし、そのうちに彼らは三人だけでプールに行き、花火大会に行き、図書館に通うようになった。
「なんなんだろうな、これ」と周は言った。
三人でプールサイドに座り、足だけを水に浸しながらだった。
「どういうわけか、いつもこの三人になっちゃうんだよな」
「ほんと」と美以子。「なんでなのかしらね」
夏の陽射しは三人にまんべんなくあたっていた。そろそろ夏休みも終わりという頃でプールの水はすこしだけひんやりしていた。周も美以子も笑っていた。それから、強士の顔を見た。
「で、強士、お前の感想は?」
「あ? ああ」
そうとだけ強士は言った。彼も彼なりに笑顔だったけれど、あまり感情を出さないので二人はいつもこうやって訊いてくる。
「ね、強士くん、あなたしゃべらなさすぎ。楽しいときは楽しいって言うものよ」
「ん? 楽しいよ。こうしてるのは」
「だろ? だったらそう言えよ。美以子の言うとおりだぜ」
周は立ちあがってプールに思い切りよく飛びこんだ。水飛沫が舞い上がり、それは強士と美以子に激しくかかった。ピッとホイッスルが鳴り、監視員が周を指さしていた。
「周くん、あなたははしゃぎすぎ」
プールサイドに手をかけた周に美以子はそう言った。しかし、笑いながらだった。どうしてかはわからなかったけれど、三人でいることが心地良いことは確かなことだったのだ。

現代小説ランキング エッセイ・随筆ランキング 人気ブログランキングへ
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》