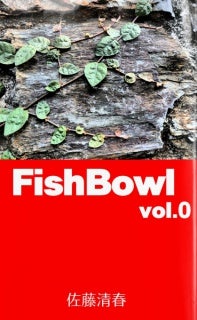鏡台から離れると美以子はクロゼットを開け、服を幾つかベッドに並べた。これを着るならスカートはこっちの方がいいかも――と考えた。身支度をすませ、美以子は外に出た。冬の明け方は道に背の低い靄を漂わせていた。大きな通りに出ると冷たい風が吹き抜けていった。美以子はコートの前を押さえるようにして歩いた。私はどこに行くんだろう? そうか、あの二人に会いに行くんだ。周くんと強士くん。私たちは仲良しで、いつも一緒に遊ぶ。あの二人は私を守ってくれる。どこにいたって探しにきてくれる。
![]()
あのときだってそうだった。私が不良たちに呼び出され、河原に連れて行かれたとき。なんなの? あの連中は。私のことを羨み、妬む人たち。周くんが私のことを好きだからって、みんなして脅してきた。私は言ってあげるべきだったんだ。「そうよ。私は周くんが好き。周くんも私のことが好きなの」って。お気の毒さま。でも、私は美しいんだもの。周くんはそういう私が好きなの。あなたたちじゃ無理よ。だって、ブスなんだもの。だから、妬むのよ。ずっとそういう人間には苛々させられてきた。子供の頃からそうだった。あの二人に出会うまでは。
美以子は土手の上へのぼっていった。桜の木は捩れて苦しそうにみえた。強士くんが手紙を渡してきたのはこの辺だった――そう思い、立ちどまった。あの手紙。私を間違った方へ引っ張っていったのは、あれだった。どうしてあんな人とつきあったりしたんだろう? 私が好きだったのはあの二人だったのに。誰が悪いんだろう? 私はあの二人が大好きで、彼らも私を好きでいてくれたのに。美以子はかつて恋人だった人間の顔を思い浮かべようとした。でも、それはうまくいかなかった。ぼやけていた。ガラスに映る顔みたいにだ。実穂は私に言った。「二人からちやほやされていい気になってる」って。「でもね、そういうのってあの二人にもよくないわ」とも言われた。
手をかたく握りしめ、美以子は振り返った。電車の窓に映った自分の顔を思い出した。透きとおり滲んだ顔。実穂の顔も同じように滲んでいた。そのようにしか思い出せなかった。振り返った先にはなにもなく、ただ明け方の景色がつづいているだけだった。しかし、美以子はなにかを怖れた。足早に歩きだした。
私は満足できなかった。あの人は私を満足させてくれなかった。下手だったのよ、セックスが。強士くんは私を満足させてくれた。私をほんとうに愛してくれてたんだもの、それも当然のこと。強士くんは一緒に暮らそうって言ってくれた。そうできればどんなによかっただろう。
――ああ、そうだった。
美以子は足をとめ、川の向かい側を眺めた。土手は高い壁のようにみえた。私はわかったんだ。私の心は裂けてなんかなかった。私は誰からも愛されなかったんじゃない。強士くんは私を愛してくれた。そして、私も強士くんだけを愛した。美以子の表情は穏やかになっていった。しかし、すぐに頬は平板になった。
なんでもっと早く気づけなかったんだろう? 今になってわかったからってなにができるの? それに、あの夢。裂かれていたのは心じゃなく、肉体の方だったのかもしれない。――そうだったんだ。肉体の方が間違っていたんだ。美以子は首を巡らせた。遮るものがなく広がった景色は美しかった。明らかで、しかし、すべてが灰色にみえた。冬の朝の色だった。川面にはきれぎれに浮く雲が映りこんでいた。
ほら、やっぱりそうでしょ? 強士くん。川には色なんてないの。いつも空を映してるだけ。美以子はゆっくりと土手を降りていった。ここにいればあの二人が迎えにきてくれる――そう思った。頭の中にはピアノの音が鳴っていた。はじめのうちはなんの曲かわからなかった。よく知ってるはずなのに思い出せない。高音はたどたどしくなにかを探るかのように鳴り、しだいにしっかりとしたメロディに馴染んでいく。低音は寄り添うように進む。
――ああ、そうか。
美以子は思い出し、それを口ずさんだ。小さな声で歌いながら歩いていった。砂利が歩くのを阻んだ。それでも彼女は川へ近づいた。まるでこの曲と一緒。空の色を映しつづける川を見つめながらそう思った。最初はたどたどしい。でも、ゆったり流れる川のようにゆるゆると一体になっていく。繰り返されるテーマもほんと川みたい。流れていき、いつも違う水があるはずなのに見ているだけではわからない。美以子はしばらくそこに立ちつくした。周と強士が探しに来てくれるのを待った。心配そうな顔をした周くんと仏頂面の強士くん。あの二人はいつだって私を助けてくれた。だから、私はあの二人が大好き。美以子は川をじっと見た。一歩そこに近づこうとした。砂利が音をたて、それは大きく響き、美以子は背中を押されたような気になった。そのまま足は川へと入った。
――ああ、冷たい。
そして、その瞬間にくっきりと昔の映像を思い出した。そう、プール。あのときの冷たさ。夏休みの終わり、足だけプールに入れて―― いろんなことを忘れてしまったというのに、あの水の記憶だけ残ってるのはどうしてだろう? それも、こんなにもくっきりと。美以子は水を掬い、それを自分にかけた。あのとき周くんはボチャンってプールに飛び込んで、私と強士くんはずぶ濡れになった。監視員のお兄さんが周くんを睨んでいたっけ。周くんはいつもふざけたことばかりして。強士くんは難しそうな顔してたな。なにを考えてたんだろう?
彼らの声が聞こえてくるように思えた。ただ、どこからなのかはわからなかった。前からなのか、後ろからなのか。なんて言ってるの? 私をどこかへ導こうとしてるの? でも、どこへ? 美以子は腰の辺りまで川に浸かっていた。水を含んだコートは重くなり、身体を下へ沈ませようとした。このままだと死ぬのだろう――美以子はそう思った。唇は自動的に動き、頭に浮かぶメロディを歌わせていた。指も勝手に動いた。右手は高音を、左手は低音を。音をひとつでも出したら、あとはつづけるしかないんだ。前の音に連動し、次の音は規定される。自分があたえた意味は予期していなくても次の意味に影響をあたえる。それは終わるまでつづく。前へ進むのが終わりへとつながっているのか、後ろへ行くのがそうなのか美以子にはわからなくなっていた。
でも、大丈夫。私はかたちを変えるだけ。それは終わりなんかじゃない。生というのはもともと無形。かたちなんてないの。川の色と同じ。いつだってなにかを映してるだけの存在。だから、大丈夫。肉体なんかがあるから難しくなってるの。私にはかたちなんてない。水とも一緒。だから、私は水にのまれていく。――そう、溶けていくんだ。溶けて、いずれは雨になり、空から落ちてくる。強士くんや周くんのところにも私は降りそそぐ。それが終わるわけない。だって、私は水になるんだもの。降った雨はまた川へと流れるでしょ? だから、大丈夫。心配しないで。
心配しないで――そう思ったとき美以子は涙を流した。身体はあらかた水の中にあった。長い髪は川面を漂い、水を吸い、まとわりついてきた。どうして私は泣いてるんだろう? 悲しいことなんてなにもないのに。でも、大丈夫よ。私は大丈夫。なにも問題なんてない。私はあなたたちに降りそそぐ。だから、大丈夫。もう心配なんてしないで――

現代小説ランキング エッセイ・随筆ランキング 人気ブログランキングへ
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》