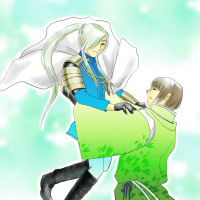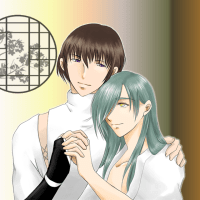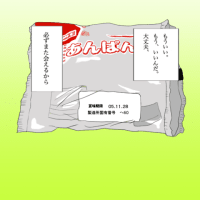一
しらしらと、雪が降っている。
真綿に似たぼた雪でも、風に流れ舞う粉雪でもない。
絹糸を引いたかのような跡が絶え間なく、灰色の空から降りてくる。
そんな細雪である。
雪の触れる地面も木々も、濡れそぼってはいるが、積もるには程遠い。
触れたそばから消えてゆく。
両手を火鉢で温めながら、歌仙兼定は雪の降る庭を眺めていた。
今年に入って、初めての雪である。
なかなか良い歌が浮かびそうだった。
その霊感が消えぬうちにと、歌仙は立ち上がった。
傍らの文机には、硯も墨も用意してある。
正月祝いにと主から贈られた、赤間石の蓋付硯である。
全体に梅の木を模した木肌模様が打たれ、握りには梅の花が浮かしで彫られている。
中々の美品に、一目で気に入った。
御礼の歌でも贈ろうか、と考えていたところである。
雅を解する主を持ち、光栄であると。
文机に腰を落ち着け、筆を取る。
そして何気なく、硯の蓋へと手を伸ばした。
二
大振りな長火鉢の上で、鉄瓶が鳴いている。
それを囲むようにして三人、顔をつき合わせていた。
石切丸、にっかり青江、歌仙の三人である。
石切丸と青江は、何ともいえぬ表情で、目の前の歌仙を見ている。
当の歌仙はといえば、顔面は蒼白、眉間に皺を寄せた必死の形相である。
「とにかく何とかしてくれ。こういうものは、君たちの専門だろう?」
「まぁ、当たらずとも遠からずだけどさ」
内番着の上に羽織った襦袢から首だけ出し、青江が呆れた声で応える。
「君の見間違いじゃないのかい?あれだけ物が散乱してる机じゃあね」
「いや、絶対そんなことはない」
眠そうな青江の眼をきっと睨みつけ、歌仙は首を振った。
猿が、いたのである。
一瞬、根付でも置いたかと思った。
大きさは三寸ほど、墨のように黒い毛皮が、艶々と光っている。
尻を文机にぺたりとつけ、両手は膝の上に揃えた格好の小猿が、硯の隣に座っていた。
南天の実のように真っ赤な目が、硯をじっと見ている。
突然現れた奇妙な代物に、歌仙はしばらく動けなかった。
猿も微動だにしない。
どれほど、そのままでいた事か。
もしかしたら、本当に自分が見忘れた根付か何かかもしれない。
そう思い、歌仙はそろそろと蓋へと手をかけた。
ゆっくり蓋を開ける。
と、同時に歌仙は蓋を放り出し、部屋から飛び出した。
猿の目が、硯の蓋を追ってゆるりと動いたからであった。
「妖怪か物の化の類か知らないが、とにかく生きて動いているんだ」
「猿の妖怪ねぇ…しっぺい太郎でも連れて来るかい?」
「こちらは本気で困ってるんだぞ!どうして君は人を茶化す事しか…」
「まぁまぁ歌仙さん」
青江に怒鳴りかけた歌仙を手で制し、石切丸は目を閉じた。
「…君自身からは、何ら悪い気は感じない。取り憑いて害悪を為す者ではなさそうだ」
「しかし……」
「とりあえず、その猿とやらを見に行こうか。青江も来なさい」
「何故だい?僕に猿を斬る趣味はないよ」
「私のしっぺい太郎の代わりだよ」
寒椿のような微笑を浮かべ、石切丸は立ち上がった。
三
そして三人は、再び文机を囲むよう、顔をつき合わせた。
猿は、歌仙の云っていた位置と寸分違わず、そこに居た。
三人が近寄っても、逃げも動きもせずにひたすら、硯を見つめている。
「小さいな。なんだ、こんなかわいらしいもので大騒ぎしてたのかい」
青江が笑いながら、指を伸ばす。
と、格好は崩さぬまま、猿が動いた。
頭に触ろうとした青江の指を、首を捻ってするりと避ける。
手が離れると、再び硯横に戻ってきて腰を下した。
「…やれやれ、恥ずかしがり屋のお猿さんだねぇ」
「歌仙さん、最近誰かから何か貰わなかったかい?」
「最近?最近と云えば、主からこの硯を…」
はたと膝をうち、歌仙は壁の階段箪笥の引き出しに駆け寄った。
と、それまで硯を見ていた猿の目が、きょろりと動いた。
引き出しを漁る歌仙の背を、じっと見ている。
見開いた大きな目を忙しなく瞬きする様子が、不安にも怯えにも取れる。
横目で猿を観察しながら、青江はそう思った。
「…あと、去年のクリスマスとやらに、お小夜がこれを」
振り向いた歌仙の手には、緋色の組紐でできた帯止めが握られていた。
ほおずき程の大きさの、赤いとんぼ玉が一つだけ付いている。
簡素だが、上品な帯止めだった。
『血の色みたいで、きれいだから』
「…と、貰ったのだけどね」
「ふむ」
石切丸が帯止めを受け取ると、猿の身体がぴくりと跳ねた。
柔らかな微笑を浮かべて、石切丸は猿を見、歌仙へと向き直った。
「歌仙さん、これは日本ではなかなか珍しいものだよ」
「これ、とは…」
歌仙は帯止めと、机上の猿とを見比べた。
「この生き物は、墨壷の猿と云ってね。中国の北部によく現れる一種の精霊のようなものだ」
「精霊だって?」
「人に密接に関係ある精霊だが、別段悪さをする訳ではない。ただ」
「ただ?」
「この猿は、墨が大好物でね。ただし磨りたてたばかりの墨は飲まない。必ず、人が使用した残り墨を飲むんだ」
「はぁ……すると、こいつが今もここにいるのは、僕が書き終わるのを待っていると?」
「そうだね」
「しかし、どこからこんな精霊が…」
「憶測だけど、これじゃないかな」
石切丸の手の中で、赤い玉が左右に揺れた。
「とんぼ玉かと思ったが、これは赤瑪瑙だよ。しかも中国にしか産しない、戦国紅瑪瑙という貴重なものだ」
「お小夜が、そんな高価なものを…」
「きっと、宗二君と江雪さんも幾らか出してるんじゃない?日頃、お小夜が世話をしてますってね」
横から青江が笑う。
「世話になってな……」
云いかけ、歌仙はしかめ面を赤らめて黙り込んだ。
「歌仙さん、おそらくこの猿はこの瑪瑙を依りにしているのだと思う」
組紐を丁寧に束ねると、石切丸は歌仙へと手渡した。
「長さも、帯止めというより硯箱を結ぶのにちょうど良いしね。用途を誤って売られていたんだろう」
「じゃあ、これを持っている限り、この猿はずっとここに居座るのかい?」
「そんなに困る事かな。墨の後始末は、結構面倒だろう?それに」
ふいに真顔になり、石切丸は詠うように続けた。
「古来、墨壷の精は名のある詩聖、歌仙にのみ現れるという。君の元に現れたという事は…」
「あ、いや……僕はそんな」
まんざらでもない様子で顔を綻ばせる歌仙の後ろで、青江は必死に笑いを押し殺していた。
「ねぇ、あの詩聖、歌仙のくだりは、作り話なんだろう?」
「さて」
「だって、よくいる精霊だと君が云ったんじゃないか。歌仙はもう忘れてしまっているみたいだけど」
「書と歌を愛する文人と、墨を好む精の取り合わせも、中々風流で良いと思わないかい」
「風流は分らないけどねぇ。まぁ、僕が精霊からも逃げられるんだって事は良く分ったよ」
四
それから数日、数週と日は過ぎた。
歌仙が書き物をしようと文机に座ると、どこからともなく猿が現れ、硯の隣に坐る。
用が終わると、教えた訳でもないのに硯を両手で持ち、墨池に残った墨を残らず啜り飲んでしまう。
自分の体より大きな硯から、一滴も零さず飲み干すのは、なかなか見ていて面白かった。
まるで洗ったように乾いた硯を、そっと机上に戻す様子もいじらしい。
いつの間にか歌仙には、この猿が書の相棒のように思えてきていた。
とうとう、雪が積もった朝。
雪見障子越しに、歌仙は白く変わった世界を見ていた。
自然と、言葉が胸に浮かぶ。
『ぬばたまの 三千世界に 降るや白雪』
中々悪くない。
が、どうしても下の句が思いつかない。
口の中で上の句をぶつぶつと何度も呟きながら、火鉢の周りを歩き回っていた。
ふと文机が目についた。
硯の隣に、小猿が座っている。
墨も磨っていないのに、先に待っているのは珍しいことだ。
まだなのか、と催促するような眼で歌仙を見ている。
「まだ当分、残り墨にはありつけそうもないぞ。難産だからね」
渋い顔で首を振ってみせ、歌仙は文机に背を向けた。
『白蓮の 三界五輪に 咲くが如くに』
その背に、りんとした鈴を転がすような声がかかった。
驚いて振り向くと、もう小猿の姿はなかった。
先程耳にした句をもう一度、口の中で繰り返してみる。
はっと我に返り、急いで文机に座ると、筆を取った。
『ぬばたまの 三千世界に 降るや白雪 白蓮の 三界五輪に 咲くが如くに』
こうして猿の言葉を借り、歌は完成した。
が、それっきり墨壷の猿は歌仙の元に現れる事はなかった。
そして硯箱の結び紐に付いていた、あの赤瑪瑙も、いつの間にか姿を消してしまっていた。
「恩返しだったのかもしれないね」
暗い顔で項垂れる歌仙の前に、温かな茶を置き、石切丸は言葉をかけた。
鉄瓶の吹く湯けむりを眺めつつ、ぽつりと青江が呟く。
「三千世界は 眼前に尽き 十二因縁は 心裏に空し」
「な!?な、何故、君が都良香を」
「以前、私が教えた句だね」
あっさりと、石切丸が種明かしをする。
不満げに唇を尖らせ、青江は軽く溜息を吐いた。
「まぁ、君にとってあの猿は、良香にとっての弁財天、羅生門の鬼だったんだろう」
「今度は都良香かい。おだてても何も出ないぞ」
「文人なのに立派な体格と剛腕の持ち主だったそうだよ、誰かさんそっくりにね」
「そちらの意味でか…」
長火鉢に置かれた湯呑を手に取り、歌仙は視線を流した。
窓の外は、まだ一面の銀世界である。
そう言えば、長らく箸と筆と包丁以外、握っていない気がする。
「刀の手触りを忘れぬうちに、一戦したいな」
「へぇ、自称文系が珍しい事を言うね」
「僕とて刀だよ」
「あぁ、その気持ちは解かるなぁ。最近私も、戦に出して貰えなくて…」
「じゃあ僕と代わっておくれよ。もう、連隊戦は疲れたんだよ…」
「僕じゃ練度が足りない」
「私は夜目が利かないから」
「……はぁ。使えない御神刀と文系だねぇ」
罵声と笑い声を遠く聞きながら、朱い南天の実が一房、雪の下から顔を覗かせていた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
久々に、ほんとーに久々に本職の物書きやりました。
こんな感じのちょっと奇妙な小話や、どさくさに紛れていちゃつく石かりとか書いてみたいと
思います。
あ、ちなみに自分しっとりとしたシリアスラブは全然書けません。
石かりもエロティックバイオレンス()になるに違いないのを、先に謝っておきます。