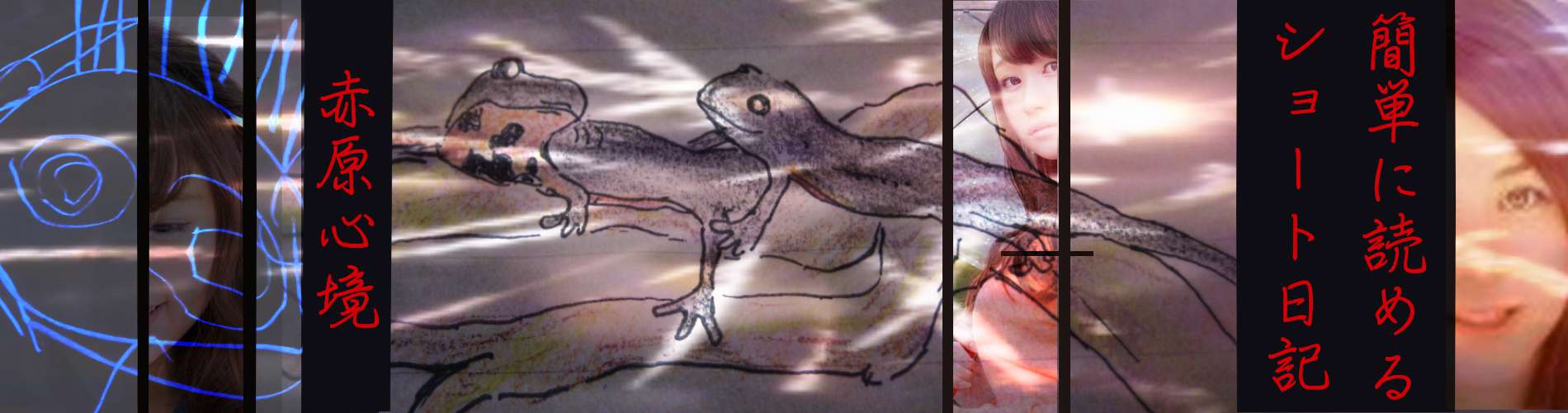苦い終わり 彼女の思いとチョコレート
2017年12月31日
終章
彼女のうるんだ瞳が 光輝く笑顔が 揺れる黒髪が
彼女の全てが ぼくの心を満たした
走り去る彼女の後ろ姿が ぼくの目に残っている
ぼくは彼女に貰った小さなピンク色の袋を胸に抱きしめ部屋へと飛び込み
部屋の中央 冷たい床の上に座り込んだ
走りながら帰ってきたので呼吸が荒い
手も震えている 部屋の寒さのせいではない
感激で震えているのだ
ぼくはピンク色の袋を頭上にかかげた
夢じゃない 本当に貰ったんだ
彼女の心が 気持ちが ぼくの手のひらの中にあるような気がした
ぼくは喜びを噛みしめる
今まで誰にもチョコをあげた事のない彼女が ぼくに…
ぼくはピンク色の袋の口を開け 中にあるものを そっと出す
触れては壊れる大切な物を扱うように ゆっくりと 慎重に そっと
中に入っていたのは ぼくの両手に収まる大きさの長方形の箱だった
赤いリボンでラッピングがしてある
ぼくは彼女の赤くなり恥じらいながらの笑顔を思い出す
胸がキュンと締め付けられる
ぼくは赤いリボンに手をかけ 優しく ほどいていく
何か いけない事をしているような 彼女の服を脱がしているようなドキドキを感じる
心臓が はち切れそうなほど脈打つのが分かる
赤いリボンをほどけば ほどくほどに
彼女の笑顔が浮かび 彼女の吐息を思い出し 彼女の存在を感じる
ぼくの手は激しく震える
赤いリボンをほどき ぼくは長方形の箱を見る
何やら英語で書いてあり 隅のほうにグラスの絵が可愛らしく描かれている
ぼくは勘で英語を読む バレンタインの文字だけが 何となく分かった
手作りではなく 市販されている物だろう
だけど ぼくが初めて見るチョコの箱だった 外国のチョコレートだと思う
でも
彼女が ぼくを想い選んだチョコに違いはない
チョコの箱を前に ぼくは迷っていた
このまま食べるのは勿体ない気がする 食べれば無くなってしまう
彼女からのプレゼント 死ぬまで大事にしたい
そして 家宝にしよう
でも ダメだ
これはチョコだ 何かの拍子に溶けてしまうかも そんな事になったら彼女の気持ちを無駄にしてしまう
ぼくは決めた
彼女の気持ちを受け止めよう
ぼくは彼女の姿を思い浮かべながらチョコを食べる事にした
箱を開けると中にはコーラの瓶を模したかのような小さな可愛らしいチョコが五つ並んでいた
ぼくは その内の二つを手に取り
彼女からの想い 彼女への想いと共にチョコを口に入れた
口の中いっぱいに微かな苦みと芳醇な甘みのチョコが濃厚にとろけてくる
ぼくも とろけそうだ
とろけたチョコの中からジェル状のものが染み出てきた
ぼくの舌を熱くする
ぼくの心を熱くする
ぼくは更に彼女の姿を 彼女を想う
彼女の照れて赤くなった顔 彼女のうるんだ瞳 彼女の「私 嬉しいよ」と言った声
微かに震えていた指先 長く綺麗な黒髪 大きくなりつつある胸 桃色のくちびる
恥じらう笑顔
ぼくの胸は最高潮に高なり熱く脈打つ
顔も真っ赤に紅潮していくのが分かる
ぼくは残りのチョコを全部 口に入れる
チョコがとろける
ぼくは全身が熱く燃えるのをハッキリと感じた
胸が苦しい これが恋なのか?
興奮の限界を超える
鼻血が垂れてきた 煮えたぎる想いは外へと噴き出すのか?
視界が ぼやける 恋は常に盲目だからか?
ぼくは そのまま冷たい床に横になり眠りについた
お母さんに叩き起こされ怒られた時に その罵声から ぼくは ある事実を知る
ウィスキー入りのチョコを一気に食べるバカが どこにいると
ぼくが食べたチョコはウィスキーボンボンと言うらしい
彼女は ぼくがウィスキーの似合う男と見て そのチョコをくれたのか
ただ 父親にあげるチョコを間違えて ぼくに渡したのか
それは とけない謎だ
彼女は すぐに転校してしまったから
ぼくは彼女からチョコを貰う時に 時が止まればいいのに と願った
願いは叶っていた
自分の心の中にいる彼女は何年たっても
あの時のまま
自分に微笑みかけている
永遠の美少女として
Posted by akahara-sinkyou
関連記事
甘い始まり バレンタインデーの思い出
まだ 自分が ぼくであった時の頃 この日が来ると いつも思い出す 小学校五年生だ ...
後編 俺には お前しかいない 変えてやるよ お前の人生を
彼女の2つめの願い 誰よりも素敵なドレスと靴を得た 彼女は誰よりも目立つ馬車を老 ...
前編 俺には お前しかいない 変えてやるよ お前の人生を
今年も もうすぐ終わりですね 月日の早さをイヤでも思い知らされる時期ですね 今年 ...
俺の前にいる時ぐらいは イヤな事を忘れて楽しんで欲しくてさ
さぁーて 暇だから日記を書いてみよう でも どんな日記を書けば良いのやら? 何を ...
とろける続き ぼくに どうしろって言うんだ?
第二章 彼女の長い黒髪が風になびく サラサラと音が聞こえるような艶やかで綺麗な黒 ...