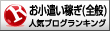⑯ 外国語と日本語と私。 日本と中国。 ゲーテ。 ノーベル賞に落選したトルストイ。 天皇の韓国訪問はあり得るのか?
外国語と日本語と私
1) 日本人は外国語に弱いと言われる。それは特に、話し方(スピーキング)と聞き方(ヒアリング)においてと言われる。 私は自分の頭(センス)の悪さを棚に上げてそう述べているので、お許し願いたい。 例えば、英語については、中学1年から大学4年まで10年間も勉強したのに、一向に会話(カンバセーション)が上手にならない。
日本人の中には勿論、英会話の上手な人もいるが、大学の英文科を卒業したというのに、ほとんど英語が話せないという人も多数いる。 そういう人達を見ると、私は自分の頭の悪さを放っておいて、なんとなく安心してしまう。
我々高年齢の日本人は、一般的に英語など外国語の会話がどうして下手なのだろうか。 私も何度も英会話に挑戦したが、少しも上手くならず今日に至っている。情けない限りだ。
25年ほど昔のことだが、私はフジテレビの報道にいた時、たまたま「外務省記者クラブ」の担当を命じられた。「よしっ、やるぞ!」と本当にやる気になって、当時で30万円以上もする英会話習得器械と教材を購入し、寸暇を惜しんで勉強した。
そして、数カ月経ったある日、アメリカ大使館でレクチャーがあるというので、記者クラブの他社の仲間と大使館へ行き、アメリカ人のレクを聞いた。 ところが、ある程度分かると思っていたのに、そのアメリカ人のレクが速いこともあってか、内容がほとんど理解できないのだ。 私はがっかりした。
仕方がないので、私はTBSの記者をしていた秋山豊寛氏(後日、日本で最初の宇宙飛行士となった人)に、レクの内容を詳しく教えてもらって事無きを得た。 彼は国際基督教大学を出ていて、イギリスのBBC放送でも仕事をした経験があるから、英語の実力は大変なものがあった。 その後も、よく彼から教えてもらったのである。
2) 私なりに猛勉強しても、英語のヒアリングやスピーキングが上手くいかないというのは、自信を喪失させるものである。 私はだんだん英会話の勉強に嫌気がさし、それから逃避するようになっていった。こうなると勉強の意欲も失われ、いつしか“特訓”は終わってしまったのである。
その後も二、三回は英会話に挑戦したが、結局上手くいかず、せいぜい片言の英語が話せる程度で終わっている。 英語だけでなく、高校・大学を通じて学んだフランス語にしても同じである。フランスへ行っても片言しか話せないのだ。
ここで、大いに負け惜しみのつもりで言うと、日本の語学教育というのは、七面倒臭い文法などから始めるから、余計に上手くいかないのではないのか。 外国語を話そうとすると、頭の中にまず文法のことが浮かんできて、思うように舌が回らなくなることが多い。 我々古い年代の者には、そういうケースが目立つようだ。
もう一つ、これも負け惜しみになるが、英会話などに対して“気恥ずかしい”と思う側面がある。 上手になりたいくせに、外国語をペラペラと話すことに違和感のようなものがあるのだ。 これは潜在意識の中にあると言ってよい。こういう意識がある限り、語学は決して上達しないだろう。
古い世代の語学教育などは、もう絶望的だ。 屈折した心理を持たず、伸び伸びした若い世代に期待するしかない。最近、特にそう思うようになってきた。
3) ところで、外国人から見ると、日本語は“悪魔の言葉”と映ることがあるそうだ。 それもその筈で、英語ではアルファベット26文字(ローマ字)で全てが済むのに対し、日本語は漢字、ひらがな、カタカナの3種類の文字を使う。 更にその中に、たまにはローマ字が挿入されることもある。外国人から見れば、確かに複雑怪奇な言語だろう。
英語なら、1人称単数主格は「I」一文字で済んでしまうが、日本語では「私」「僕」「俺」「小生」などがあり、しかも「私」は、発音が「わたし」「わたくし」であったり、女性では「あたし」「あたくし」と言うこともある。
更に、日本語の同音異義語の多さ、複雑さは物凄いものがある。 例えば「きこう」というのは優に20種類以上の言葉がある。「気候」「気孔」「奇行」「機構」「紀行」「帰港」「起工」「寄港」「寄稿」「起稿」「貴公」「気功」「貴校」「機甲」「機巧」「帰校」「奇効」「騎行」「帰降」「寄口」「帰向」「奇巧」「帰耕」「紀綱」などで、この他にも、あまり使っていない言葉がまだあるのだ。
「こう」と発音(音読み)する漢字が幾つあるか調べてみたら、259もあったので厭になった。(講談社・日本語大辞典を参考) 主なものでも、口、高、好、甲、公、功、巧、光、広、工、弘、交、好、向、行、考、港、孝、航、坑、宏、紘、攻、更、幸、降、鉱、抗、効、校、肯、皇、厚、後、構、鋼、硬、恒、侯、荒、候、降、耕、香、虹、黄、康、腔、稿、冦、衡、綱、項、興、拘、勾、購、閤、浩、巷、講、媾、酵、縞、肛、仰、絞、洪、肱、郊、江、孔・・・などである。
日本語では、これらの漢字がふんだんに使われるのである。 アルファベット26文字で済ます英語等に比べると、なんと複雑で厄介なことか! これでは、悪魔の言葉と言われても仕方がないだろう。
4) 私達日本人は1000年以上もの長い間、そういう複雑な日本語を使ってきた。 従って言語に対する“感性”が、欧米人とは比較にならないほど、独特のものになってしまったのではなかろうか。 そして又、日本語の使い方が極めて“微妙”なものになってしまったのだ。
例えば「又」とか「勿論」という漢字があるが、平仮名で「また」とか「もちろん」と書く場合も多い。 文章を書く時、前後の文脈や句読点のことまで考えて、漢字にするか平仮名にするか迷ってしまうことがある。 私は文章を書くことが多いので、いつも迷っている。 これが英語ならば、ほとんど迷わない。「and」と「of course」で済んでしまう。
更に敬語(謙譲語、丁寧語、尊敬語)を使う場合は、日本語はもっと複雑になってくる。 それらを使う場合、余りに多くの使い方があるので、重複したりバカ丁寧になったりすることも多い。「~させてもらっていいですか」というのも、「~させてもらって宜しいですか」とか、「~させてもらって宜しゅうございますか」などと平気で言ってしまうのだ。 その点、英語なら「May I~」で大体済んでしまう。
これらのことを見てくると、日本語の感性は、英語など外国語の感性とは余りに大きな隔たりがある。 日本語は難しい。しかし、日本人である私は日本語が大好きである。 外国語の習得が下手な私は、今後も日本語を愛し続けていくしかないのだ。(2002年7月9日)
日本と中国
1) 作家・陳舜臣さんの著作に「中国五千年」(講談社文庫)というのがあり、以前読んだがなかなか面白かった。 中国の書物には「史記」を始め「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」など、我々日本人にもよく読まれているものが多い。 我々には主に短縮したものしか読めないが、それでもどの書物も壮大なスケールで実に面白い。感化を受けた日本人も多いはずだ。
中国の5000年に及ぶ「歴史時代」は、日本の「歴史」よりはるかに深みがある。これは到底太刀打ちできるものではない。 日本では2世紀から3世紀に至る“邪馬台国”ですら、一体どこにあったのかさえ確証がつかめていない。 それに比べて中国では、紀元前14世紀ぐらいからあった殷王朝の所在(殷墟)も明白になっているというから、日本とはまったく気の遠くなるような差がある。
日本人の先祖(ルーツ)については諸説あるようだが、中国からも相当数の先祖が日本に渡来してきたことは間違いない。 歴史書によれば、紀元前2~3世紀には、日本は大陸文化(中国文化)の影響を強く受けるようになったと言われる。 その頃の日本の歴史はよく分からないというのに、中国では秦の始皇帝による統一から前漢時代へと、歴史の真実がはっきりと記録されているのだ。 歴史的に見れば、あらゆる面で中国は日本の“大先輩”に当たる。
2) 歴史に素人の私が言うのもおこがましいが、古代日本の文化はほとんど中国からの影響で成り立っているのではないか。 稲作農耕に始まり漢字や儒教、仏教などが、中国大陸から主に朝鮮半島を経由して我が国に入ってきた。 古代日本は遣隋使や遣唐使を派遣し、中国から多くのことを学んできた。 聖徳太子の17条憲法にも「五経」や「論語」の句が取り入れられているという。
大和朝廷が確立していく中で、日本は独自の政治・文化を築いていくことになるが、その後も中国からの影響は絶大であった。 630年に始まった遣唐使は延々と9世紀末まで続いた。その間に、有名な最澄や空海らの入唐がある。 日本がようやく中国文化から独立して、文化の和風化(国風化)を目指すことになったのは、ほぼ10世紀に入ってからである。
10世紀初頭に唐が滅亡してから、日本は初めて中国から精神的に自立したと言ってよい。 しかし、それまでの中国からの影響が余りに大きかったため、中国文化は和風化されたまま沈殿していく。 日本が本当に中国より優位に立つことができるのは、明治維新を待ってからであろう。
3) ご存知のように、明治27年(1894年)からの清国(中国)との戦争で日本は勝利した。 これによって、日本は有史以来初めて中国より優位に立った。その後の日中関係は大多数の人が知っているので、詳しく述べることは差し控える。 近代化や富国強兵に成功した日本に、今度は中国の革命家達が学ぶようになる。1905年、孫文が中国(革命)同盟会を結成したのは東京であった。
「中華民国」の成立、そして孫文から蒋介石へと指導者が変わっていく中で、1931年(昭和6年)の満州事変は、明らかに日本による中国への侵略だった。「満州国」を樹立した日本は、やがて日中戦争を引き起こし泥沼の戦いにはまり込んでいく。 歴史上、日本と中国は最も不幸な関係に陥ってしまうのだ。
そして、1945年の日本の敗戦、1949年の「中華人民共和国」の成立によって事態は大きく変わっていった。 日本はアジア・太平洋戦争での敗北によって、朝鮮半島、台湾を始め多くの領土・支配地を失った。そればかりでなく、独立さえ失い連合国に占領されるまでに転落した。 これによって、50年間中国に対して優位を誇っていた日本の立場は崩壊していく。
4) 中華人民共和国に対して、日本は政治的に絶えず劣勢に立たされてきた。日本がいかに経済発展を遂げても、政治的には中国の風下におかれていた。 1972年9月に日中国交正常化が成ったが、中国はすでに国連安保理事会の常任理事国となっており、国際政治の上では日本より格上の立場になっていたのである。
「文化大革命」の混乱や「民主化運動」の弾圧等、中国は国内的に動揺を繰り返してきたが、対外的にはアメリカ、ロシア(旧ソ連)などに対しても、絶えず毅然とした姿勢で臨むことができた。 香港、マカオの祖国復帰も果たし、残るは主に“台湾問題”だけである。(もっとも、“台湾問題”は複雑な要素があるが・・・)
日本が今、中国に学ぶことができるものと言えば、正にこの国の毅然とした対外姿勢である。外交姿勢と言ってもよい。 1840年のアヘン戦争以来、この国は100年以上にわたって外国の侵略を受けてきた。外国に侮られてきた。 その痛恨の歴史が、中国をして今毅然とした対外姿勢を取らせている。
それに比べて日本はどうか。 いかに第2次大戦の「敗戦国」とはいえ、必要以上に他国の顔色ばかりを窺っている姿勢が目立っているのではないか。 平和主義はもとより良いが、往々にして卑屈な外交姿勢を見せているのではないか。
5) もともと「中華思想」があるものの、中国は他国から侮られることを最も忌み嫌う。どの国もそうであろうが、先に述べたように、この国は100年以上にわたって外国の侵略を受けてきたから、その思いは尚更強い。 従って、日本は中国に対し十分な配慮をもって接していかなければならない。
しかし、その配慮も、なんでも中国の言う通りにすべきだということではない。 日本としても言うべきことは言い、主張すべきことは主張するべきである。そうでなければ、こちらがかえって侮られてしまうだろう。 お互いに道理に叶ったことを言い、行うことによって“真の平等互恵の友好関係”が樹立されるはずである。
靖国神社参拝問題でも教科書検定問題でも、言うべきことはこちらからも言わなければならない。 日本としても、中国の毅然とした姿勢に学ぶべきである。 この点、中国は間違いなく日本よりはるかに率直である。
つい最近の“瀋陽における北朝鮮国民亡命事件”の経緯を見ていると、かなりの日本人がこれで良いのだろうかと思ったに違いない。 テレビなどを見ていると、日本の総領事館は何をしているんだと怒っている識者が多かった。 中国の武装警官が総領事館に侵入してきて、亡命を求める北朝鮮国民5人を強制連行したから、主権を侵害されたと怒っているのだ。
中国政府は「日本側の同意を得た上で連行した」と正当性を主張しているが、日本の外務省は「同意を与えた事実はない」と反論し、中国側と対立している。 我々は外務省を信じたいが、テレビ等の報道を見ていると、どうも心もとない気がしてくる。
総領事館員らの対応を見ていると、日本の主権は本当に守られているのかと疑いたくなる。毅然とした姿勢が見えてこないのだ。 これに反して、中国はいつも堂々としていて、こちらが“内政干渉”ではないかと思っても、靖国問題や教科書問題等について明白に自国の主張を示してくる。
日本も少しはそうした姿勢を見習うべきだ。 戦後、(敗戦によって)自尊心も誇りも失ってしまった日本は、事なかれ主義と惰性に終始してきた。 それに比べて、中国は自尊心と誇りを回復し、今や堂々たる政治大国として甦った。
日本は歴史上、多くのことを中国から摂取し学んできたが、今こそ日本に最も欠けているもの、つまり毅然とした政治姿勢・外交姿勢を中国から学ばなければならない。 そして、中国と“対等”の友好関係を結ばなければならない。
(2002年5月13日)
ゲーテ
1) ドイツの文豪・ゲーテという人をどう理解したらいいのだろうか。 我々人間が感じること、考えること、想像することの全てをこの人は把握しているようだ。 それだけではなく、我々が感じ、考え、想像することの全てを越えるものを、この人は体験しているようだ。 その精神の広さと深さにおいて、この人の右に出る者はいないのではないか。
例えば、最も崇高なものも、最も醜悪なものもこの人は理解でき、そして体得して実行することができるだろう。 つまり、人間が持っているものを全て所有しているということだ。 ナポレオンがゲーテに会った時、「あなたは人間だ」と言ったことは十分に分かるような気がする。
この汲めども尽きない人から、我々は何事でも学び、教えられることができるだろう。そういう意味で、この人は正に“人生の師”と言える。 全ての人がそれぞれの仕方で、ゲーテから学ぶことができるのだ。 例えば私の場合は、ゲーテからはっきりと学んだものは「汎神論」だ。
2)「汎神論」のことはさておき、私なりにゲーテについて語っていきたい。 若き日のゲーテは、新しい文学運動であるシュトゥルム・ウント・ドラング(疾風怒濤)の旗手であった。 ご存知のように小説「若きウェルテルの悩み」や、戯曲「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」の著者として一世を風靡した。非常に輝かしい青春を駆け抜けたのである。
しかし、ゲーテ自身の告白から知られるのは、その青春は同時に極めて苦悶に満ちたものであったようだ。 肉と霊の葛藤に苦しみ抜いた形跡がある。彼ほど生命力に満ち溢れた人も珍しいから、その葛藤は凄まじいものがあったらしい。「ウェルテル」にもその一端が窺える。
人はその偉大さによって、ゲーテを神聖視するきらいがある。それは良く分かるが、彼の青春時代は正に懊悩苦悩の連続だったようだ。 それは現代風に言えば、リビドー(libido)の横溢による絶え間のない苦悶ということである。 リビドーと言う限り、もちろん性的エネルギーの奔出も含まれる。
年上の娘から料亭の少女、その後牧師の娘から銀行家の令嬢へと、青春時代の彼の恋愛は止まる所を知らなかった。その間にも、他の青年の婚約者であるシャルロッテ・ブッフ(「ウェルテル」の中のロッテのモデル)に恋をして果たせず、心に痛手を負うということもあった。 挙げ句の果てには、銀行家の令嬢との婚約を破棄して彼はワイマールへと去って行く。正に恋愛の疾風怒濤という感じがする。
3) そうした中で、ゲーテがどれほど「罪」の意識を感じたかは計り知れない。ある意味で、煩悩の塊だったと言ってよい。 若き日の彼は自分自身にこう言った。「 この哀れな者よ、一体いつまで狂い回らなければならないのか!」 その深い苦悶の合間から、束の間の「生」の喜びが輝かしい青春の詩歌となって、ほとばしり出てきた感じがするのだ。 煩悩の塊であればこそ、真実の喜びを体験できるのかもしれない。
晩年になって、家族との食事の時にゲーテがふと漏らした言葉は、この天才の恐ろしさを如実に物語るものである。 彼は言った。「もし私が、自分の好きなようにしていたら、私の意思一つで自分自身も、周りの人達をも全て破滅させていただろう」
この言葉を待つまでもなく、彼は生死のぎりぎりの所を頻繁にさまよって来たのだ。 これは耐え難い苦痛だったに違いない。地獄の業火に苛まれる罪人を想い起こさせる。それほどまでに、この人は苦悩したのだ。 こうしたことは、余人にはなかなか分からないだろう。彼自身が自分の煩悩を乗り越えるためにどれほど苦労したかは、彼の次の言葉の中にも表れている。「自分の風変わりな、どうしようもない性格を治してくれたのは、スピノザの哲学(汎神論)だった」
ゲーテの心(精神)こそ、ありとあらゆる矛盾、あつれき、衝突を包含していたのだろう。 フランスのある高名な作家が言った。「彼の心は、あらゆるものの戦場だった。それは耐え難い戦場だった」と。 そして、ゲーテ自身もこう言った。「私の後を決して追うな」
4) 多くの人が知っているように、ゲーテはワイマールに行ってから、ようやく落ち着きを取り戻すことができた。現実生活との調和を得ることができたのだ。 7歳年長のシュタイン夫人とのプラトニックな恋愛が、背景にあったのは言うまでもない。しかし、ゲーテと知り合った最初の頃は、シュタイン夫人も彼の野性を相当警戒していた形跡がある。
その後のゲーテの人生については、余りに多くの伝記に描かれているので省略する。 37歳の時のイタリアへの脱出旅行から晩年に至るまで、彼の創造力(デモーニッシュな創造力)と、自然研究の精神はまったく衰えを見せるどころか、むしろ円熟と深みを加えていった。 驚嘆すべき創造力は劇作、詩、小説等で発揮され、自然科学の研究は植物、動物の形態学、「色彩論」などに結実していった。 ゲーテのことを『ルネサンス最後の巨人』と評した人がいるが、正に“万能の天才”と言うべき存在であった。
これほど輝かしい人も他にいないが、晩年に至るまで彼は“悩める人”であった。そこがまた、我々普通の人間を魅了してやまない所である。 39歳の時、若い造花女工(クリスティアーネ・ヴルピウス)と同棲し男子を儲けるが、彼女と正式に結婚するのは18年も後になってのことである。 その間も、また妻に先立たれた後も、晩年に至るまでゲーテの恋愛遍歴は止まることがなかった。
5) 19世紀ロシアの有名な批評家・ベリンスキーは、「ゲーテはまるで豚みたいな奴だ」と言ったことがある。漁色家ということである。 これは正に当を得たものであろう。彼は74歳になっても、19歳の少女に恋をして結婚を申し込んだほどだから。
しかし、ゲーテの恋がドン・ファンのような単なる漁色家のものと違うのは、それが余りにも美しく昇華されることである。 19歳の少女に失恋した老ゲーテは、悲嘆と苦悶のどん底から魂を揺さぶるような詩をうたう。有名な「マリーエンバートの悲歌」の一節を紹介しよう。
『どうしようもない憧憬に 此方彼方へ私はさまよい 慰さめる手だても知らず ただ果てもなく涙は流れる よし涙よ 湧きやむな 流れ続けよ この心の火を消すことは それでもできまい 生と死が むごたらしくも組み打ちする 私の胸の中は今すでに 狂おしく裂けんばかりだ』(人文書院発行「ゲーテ全集 第一巻 詩集」より。高安国世訳)
哀切の尽きないこの悲歌を読む時、我々はとても74歳の老人が詠んだものとは思えない。 恋に破れた老ゲーテの心情が切々と迫ってくる。 年老いて尚このような情熱を秘めているとは、驚異としか言いようがない。情熱の虜にならなければ、このような悲歌は生まれてこないだろう。
こうした点に、私どもはなんとも言えない魅力をゲーテに感じるのではないか。 絶えず生の拡充を求めて、生と闘った人間。 そして、人生の最後の瞬間まで生を愛した人間。 死の間際に「もっと光を!(mehr Licht!)」の言葉を残した人間・・・ゲーテは『生の詩人』として、人類の中に末永く生き続けるだろう。
(2002年5月9日)
ノーベル賞に落選したトルストイ
ノーベル賞は世界で最も有名な賞だが、その平和賞は極めて“政治的”な意味合いが濃いものになっている。同時に、文学賞もまた政治的な理由で決められることがよくある。 その象徴的な出来事が第1回のノーベル文学賞の時に起きた。それが、世界的な文豪レフ・トルストイの落選であった。
ノーベル賞が創設された1901年当時、世界最大の文豪と言えば誰もがロシアのトルストイを挙げただろう。彼の文学作品の影響力はロシア、ヨーロッパだけでなく、遠く日本にまで及んでいた。だから、ほとんどの人がノーベル文学賞は文句なくトルストイが受賞するものと思っていたようだ。ところが、トルストイは落選し、フランスの某詩人が受賞したので皆が驚く結果になったのだ。
この件で、私は子供の頃から面白い話を聞いていた。それは、スウェーデン・アカデミーがトルストイに授賞しなかったのは、「彼があまりにも偉大であったため、畏れ多くて授賞しなかった」というものだ。たしか児童向けの世界文学全集だかにそう書いてあったので、単純にそれを信じていた。
ところが、事実は全く違っていて、トルストイ自身も受賞するものとばかりに思っていたようだ。彼はそうなると信じていたのか、スウェーデン・アカデミーに宛てて、受賞賞金は某キリスト教団体のカナダへの移住費用に充てて欲しいという手紙まで出していたのだ。
自他共にトルストイの受賞が確実だと思われていたのに、なぜ彼は受賞できなかったのか。それこそ政治的な理由があったからだ。
スウェーデン・アカデミーの見解によれば、トルストイの絶対平和主義、暴力否定論には“アナーキズム的”な傾向が強く、ノーベル賞の趣旨に合わないというものだったらしい。 事実、トルストイは「徴兵制」を絶対に認めないロシアのドゥホボル教徒を支援していて、そのカナダ移住に手を貸そうとしていた。
ところが、当時のヨーロッパ諸国は「徴兵制」を国家の発展には不可欠のものと捉えていたため、トルストイらの思想とは真っ向から対立したようだ。このため、誰もが確実視していたトルストイのノーベル文学賞受賞は実現しなかったというのが真相のようである。正に政治的な理由でそうなったということだ。
ノーベル賞を受賞できなかったトルストイはその後、名作『復活』を著し、その印税でドゥホボル教徒のカナダ移住費用を賄うことになる。
ノーベル文学賞でさえこうだから、平和賞になるともっと複雑で政治的なものになってくる。昨年、オバマ米大統領が「核廃絶」に強い決意を表明したというので平和賞を受賞したが、つい先月(9月15日)、アメリカは核実験を実施した。一体、どうなってるんだと言いたくなる。
そうかと思うと、今年の平和賞は中国の人権活動家・劉暁波氏に与えられるというので、中国が難色を示し国際問題にまで発展しそうだ。ノーベル賞は結構だが、そこに政治的な思惑、理由などが入ってくるとどうしても生臭くなってくる。
それほど影響力のある国際的な賞だが、私に言わせれば、欧米中心の価値観、世界観から授賞しているものだとしか思えない。まあ、ノーベル賞なんて私には全く関係ないことだが(笑) (2010年10月16日)
ノーベル文学賞・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%B3%9E
レフ・トルストイ・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A4
天皇の韓国訪問はあり得るのか?
〈2014年10月26日に書いた記事を“一部修正”して復刻します。〉
昔、テレビ局に勤めていたころ、私の後輩で元ソウル特派員のS氏に尋ねたことがある。「日韓関係を本当に正常化させるには何が最も必要か?」
正確な言葉遣いは忘れたが、大体そういう意味で聞いたのだ。S氏はしばらく考えていたが、やがてポツリと答えた。「それは天皇の韓国訪問でしょうね」 そのやり取りから10数年たったが、今でもS氏が言ったことは忘れられない。
昭和天皇も今上天皇も諸外国をずいぶん訪問されたが、最も近い国である韓国は訪問されていない。 逆に韓国の国家元首である何人もの大統領が、わが国を訪れた際に天皇陛下に謁見している。その中で最も印象的だったのは、1990年(平成2年)のノ・テウ大統領の訪日だったろう。
この時、今上天皇の“お言葉”は「我が国によってもたらされたこの不幸な時期に、貴国の人々が味わわれた苦しみを思い、わたくしは痛惜の念を禁じ得ません」というものだった。
それ以降、日韓関係は順調に推移していったと思うが、最近になってその関係はどうもギクシャクし、悪化してきたようだ。特に2012年8月のイ・ミョンバク前大統領の発言は、大きな物議をかもした。 それは「日王が痛惜の念などという単語ひとつを言いに来るのなら、訪韓の必要はない。日王は韓国に来たければ、韓国の独立運動家が全てこの世を去る前に、心から謝罪せよ」というものだった。
“日王”というのは天皇を指す言葉だが、天皇に正式に謝罪を要求したことで、日本国内では一気にイ・ミョンバクへの非難、反韓感情が高まった。イ・ミョンバクはその直前、韓国の大統領としては初めて竹島に上陸したことから、なおさら反韓感情を煽ったのである。
日韓関係はその後、慰安婦問題や歴史認識などで対立が続いているが、それは周知の事実なので省略しよう。ここで問題にしたいのは「天皇訪韓」のことである。イ・ミョンバクはまるで日本側がそれを望んでいるかのように言っているが、そんな話は誰も聞いていないだろう。外務省や宮内庁で内々に話し合われているかもしれないが、まだ全くの“絵空事”である。
しかし、イ・ミョンバクが公式に発言したこと、また韓国情勢に詳しいS氏が述べたことで、天皇訪韓はいつか実現すると思っている。 多くの人はもう忘れたかもしれないが、今上天皇は1992年(平成4年)10月に中国を訪問されている。日中関係にとってはとても有意義ななご訪問だったと思う。
さて、日中関係の話はさておき、日韓関係はいま相当に悪い。ちょっとやそっとで改善されるとは思えない。慰安婦問題や歴史認識のほかに、産経新聞ソウル特派員の起訴事件などが相次いでいる。これは報道機関への“弾圧”と言える。だから、天皇訪韓などいま口にすべきことではないが、関係が悪化しているからこそ胸に去来するのだ。
日韓議員連盟のメンバーも韓国を訪問した。私は韓国にある種の“不信感”を持っているが、日韓関係がいつまでも不正常なのは良くないと思っている。いつの日か関係は修復されるものと期待するが、それでつい「天皇訪韓」の夢物語(?)をしてしまった。お笑いになる人も多いだろうか。しかし、韓国は地理的に日本に最も近い国なのだ。(2014年10月26日)