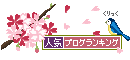小澤征爾指揮のマーラー、交響曲第八番の80年の録音です。定期演奏会からほどなく制作を敢行。マーラー作品中、最大規模の作品はその規模の大きさから上演至難のため実演の機会も限られます。そこで録音に触れることになるわけですが、規模の大きさは録音の難しさにも直結しています。71年のショルティ盤などはアナログ期でも最上の音響でした。細部の拾い出しと大音量、レンジは広くシカゴ交響楽団の名技も堪能できるものでした。実演に接するとこういった響きを耳にすることはできません。壮大な規模はイベント、機会性も高く音楽を聞くという以上に体験するという意味合いを持つのものです。ジョージ・セルも数は少ないものですがマーラーの交響曲を録音しています。セルはイマジネーションまで振っていると言われるほどに、合奏を練り上げました。交響曲第六番などでは、高い精度で合奏力の高さを確認できるでしょう。小澤征爾のマーラーは、細部を熟考して練り上げるものではありません。セルのマーラーとは対称的です。外に照射する熱量の多さが持ち味です。こうした演奏は実演でこそ最大の効果を上げるものです。反対に、スタジオ制作にはその魅力が乗りづらいということがあります。小澤征爾、ボストン交響楽団の組み合わせではレコード・アカデミー賞を受賞したシェーンベルクの大作、グレの歌の録音がありました。こちらは79年の録音で、録音上にも大規模編成の制作ということで近接します。グレの歌は二十世紀初頭に書きはじめられ、一旦、中断しました。その後、十年以上間をあけて完成されました。巨大な編成はマーラーの影響を強く受けていたとされています。マーラーは第八交響曲について「宇宙の震え、鳴り響く様」といった音響について触れています。その初演はマーラーの生涯中でも大きな頂点を築くことになりました。歌入りの交響曲。そして、文学、思想的な背景はテキストにも及んでいます。小澤征爾の盛期とも言える時期のふたつの大作録音はそういった機会性にも対応。第八交響曲盤面の指揮ぶりには情熱的な表現意思がみなぎります。テンポは早く、粘性には乏しいですが、楽器はよく鳴っています。
「大地の歌」には東洋的な死生観が反映しています。マーラーの音楽の展開には、西欧音楽の歴史的な層の積み重ねで成り立ったものではありません。広くひらかれて世界となっているものです。交響曲という以上に、大規模なカンタータにも聞こえます。異形な作品ですが、核心的な第二部の終結には心揺さぶられます。