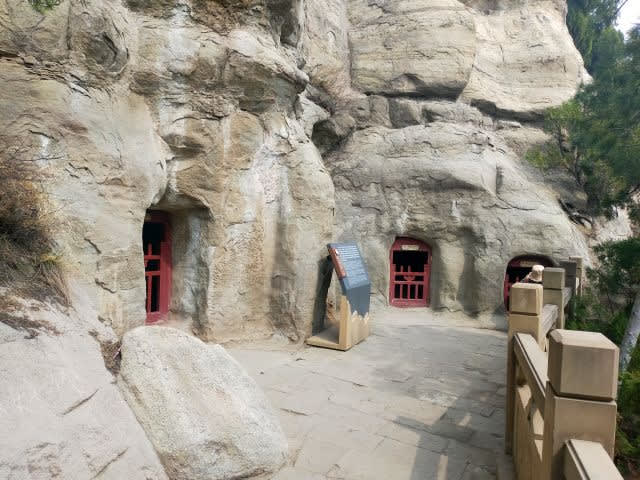G1954は、山西省の運城北駅から、浙江省の嘉興南駅まで12時間半ほどで結ぶ高速鉄道列車です。
太原南駅から蘇州北駅までの乗車時間は8時間23分です。

G1954のルートはちょっと変わっていて、
始発の運城北駅は、黄河沿いの西安と洛陽の間にある三門峡に近く、
太原まで大きく北上して東に向きを変え、石家庄から南へ戻って鄭州や合肥、南京、蘇州、上海、
終点の浙江省嘉興へと向かいます。

出典:百度 G1954次列车运行图
前日、早朝から夜遅くまで歩いたのでこの日はもうどこにも出かける気も起きず、
ホテルで少し遅めの朝食をとってから、太原南駅へ向かうことに。
太原でまだ食べていなかった山西省の名物はホテルの朝食で頂きます。

太原といえば黒酢。豆腐脳(おぼろ豆腐)には黒酢をかけて。
それに刀削麺も。
でも、自分好みの味付けをするタイプは、調味料の名前や色だけでは判断が難しく味が決まりません。

太原南駅はまだ地下鉄が繋がっていないので公共バスで移動です。
太原駅と太原南駅は10kmほど離れています。バスでの移動時間は1時間ぐらいです。

太原南駅が開業したのは2014年ごろのようで、比較的新しい駅です。
駅の周辺は商業施設やマンションを建設中です。

広い駅構内の上の階には売店や飲食店などもそれなりに並んでいて、食事や食料の調達は問題さなそうです。
規模は違いますが上の階に店が並んでいるのは、上海虹橋駅や長春駅と同じような感じです。

G1954の太原南駅発車時刻は12時26分、蘇州北駅には20時49分着です。
長丁場に備えて、飲み物(もちろんビールも)、おつまみなどしっかり買い込んで乗車。

太原から河北省の石家庄までの間は、炭鉱と黄土高原の景色です。
線路沿いに大きな都市はないようです。

高速鉄道の窓ガラスは、普通列車に比べると少しはマシです。
天気も良かったので行きは楽しめなかった車窓の風景を楽しむことができました。

列車は石家庄で向きが変わります。なので石家庄の停車時間は25分と長めです。
座席は回転式ではなく、倒して簡単に向きが変えられるようになっているタイプです。

最初の方向だと席は東側で、日よけを降ろさずにゆっくり景色を楽しめると思っていたのに、
向きが変わったので、残念ながら西日に照らされることになりました。
黄河を渡ったのは15時を過ぎ、一瞬で通り過ぎてしまいますが水のある黄河を見るのも久ぶりです。

16時に河南省の省都、鄭州の鄭州東駅に到着。遠くに二七記念塔が見えています。
前に鄭州に行ったのが2019年なので、それからもう5年も経ちました。

蘇州までまだ残り半分、久しぶりに高鉄の弁当を食べてみました。
G1954は山西省の管轄なので、車内販売の弁当も山西省の会社が作っています。
パッケージには山西省ゆかりのものが描かれています。

販売員に聞くと、土豆紅焼肉弁当と宮爆牛肉弁当の2種類あって値段はどちらも45元。
車内の売店まで行けば、他の種類もあるかもしれません。
地域差はきっとあると思いますが、昔に比べるとずいぶん見た目も味も良くなった気がします。
何となく、日本にもありそうな中華幕の内弁当風でした。
ちなみに、地域差なく同じなのは触れないくらいに加熱されて席まで持ってきてくれることです。

弁当を食べ終わるころには日も暮れて、列車は安徽省内を走行中です。
ここまでくるともう普段見慣れた景色に近くなります。

今回の太原旅行は列車内1泊、現地1泊、半分は列車の中でした。
私は窓の外をボーっと眺めているのが好きなのですが、
中国では、ほとんどの人にとって列車は単なる移動手段のひとつに過ぎないので、
スマホやタブレットの画面を見やすくするためにすぐサンシェードを降ろされてしまいます。
日が当たる場合は、自発的に日が当たらないぐらいまでサンシェードを下げて、
外を見ていますアピールをして視界を確保しています。