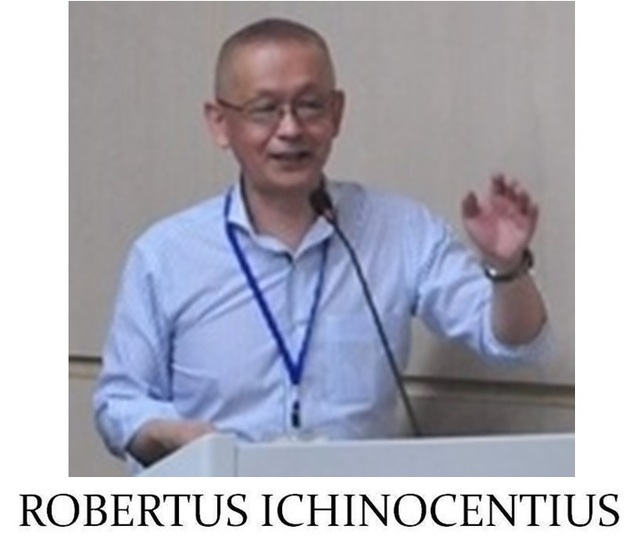Accepted (Forthcoming).
Ichinose, T., Y. Pan, Y. Yoshida (2024):
Clothing color effect as a target of the smallest scale climate change adaptation.
International Journal of Biometeorology.
これで取材対応もシンプルに歯切れよく。一ヶ月ほど余計に待たされて焦った。プレプリント出た後にリジェクトは悲惨なので。目下人生における論文出版の遅れは4年。
これで2019年夏の状態に戻った。バリバリの現役時に出すべき最後の1本が依然存在。しかし最近4年半でその内容が固まり、データ点検、作文を残す段階。あと数ヶ月は不要だろう。
Ichinose, T., Y. Pan, Y. Yoshida (2024):
Clothing color effect as a target of the smallest scale climate change adaptation.
International Journal of Biometeorology.
これで取材対応もシンプルに歯切れよく。一ヶ月ほど余計に待たされて焦った。プレプリント出た後にリジェクトは悲惨なので。目下人生における論文出版の遅れは4年。
これで2019年夏の状態に戻った。バリバリの現役時に出すべき最後の1本が依然存在。しかし最近4年半でその内容が固まり、データ点検、作文を残す段階。あと数ヶ月は不要だろう。
https://www.researchsquare.com/article/rs-3975360/v1