今回の記事では、身体の各関節に存在する、【関節の凹凸の法則(Concave-Convex Rule)】についてまとめていきます。
この法則は、徒手介入で他動的に関節を動かす際に最低限必要となる知識です。また、運動療法において、運動を補助・アシストする上でも必要になります。

各関節の凹凸の理解を深めることで、あらゆる臨床場面での応用が可能となります。
理学療法士・トレーナーとしてワンランクアップさせるための基礎知識、絶対に押さえておきたい必須ポイントです!
スポンサードサーチ
凹凸の法則
関節は、骨同士が接触している箇所であり、体の運動と機能に欠かせない重要な要素です。関節が正しく機能するためには、正確な形状や構造を有する必要があります。
関節の形状や構造は、関節の凹凸の法則に基づいています。
関節面の形状がお互いに凹凸を成すことで、安定した関節結合と関節運動が可能となります。また、関節の凹凸の法則によって、関節の可動域や安定性が決まります。
反対に、運動する関節面が凸の場合、滑りは骨運動と反対方向に生じます。
上記のように、運動する関節面が凹の場合を『凹の法則』、凸の場合を『凸の法則』と呼びます。
凹の法則
凹の法則について解説します。
手指の伸展運動の際、指節骨頭は伸展方向へ運動します。近位の指節骨頭(凸)に対して遠位の指節骨頭(凹)が動く際は、関節窩の軸が凸側にあるため。凹側は骨運動と同方向に滑る運動が生じます。
足関節背屈運動の際、CKCの場合は距骨の凸面に対し、脛骨・腓骨の凹面が腹側・前方へ滑る運動が生じます。
つまり、骨運動と同方向に滑り運動が生じます。
凸の法則
凸の法則について解説します。
肩関節外転運動の際、上腕骨は外転方向へ運動します。肩甲骨関節窩に対して上腕骨頭が求心位を保つためには、関節窩を中心とした軸運動となるように上腕骨頭が尾側方向へ滑る運動が生じます。
足関節背屈運動の際、OKCの場合は脛骨・腓骨の凹面に対し、距骨の凸面が背側・後方へ滑る運動が生じます。
つまり、骨運動と反対方向に滑り運動が生じます。
この知識を臨床現場で活かすには、各関節の構造を理解した上で、実施肢位を考慮する必要があります。エクササイズ時に運動方向に対して適切に補助するとことで、動作機能改善に繋がるでしょう。
関節の形状
関節には、球関節や鞍関節など、さまざまな種類がありますが、関節面の形状はそれぞれの関節の機能に適しています。
・鞍関節
・半関節
・蝶番関節
・螺旋関節
・車軸関節
・楕円関節
・顆上関節
・平面関節
球関節は、球状の骨が凹状の骨に収まるような形状をしています。このような関節の形状は、関節が多方向に可動することを可能にしています。
鞍関節は、凹面の骨が凸面の骨にフィットするような形状をしています。このような関節の形状は、関節が前後に動くだけでなく、左右にも動かすことができる特殊な可動性を持たせることができます。
関節の凹凸の法則によって、関節の動きが安定するため、骨・関節の状態が健康的に維持され、身体運動機能を実現することができます。関節の動きが破綻し、関節の形状が適切でなくなった場合、関節の動きが制限されたり、痛みや機能障害が生じる可能性があります。
そのため、関節の凹凸の法則を理解することで、関節の機能を向上させるための治療や再発予防策の考察が可能となります。
スポンサードサーチ
各関節の凹凸の形状の一覧
各関節の凹凸の形状について、臨床的に使用頻度の高いものを抜粋してまとめます。
【下位頸椎椎間関節】上関節面:凸 下関節面:凹
【胸椎椎間関節】上関節面:凸 下関節面:凹
【腰椎椎間関節】上関節面:凹 下関節面:凸
【肩甲上腕関節】肩甲骨関節窩:凹 上腕骨頭:凸
【胸鎖関節】[挙上・下制]胸骨:凹 鎖骨:凸
[前突・後退]胸骨:凸 鎖骨:凹
【橈骨手根関節】橈骨:凹 近位手根列:凸
【手部・手指】近位手根骨:凸 遠位手根骨:凹
【股関節】寛骨臼:凹 大腿骨頭:凸
【脛骨大腿関節】大腿骨:凸 脛骨:凹
【膝蓋大腿関節】膝蓋骨:凸 大腿骨:凹
【距腿関節】脛骨・腓骨:凹 距骨:凸
【距骨下関節】[前・中関節面]距骨:凹 踵骨:凸
[後関節面] 距骨:凸 踵骨:凹
【足部・足趾】近位足根骨:凸 遠位足根骨:凹
以上が、関節の凹凸の法則について解説です。
関節は、私たちの日常生活において重要な役割を果たしているため、関節の構造と機能を理解することは、健康的な生活を送るために欠かせません。
参考文献
- 中村隆一, 斎藤宏, 他:基礎運動学(第6版補訂), 医歯薬出版株式会社, 2013
- 竹井仁:触診機能解剖カラーアトラス 上, 文光堂, 2013
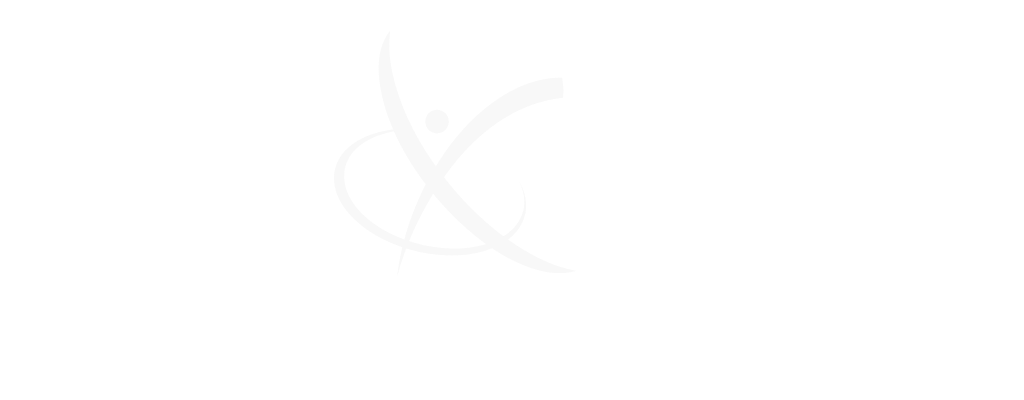
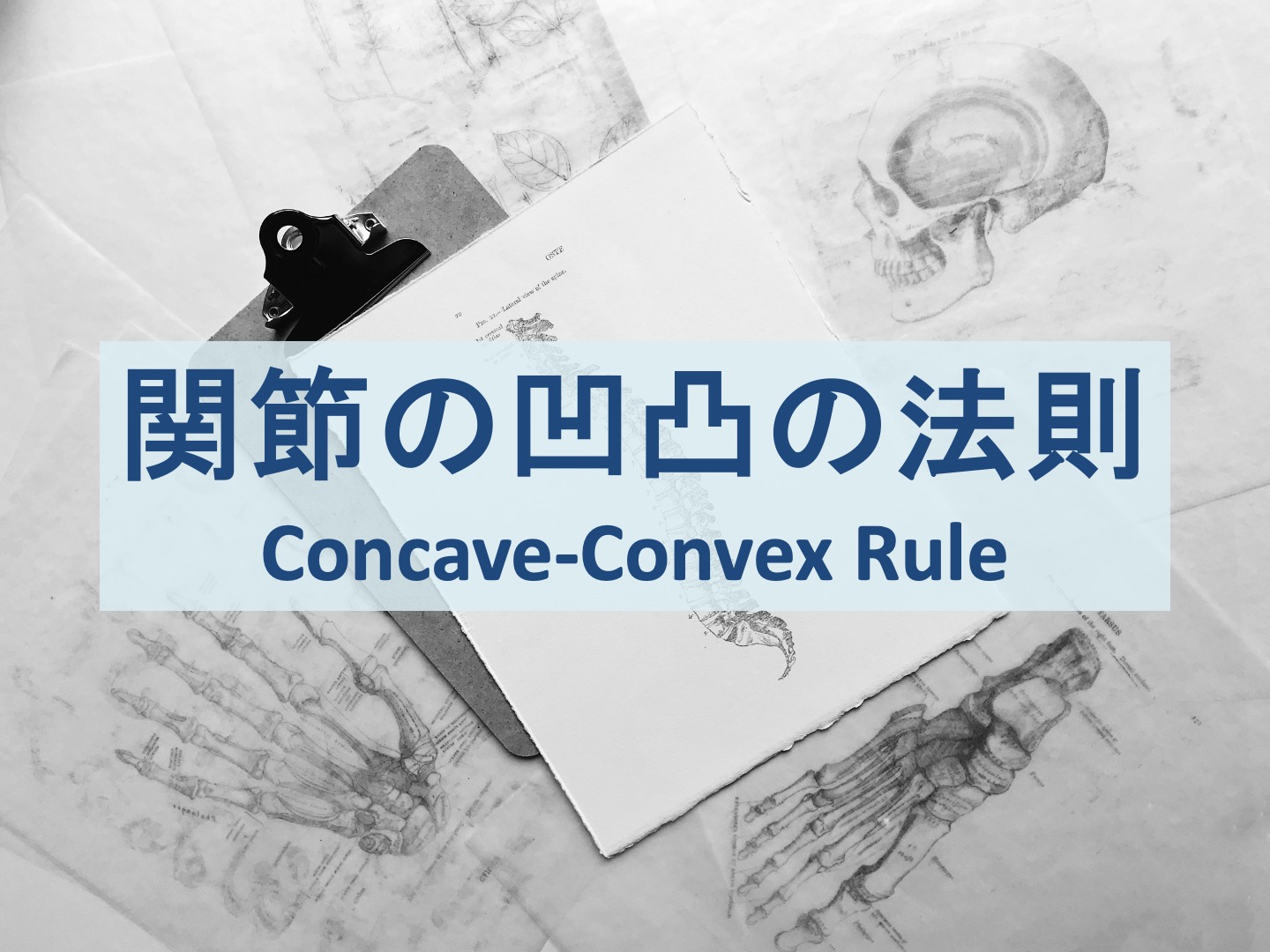

コメント