勤務しているF病院で、
主治医のKI医師、内科部長のY医師、
人工呼吸器設定などに関してお世話になった麻酔科のS医師に
話を伺うことができました。
皆さんお忙しい方なので、
どのような意図で何を聴きたいのか明確にして
できるだけ短時間で済むようにして臨みました。
主治医のKI医師と内科部長のY医師には、
内科外来担当の日に、
比較的楽に声をかけることができたのですが、
私の勤務部署と無関係の
S麻酔科医師とはなかなか会うことが難しく
(院内用のPHSでお呼びするのは失礼と思い)
休憩時間に立ち寄られそうな場所をウロウロしたり
担当の麻酔科外来の周辺を覗いたり…と、
予想以上に苦労しました。結局、外来の廊下で
立ち話のような形で話をさせていただきました。。
母が亡くなったのは1月、お話できたのは7月の上旬で
かなりの時間が経っていましたが、
3人の医師はいずれも(症状や病態が重かったためか)
母の経過を詳しく憶えられていて、
スムーズに聴取することができました。
ポイントは、Z病院の診療やF病院転院時の母の状態です。
確認事項は
・(Z病院で)発熱後3日間放置されたことは予後(病気の結果)に影響したか
・早期にF病院に転院すれば救命できたか
・肺炎が悪化した年末に、F病院で投与された抗菌剤(抗生物質)の選択は妥当か
・画像診断や血液ガス分析がされていないことについての見解
・細菌検査(起炎菌の特定)や感受性テストは、現在の医療では必須か
・母のような状態で、医師の診察・訪室がない(Z病院)ことについて
などです。
<<主治医のKI医師>>
・肺炎は初期治療が肝心。
発熱当初に治療がされなかったことは予後への影響は大きい。
自分では、放置することは考えられない。
もし発熱していることを報告されてなかったのなら、その看護師の責任も重大。
早くに当院に来ていれば、助かった確立は高い。
・転院時はすでに肺炎に合併した成人呼吸促迫症候群の状態だった。
有効な治療法があるので、重症化する前に
適切に行っていれば効果があった可能性は高い。
・抗菌剤の選択も自分とは違う。
Z病院入院時(11月)に使用して効果があった薬剤をまず使うべき。
それで効果がなければ、さらに強いものを選択する。
(具体的に薬品名を言われましたが、ここでは省略します)
・肺炎を少しでも疑うならレントゲン撮影は必須。血液ガス分析も同様。
SpO2 90%0を下回る状態で酸素投与をしないのは不可解。
細菌検査も通常は行うべきであり、Z病院のスタンスがわからない。
・診察行為がないことは、医師の応召義務に反していると思う。
KI医師は、私が訴訟を考慮している旨を伝えた後も、終始好意的で、
「カルテを早く差し押さえた方がいい」
「弁護士さんが言っているようにやはり争点は
“治療の遅れ”“転院の遅れ”がポイントになるだろう」
「僕も証言台に立った方がいいのかな…」などと発言されました。
また、翌日『肺炎診療ガイドライン』をコピーして手渡して下さいました。
<<呼吸器科部長 Y医師>>
・治療がされなかった3日間で肺炎が悪化したことは考えられる。
予後に影響しただろう。
・早期に転院していれば救命できた可能性はある。
・Z病院で使用した抗菌剤も広域性で決して間違いとは言えないが、
自分なら(あの状況なら)
別の薬剤(Z病院で使われた抗菌剤より強力な薬剤名)を使う。
・検査はどれも必須。SpO2 80台~90前後なら酸素を投与するべき。
<<麻酔科S医師>>
・治療が遅れた3日間の状態がわからないので何とも言えないが…
治療は早いに越したことはない、タイミングが大事。
坂道を転がるように悪化する例は少なくない。
・当院に搬送された時点では重症肺炎で、
人工呼吸管理が必要な呼吸不全状態だったのは明確である。
・年末年始だったので主治医が不在でアルバイトなどの当直医が診ていたのなら、
検査・治療指示が遅れたことは想像できる。
(…実際は主治医が病床を訪れていましたが)
S医師とは立ち話の状況だったため、
私はZ病院での母の状態や行われた医療に関して
十分な説明ができませんでした。
また彼が“呼吸器科専門ではない”という立場から、
明言を避けられた印象を受けました。
++++++++++++++++++++++++++++++
また並行して、F病院でのカルテの開示・コピーに着手しました。
まずは市の病院事業局宛てに、診療記録の開示の申し出…。
これに対して病院事業管理者から
「診療記録開示決定書」が通知されました。
この通知書とともに本人確認ができる書類等を持参し
病院の担当係へ提示するよう記載されていました。
(私の場合は、庶務の方も見知った職員でしたし
私自身が職場のユニフォームを着ていたので
“本人確認”のものは不要でしたが。)
一番悩んだのが…病院職員である私が
「何故、母のカルテ開示が必要なのか」を
どのように説明するべきか…でした。
いろいろ考えて庶務に赴きましたが、
何も聞かれることはなかったのです。
確認されたのはコピーの部数だったり…で
あとは所要時間・日数や料金についての説明を受け
意外にも、すんなりと終わりました。
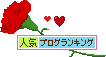 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ↑↑ clickお願いします…お力をください。











F病院の医師の見解はどれも優等生的ですが、逆に言いますとZ病院の対応が劣等生的なのでしょう。
その(=Z病院の)医学的な対応とお母様のご逝去との因果関係を立証するのは、原告側です。
「もし、あの時・・」、「私だったら・・」
程度では足りないのでしょう。 たった一つの命です、「もし」、「れば」、「たら」は不要です。
だからこそ、ガイドラインのコピーをくださったのでしょうね?
心強い限りです。
>医学的な対応とお母様のご逝去との因果関係を立証する
行われなかった検査の必要性・抗菌剤の不適切な使用など…
これらを証明していくことになります。
また呼吸器の専門でない医師に、ガイドラインに沿った医療をどこまで求められるか…もポイントなのです。