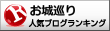信州の
高遠城跡を訪問しました。
<高遠城跡>
たかとおじょう
築城年や築城者についての詳細は分かっていませんが、諏訪氏の分家である
高遠氏が拠点とした城でした。その高遠氏が甲斐の
武田信玄によって滅ぼされると、城には大改修が施され、
武田氏の南信濃支配の拠点として機能し続けました。
<案内板>

高遠城は二本の川の合流地点の崖上に位置するため、三方が川という要害です。曲輪の配置はシンプルですが、攻めるのに難儀な山城(平山城)だったことでしょう。
<三峰川>
みぶがわ
こちらは高遠城の南側を流れる三峰川です。右手が高遠城。崖になっており、地形の険けわしさを利用した城だったことが伝わってきます。川から本丸までの高低差は約80mです。
武田氏が改修した時には、あの山本勘助が縄張りしたとも言われています。現在、城址公園西側の駐車場となっている区画は勘助曲輪と呼ばれていますが、そのなごりでしょうかね(不明)?
信玄亡きあと、
織田信長による甲州征伐により、約35年続いた武田氏の支配は終焉をむかえます。武田家臣団の士気は徐々に低下し、離反や逃亡が相次ぎました。そんななか、高遠城では
勝頼の弟で城主の仁科五郎盛信が3千の兵で抵抗を試みました。しかし相手は信長嫡男・信忠が率いる5万の大軍です。数的不利は如何ともし難く、高遠城は一日で陥落。仁科盛信は自害しました(1582年)。その後、当主の勝頼も天目山で自害し、戦国大名としての武田氏は滅びました。
<高遠城の戦い説明板>

戦いは壮絶で、双方に多数の犠牲者がでました。
本能寺の変は、武田勝頼が亡くなってから僅か3ケ月後のことです。織田信長がいなくなった混乱期に、
高遠城を手にしたのは、武田の旧臣である保科正直でした。保科正直は徳川家康の支配下となります。
その徳川家康が関東移封となると、高遠は天下人となった豊臣秀吉の支配下となり、家臣の所領となりました。しかし関ヶ原の戦いの戦後処理で、日ノ本の勢力分布図は大幅に変わることとなり、高遠には
保科正直の長男・正光が2万5千石で入部し、高遠藩が成立。高遠城は藩庁として統治のための城となりました。
藩主となった保科正光に子はなく、
徳川秀忠の隠し子を跡取りとして養子に迎えます。その少年こそが、
高遠藩主・山形藩主を経たのちに、会津藩の初代藩主となる保科正之です。幕府の中枢となって将軍をサポートした保科正之は、多感な少年時代を高遠で過ごしました。
<保科正之像>
ほしなまさゆき
正之は会津松平家の祖となりますが、本人は養父の名・保科を生涯貫きました。
保科氏のあとは
鳥居氏(1636年から2代)、
内藤氏(1691年から8代)が藩主となりました。高遠城が廃城となるのは明治になってからです。
最後の藩主は内藤頼直でした。
<高遠城址公園>

左手に見えているのは三の丸と二の丸を隔てる堀跡です。城跡は高遠城址公園として整備され、多くの人が訪れる観光地となっています。特に高遠の桜は全国的に有名です。
<高遠桜>

やや色の濃い高遠桜は、タカトオコヒガンザクラという固有種です。私の訪問時はまだ蕾が多い状態でしたが、園内の約1500本の桜が満開となれば圧巻だと思います。高遠城の桜は、
城跡の荒廃を憂いた旧藩士たちが、城下の馬場から桜を移植したことに始まります。
<伝 高遠城大手門>

こちらは大手門と伝わる遺構です。場所は高遠城の北西、駐車場になっている勘助曲輪の北側です。門前に設置されている現地説明板によれば、大手門は明治になって取り払われており、現役の時とは姿形が異なるようです。また、ここは大手口はここではありません。民間からの寄贈により移設され、高校の正門として使用されていたようです。
<武家屋敷跡>

先ほどの門より先は三の丸跡です。この付近は武家屋敷が建ち並んでいた区画になります。この更に奥(北側)がかつての大手口。高遠城の三の丸は、本丸・二の丸など城の中心部の北側と東側を囲むように設けられていました。
<進徳館跡>
しんとくかん
三の丸跡の藩校跡です。空き家となっていた元家老の屋敷を利用して、江戸末期に開校しました。
<高遠閣>
たかとおかく
こちらは二の丸跡の高遠閣。昭和になってから建てられたもので城と直接は関係ありませんが、登録有形文化財に登録されている貴重な建物です。
<堀跡>

二の丸側から見た本丸北側の堀跡。廃城は明治ですので、遺構は近世城郭として整備された江戸時代のものということになります。ただ城の縄張りは戦国時代、つまりは武田流を引き継いでいると思われます。
<問屋門>
とんやもん
城内に問屋門?この門はもともと城下の問屋役所にあったものです。問屋役所建物取り壊しの際、歴史ある門が失われることを惜しんだ町の有志の尽力により、城跡に移築されたものとのこと。城門だったわけではありませんが、今では城址公園には欠かせない存在となっています。
<問屋門と桜雲橋>
おううんきょう
問屋門の内側から撮影。手前側は本丸、門の向こう側は二の丸と本丸をつなぐ桜雲橋です。桜雲橋は高遠城址公園のなかでも特に人気のスポットです。橋から満開の桜を見上げると、花弁が雲の如く見えることが名の由来です。
<満開時の桜雲橋>

こちらは公園内に設置されている大きなパネルです。記念撮影用ですね。私は眺めることが叶いませんでしたが、満開の日に晴れていれば、きっとこんな感じなのでしょう。
<本丸虎口付近>

本丸の虎口付近。いい感じの石積みは、城門のなごりであろうと現地では思いましたが、どうも廃城後に設けられたもののようです。塁上には古戦場跡の説明板。
<太鼓櫓>
たいこやぐら
こちらは本丸跡の太鼓櫓です。番人がおかれ、太鼓で時を知らせる役割を担っていました。本来はこの場所ではないようです。
<新城神社・藤原神社>

こちらも本丸跡。新城神社と藤原神社がひとつの社に祀られています。
新城神社の祭神は仁科五郎盛信、藤原神社の祭神は
内藤家の祖先にあたる藤原鎌足、そして内藤家代々の当主です。
<本丸土塁跡>

本丸を縁取る土塁のなごり
<堀跡>

本丸と南曲輪を隔てる堀跡
<南曲輪>
みなみくるわ
本丸の南に位置する曲輪。柵の向こうは三峰川に面した崖です。
<南曲輪説明板>

南曲輪は保科家の養子となった保科正之が、幼少のころ実母と居住したところと言われています。
<白兎橋から見た堀>
はくときょう
南曲輪と法幢院曲輪の間の堀跡
<法幢院曲輪>
ほうどういんくるわ
南曲輪より更に南側の法幢院曲輪。高遠城の南端に位置します。
<空堀>

左手が法幢院曲輪です。適度な高低差と空堀。城跡好きが喜びそうな景色です。
高遠城は険しい地形を巧みに利用した山城ですが、現地は城址公園として整備され、比較的散策しやすい城跡となっています。多くの遺構が失われても、曲輪の周囲にめぐらされた深い堀が、むかしを偲ばせる形で残されています。戦国時代に激闘のあった古戦場であり、江戸時代も統治の中心地と存続した城です。国の史跡に指定され、日本100名城の一つにも選ばれています。
<つわものどもが夢の跡>
 ---------■ 高遠城 ■---------
---------■ 高遠城 ■---------別 名:兜山城
築城者:不明
築城年:不明
城 主:高遠氏・武田氏・仁科氏
保科氏・鳥居氏 他
改修者:武田氏
廃城年:1872年(明治5)
現 況:高遠城址公園
[長野県伊那市高遠町東高遠]
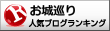 お城巡りランキング■参考
お城巡りランキング■参考
・高遠城址公園説明板
・Wikipedia:2024/4/27
・伊那市HP(高遠城址公園)https://www.inacity.jp/shisetsu/koenshisetsu/takatojoshikoen.html・長野伊那谷観光局HP
(高遠城物語)https://www.inadanikankou.jp/special/page/id=915