小アジア/アナトリア:歴史の十字路
アナトリア半島:古代から現代までの変遷
アナトリア半島、またの名を小アジアとは、西アジアの西端に位置する歴史的に重要な地域です。現在はトルコ共和国の一部となっていますが、この地はヒッタイト、ペルシア帝国、ローマ帝国、ビザンツ帝国、セルジューク朝、オスマン帝国といった多くの大国によって支配されてきました。アナトリアは、北に黒海、西にエーゲ海、南に地中海を臨み、東はアルメニア、メソポタミア、シリア地方へと続いています。この地域は、かつて「アジア」と呼ばれたローマ時代の属州の名前から、ヨーロッパに対する東方世界全体を指す言葉へと意味が拡大しました。その結果、「小アジア」という言葉が生まれ、本来のアジアと区別されるようになりました。現在では、アナトリアはトルコ語で「アナドル」と呼ばれ、トルコ共和国の主要な国土となっています。
小アジアのトルコ化とオリエント文明の影響
小アジアは現在トルコ共和国の一部であり、トルコ人がこの地に最初からいたわけではありません。古代にはヒッタイト王国やリディア王国が存在し、後にペルシア帝国、アレクサンドロス帝国、セレウコス朝、ローマ帝国によって支配されました。4世紀以降は東ローマ帝国、そしてビザンツ帝国の領土となりました。この地域は、ヘレニズム期からローマ時代にかけてギリシア文化・ローマ文化が支配的であり、ギリシア人やユダヤ人が多く住み、キリスト教が広まった地でもあります。また、オリエント文明の時代には、メソポタミア文明とエーゲ文明の橋渡しをする位置にあり、鉄鉱石が豊富であったため、早くから鉄器を作る技術が発展しました。ヒッタイトはこの技術を身につけ、前1650年頃からこの地で有力となりましたが、海の民の侵攻によって衰退しました。その後、リディア王国やアケメネス朝ペルシア帝国が支配し、エーゲ海岸にはギリシア人が進出して植民地を建設しました。
ヘレニズムからビザンツ時代への移行
ペルシア帝国がアレクサンドロスによって滅ぼされた後、セレウコス朝シリアがこの地を支配しましたが、前3世紀にはペルガモンが独立し、ヘレニズム文化が繁栄しました。小アジアにはポントス、カッパドキアなどのヘレニズム諸国が分立しました。ポントス王国は前1世紀にミトリダテス王の時代に強大となり、ローマとの間で三次にわたるミトリダテス戦争を展開しましたが、最終的にはローマ軍に制圧されました。ローマ時代には、小アジアの西部が属州アシアとなり、キリスト教が広まりました。330年にはコンスタンティヌス帝がコンスタンティノープルに遷都し、小アジアの重要性が高まりました。ビザンツ時代には、東ローマ帝国がギリシア化し、ビザンツ帝国として知られるようになりましたが、ササン朝ペルシアとの争いにより、小アジアを通る東西交易ルートは衰退しました。
オスマン帝国からトルコ共和国への変遷
1071年のマンジケルトの戦いでビザンツ帝国軍が敗北した後、トルコ系民族がアナトリアに流入し、セルジューク朝の地方政権ルーム=セルジューク朝の支配が続きました。1242年のモンゴルの侵入後、イル=ハン国に服属し、13世紀後半には小国家が分立しました。その中の一つがオスマン=ベイであり、これが後のオスマン帝国の基となりました。第一次世界大戦後、1922年にオスマン帝国は消滅し、翌年にはトルコ共和国が成立しました。ケマル=アタチュルクの指導の下で近代化を目指す改革が進められ、政教分離の原則が掲げられました。小アジアはヨーロッパとアジアの接点に位置し、現在はトルコのEU加盟問題やイスラーム原理主義の台頭など、多くの課題を抱えています。また、アルメニアとの対立、クルド人の独立運動、ギリシアとの領土紛争(キプロス紛争)も小アジア情勢の周辺に存在しています。
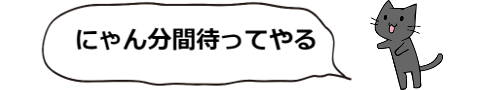
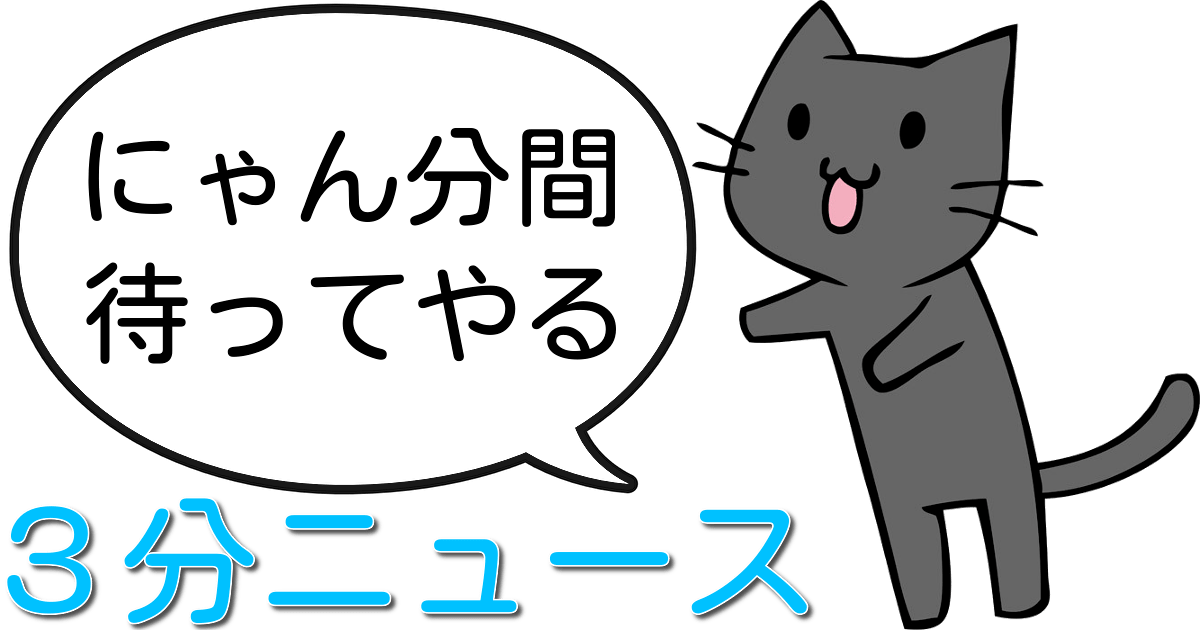
コメント