はじめに
中国農村部では土地などの不動産に関する財産権が長らく認められてきませんでした。これに対して都市部の家族には住宅民営化以降の2003年頃から完全な形の財産権が付与されてきました。つまり都市部の家族は自分達の住宅や土地を時機を見て市場価格で売却し、大きな利益を得ることが出来ますが、一方の農村地帯の家族は彼らの土地を使用する権利はあってもそれを市場価格で不動産開発業者に売却するなどと言う事は出来ないのです。その代わりに彼ら農夫達は近郊の都市政府によって彼らの土地を不当に安く買い上げられてしまう事が多かったのです。近年、農村と都市部でのこうした財産権の違いはそれらの間での富や収入の格差を助長する物として中国政府にも問題視される様になりました。
そこで中国政府は農村経済を都市的な不動産事業などと言う不健全な方法で活性化するのではなく、農地の集団所有を古来から続いているものとして神聖視し、耕作地総面積をある一定以上に保つ事を前提に農村古来の農業を大事にしながら徐々に改革していこうとしてきました。その改革手法としては主に三つあります。一つ目は政府への農地登録件数を増加させることにより多くの農夫たちが彼らの農地を比較的自由に使える様にする事です。二つ目は個々の農夫から土地使用権を買い上げ、農業を一つの巨大な事業に統合し、これによって可能になる機械化された大規模農業を農夫からの出資によって作られた株式会社によって経営する事です。そして三つめの改革は農村の広域に散らばった小さな村々を高密度な町として統合し、それによって農地面積を増加させ、農業効率を上げる、いわゆる“町化”です。
今回はこの内三つ目の“町化”に焦点を当て、農村経済の改革の様子を解説して行きます。またその後で中国の食糧事情と世界の農業事情の関係などについても解説します。
農村経済の改革の一つ“町化”のプロセス
都市部との間の格差が問題視されてきた中国の農村経済を改革する為に、現在農村では、“町化”と言う改革が行われています。町化とは、農村部に広く散らばった村々を元の立地からある特定の場所に移動させ集合させる事により、より高密度な町に統合する作業の事です。ちなみにこの"町化"とは英語の"townization"を日本語に訳したものです。都市化(urbanization)と対比される意味の言葉ですね。中国の都市で起きるのがurbanization、農村で起きるのがtownizationである、と覚えておきましょう。
このプロセスでは、元の村は取り壊され、その土地は耕作用地に戻されます。そして重要なのが、このプロセスを経て新たに出来る町と言うのは元の散らばっていた村々の占めていた総面積よりも遥かに狭い面積しか占有しないので、結果として使用されない土地が耕作用地として大量に発生し、耕作地の総量を増加させることが出来るという事です。
こうした村々の圧縮プロセスである“町化”の後、農夫達はどの様な生活を送る事になるのでしょうか?
町化の後の農夫達の進路
こうした村々の圧縮プロセスである“町化”の後、農夫達はどの様な生活を送る事になるのでしょうか?
勿論、彼らは農地の使用権を相変わらず保持し、もし彼らが望むのであれば、農地を耕作し、農業を続ける事も出来ます。しかし恐らく、大半の農夫は町化の後、自分達の農地の使用権を別の農夫や農業事業者に移管し、それによる収益を持って農業から離れ、都市部のより高収入の職業で働き始める事に決めるでしょう。つまりこの政策によって農村の民が徐々に都市化に参入するようになるのです。
しかしこれによって農地が失われるのではなく、逆に農地の供給量を維持、或いはさらに増加させる事になると言う点が町化の素晴らしい所なのです。
農夫の数が減少する一方で先述したように農地面積は増える事になるのですから、農夫一人当たりの耕作面積は増加し、従ってより大規模で高効率の農業が生まれる事になる、と考えられる訳です。そして一方の農業をやめた人々は都市に行ってより生産性の高い高度な職業に就くことが出来るのですから、中国経済にとってこれは大きな躍進に繋がると期待されています。
これまで中国の農村経済を改革によって如何に改善するかについて述べてきました。ここで農村経済についての最終的な疑問に焦点を当ててみたいと思います。農村の仕事と言うのは農業を通じて食料を国内、或いは海外に供給する事ですが、その供給量は果たして中国を養って行くのに十分なのか、という事です。或いは自国で賄わなくても、海外から輸入した食料で中国を養おうとした場合、世界の食糧事情に影響はないかという事なのです。
中国は自身を養っていけるか?
これまで中国の農村経済を改革によって如何に改善するかについて述べてきました。ここで農村経済についての最終的な疑問に焦点を当ててみたいと思います。農村の仕事と言うのは農業を通じて食料を国内、或いは海外に供給する事ですが、その供給量は果たして中国を養って行くのに十分なのか、という事です。或いは自国で賄わなくても、海外から輸入した食料で中国を養おうとした場合、世界の食糧事情に影響はないかという事なのです。
この疑問は中国だけでなく、その他の全世界の国々にとっても非常に意味深いものです。何故ならもし中国の14億人の人口を養う為に中国が大規模な食料輸入を始める事になれば、供給量のかなりの部分を中国に吸い取られた世界の食料価格への影響は非常に大きいと考えられるからです。
中国の食欲(食料需要)は旺盛です。もし中国が食料を自給する事を怠り、外国からの輸入に頼る様になれば、それによって世界の食料価格は高騰する事になると考えられます。また同時に、そうした中国の圧倒的な食料需要によって、世界の少ない耕作地供給が圧迫され、さらに多くの農地を開発によって作り出さなければ農産物の生産が追い付かなくなる可能性があります。
中国の旺盛な食欲と世界の食料価格、耕作地面積の関係
中国の食欲(食料需要)は旺盛です。もし中国が食料を自給する事を怠り、外国からの輸入に頼る様になれば、それによって世界の食料価格は高騰する事になると考えられます。また同時に、そうした中国の圧倒的な食料需要によって、世界の少ない耕作地供給が圧迫され、さらに多くの農地を開発によって作り出さなければ農産物の生産が追い付かなくなる可能性があります。
この悪夢が現実になるかどうかは、人口14億人と言う規模の大国である中国農村の農産物の生産性によって左右されるでしょう。もし中国が農産物の生産を怠れば、世界中で食料供給が滞り、食料価格が上昇しかねないのです。だから中国農村部の農業事情が我々日本人も含めた外国人にとっても非常に大事な問題なのです。
中国の農村経済の改革政策として“町化”のプロセスを見てきました。町化では農村に分散した小さな村々を圧縮してより高密度な町に統合し、それによって多量に出来る不要になった土地が農地として復活する事で、農業の一層の効率化が行われることが期待されています。この町化によって、多くの農夫達は農業を止め、都市へ出て行きそこでより生産性の高い比較的高賃金の職業に就く様になると見込まれています。しかしその一方で農地面積は増えるので、今後中国の農業が機械などを導入した大規模農業へシフトして行けば農夫人口が減ったとしても農産物の自給率には悪影響はない様です。
まとめ
中国の農村経済の改革政策として“町化”のプロセスを見てきました。町化では農村に分散した小さな村々を圧縮してより高密度な町に統合し、それによって多量に出来る不要になった土地が農地として復活する事で、農業の一層の効率化が行われることが期待されています。この町化によって、多くの農夫達は農業を止め、都市へ出て行きそこでより生産性の高い比較的高賃金の職業に就く様になると見込まれています。しかしその一方で農地面積は増えるので、今後中国の農業が機械などを導入した大規模農業へシフトして行けば農夫人口が減ったとしても農産物の自給率には悪影響はない様です。
また、懸念されている中国の食糧事情ですが、中国がその人口を養う為にもし大規模に食料を輸入する事になれば、世界的な食料価格への影響は大きくなると予想されています。中国の巨大な食糧需要によって世界の食料価格が高騰したり、或いは耕作地面積が足りなくなってしまう事態が引き起こされかねないのです。そしてそうした事が起こらないようにするためにも、中国農村部の農業を大事にし、食料自給率を維持、向上していくことが不可欠なのです。
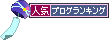
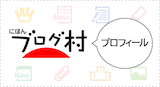
0 件のコメント:
コメントを投稿