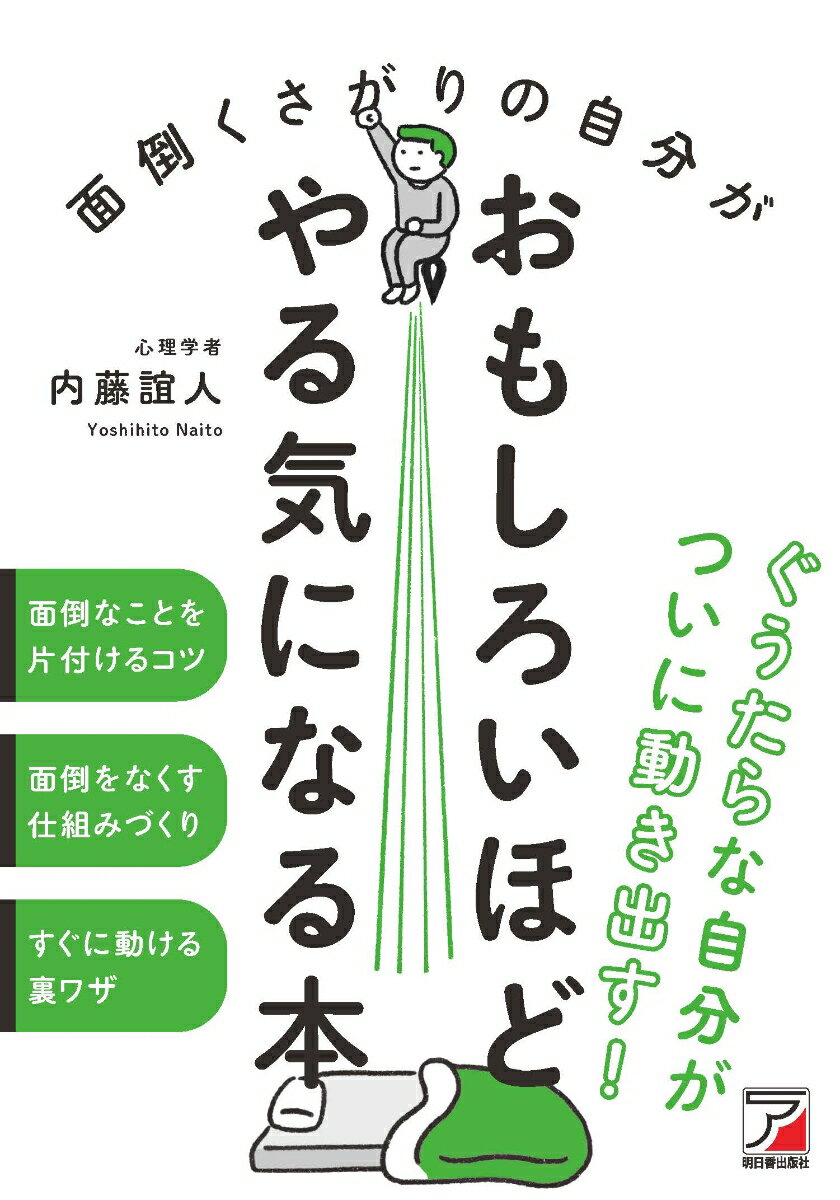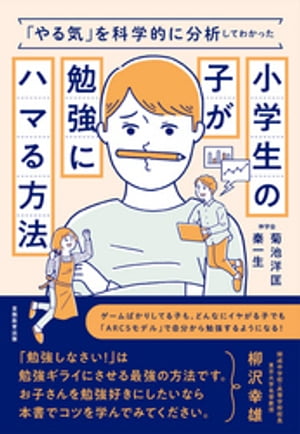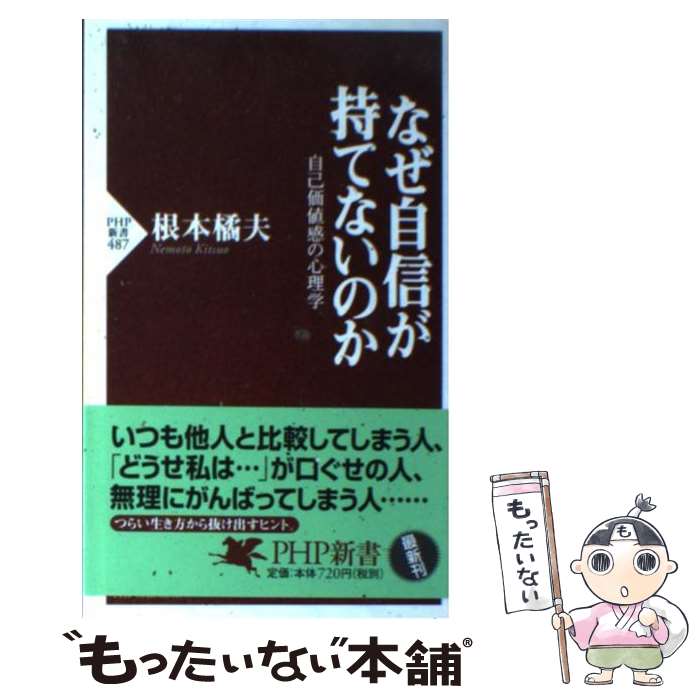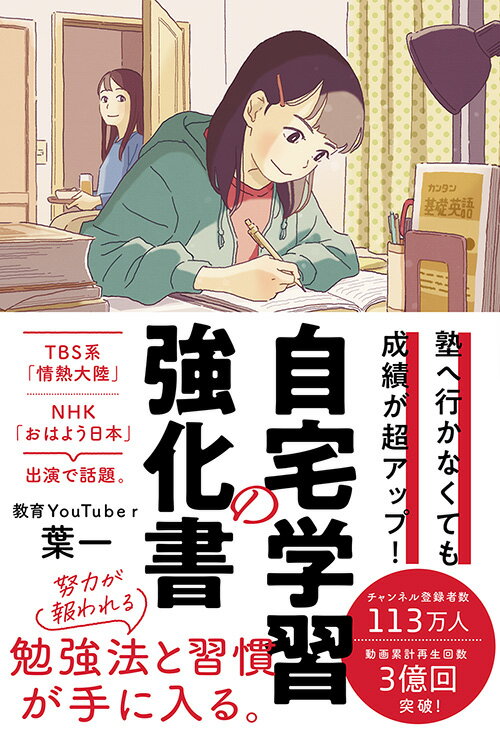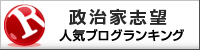子どもの事に関わっていると、必ず交わす会話
「どうやったらこの子のやる気を出させてあげられるだろう」
そう考えて、子どもの自発的な成長を望んでるわけですが
そもそも、やる気って何?
やる気にならない原因はどこにある?
やる気になるには何が必要?
実際やる気を出すには?
そんな事をふと思ったので、まとめて見ようと思う。
やる気って何?
子どもの事を考える時、大人から見た子どもと、子ども目線に立って子どもの立場で考えるという事があると思います。
ただ、フォーカスを子どもに持っていく必要はないのではないかと思います。
自分が子どもの頃からいまに至るまでの成長を思い返した時、人生を歩んでる本人にとっては、“子どもとしての意識”ではなく、ひとりの自分という意識でいた事に気づきます。
それは大人になった今も連続的に続き、周りとの比較対照的に大人という立場であっても、“わたしという一人の人”という状態は死ぬまで続きます。
だからあえて、子どもの立場ではなく、大人である立場で考えても、同じ事が言えるなというので、自分ならどうだ?と考えると、さほどわかりにくい問題でなくなります。
大人の皆さんも日々、やる気との闘いな気がしますよね。
ほんとはやったほうがいいのはわかってるけど、いまいち気分が乗らない。
やる気スイッチが入ると、いきなり精を出して動き出す。
様々な決断をやる気に翻弄されて判断してる事も多々あります。
でも、やらないと行けない時はやる気になりたいですよね。
やる気にならない原因はどこ?
頭で考えていると思っている大半は、感情が根本にあります。
なので、やる気になってない時の感情を見ればわかるのですが、
・動作そのものがしんどい
・得意な事ではない
・優先順位が中途半端
・過去にやった時に嫌な思いをした
などなど、色々あると思いますが、現代人及び日本人は真面目がゆえに特に、
・タスクを完璧にこなそうとする
・やらないといけないという焦りで逆に身動きがとれない
・最低限の事だけだでもやる事多くて疲れきってしまう
・自分がそこまでやらなくてもいいのではと放棄してしまう
など、思考を巡らせば巡らすほど、時間だけが過ぎていき、できなかった事に対して自己評価が下がるという風に悪循環にも思えます。
それは子どもとて一緒で、行動するまでの気持ちがそこに向いてない以上、無理やりやらされるほど苦痛なものはありません。
だからこそ、自発的にやる気になって欲しいと思うわけですが、もし自分なら何があれば自発的になれると思いますか?
やる気になる材料は?
早い話し、先程のやる気になれない理由を解消していけばいいので、
・タスクが多いなら、タスクを減らす
・やらないといけないという想いを軽くする
・疲れるほど他の事を頑張りすぎない
・絶対に自分がやらないといけないと言うことはないので判別をつける
これらができると、まず心に余裕が生まれます。
人は本来探究心の塊なので、余裕があれば、あれこれやりたい事が湧いてくるでしょう。
ただ、上記の事を実践しようと思っても
そうは言ってもやらないといけないんだから、そこを困ってるんだよと突っ込まれると思いまして、より実践的な方法を考えたいと思います。
やる気への転換方法
それにはこれまで語ってきた、やる気でない時の感情ではなく、“やる気になっている時”の感情に目を向けます。
やる気に満ち溢れている時はかなりシンプルで
・楽しい、面白いという感情がある
・やった後の報酬を求めている
大きくはその2点かなと思います。
他人のために尽くして感謝されるときも、感謝されて嬉しい、自己評価が上がるという報酬への感情であり、世の中でなぜそこまでしてボランティアしてるの?という人は、そこを求めていると思います。
自己満かよとか、偽善者かよとか、そういう見方をすればそうかもしれませんが、自己満でも偽善者でも、相手がそれで助かって喜んでくれてるなら、結果良いのではないでしょうか?
助ける側、助けられる側、双方が漫才していれば外野がどうこう言う必要はありません。
それが、やっていて楽しいという感覚があるからこそ、生き甲斐だあったり、さらにもっと解決できる事はないかとアイデアも湧いてくるわけですね。
どんな仕事、どんな作業でも同じ事が言えて、
やってる時の充実感と、やった後の達成感
その2つが存在すると、もうやる気の波に乗っかっちゃってるので、それを子どもたちにも与えてあげられると、やる気スイッチが入るわけですね。
スイッチの入れ方は人によって違う
まとめとして、
中には他人から聞いてとか動画を見て勉強して、それでもうちの子はやる気が起きないという事があるでしょう。
それは単純で、その子に合ったやり方ではないというだけです。
そこが一番難しい事のように思えますが、
本当にその子のやる気を理解してますか?
というのを考えてもらいたいと思います。
・良かれと思ってやっている
・どちらかというと親がやって欲しい事を求めていた
・やる気になって欲しい事以外の楽しい他の要素が周りに溢れている
・やった後の報酬が何もない
最後の部分は気にかかるかも知れませんが、結構これ重要です。
やったのに何も得られななかった時、むしろやらされ損に感じてしまったら、やる気どころか二度とやってくれなくなります。
報酬は物理的なものだけでなく、先程のボランティアのように、やり甲斐を感じなくてはなりませんね。
まだこの子は理解してないけど、やる事でこの子のためになるんだから、それを報酬として感じたらいいのに、と思ったりもしますが、大人になった今だから言える事で、それを子どもが理解するには、やらなかった事の損失を体験するにはまだ人生そこまで歩んでいないので、その方法は得策ではないでしょう。
ゲームにはまるのは、まさに小さな報酬が沢山ちりばめられていて、やり甲斐を感じているのかもしれません。
勉強をした先に得られるものは、あまりにも時間が長く不確実です。
なので日常においても、ほんのちょっとしたことで自分にとって得だと感じることがあれば、そちらに目を向けるようになるでしょう。
ぜひ工夫を凝らして、やる気に導いてあげてください。
応援くださる方はポチッとよろしく![]()
![]()