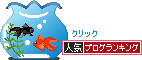若かりし頃、東京で知り合った男友達はほぼ高知出身だった。
一人の高知出身者と知り合うと、その友人と知り合い、次々に
友達の輪は大きくなっていき、通う大学は東大、早稲田、青山、
獨協大と多岐に渡っていたが、やはり地元出身の友人が一番
心許せるらしく、みな高知の幼なじみだったからだ。
その友人たちが高知の有名人として必ず名前を挙げていたのが
坂本龍馬ではなく、漫画家の黒鉄ヒロシ氏であった。
理由はいたって単純で土佐高の大先輩だから。
彼らが嬉しそうに 「 げに黒鉄ヒロシは筋が一本とおっちょおきに 」
と身内のように自慢していたのが、今でも目に浮かぶ。
そして必ず 「 土佐高じゃき 」
わたしは長いあいだ、四国で一番の学校だと思っていた。
その土佐高出身の 黒鉄ヒロシ氏の記事があった。
読んでみると、まっこと一本筋の通った博覧強記の知識人である
ことに恐れ入った。
わが先人たちは、明治維新から日清 ・日露戦争、そして韓国併合
と、シナ ・ 朝鮮との一定の距離を、決して縮めようとはしませんで
した。
その真意は祖先を仰げばわかるはずです。
黒鉄ヒロシ( 漫画家 )
弁解したところで詮無く、また、するつもりもないが、韓国問題を
考える時、日本人はどうやらスタート地点の選択を間違えていた
ように思う。
譬 ( たと ) えは乱暴でも、ここを押さえておかないと、続く後輩達
も我々同様のミスを犯す可能性が残る。
四カ国、つまり、日本、韓国、中国、ロシア、の位置関係と特質を
それぞれ一軒の家として見直してみるところから始めたい。
まず、水の上に一軒の家がある。
日本である。 大和家( やまと )とする。
少し離れたところに今一軒の家がある。
朝鮮である。 金 ( キム ) さんの家。
この一軒は後に二軒に分断されるが、この時点ではまだひとつ
にまとまっている。
更に、今一軒がその先にあって、これが敷地面積の広い、造作
は、ともかくやたらにデカイ家で、意味なく威張って何故か昔から
尊大である。
中国であり、態度の理由は中華思想。
今は漢さんが住んでいるが、昔は 「 清 」 という表札が掛かって
いた。
北の方角に、たとえる最後の一軒がある。
これまた馬鹿デカイ家だが北向きに建てられており、何かにつけ
寒さが付き纏 ( まと ) うので、常に南の方の土地を手に入れたい
と考えている。
もちろんロシアで、イワンの家。
とりあえず、この東アジア、いや、この町内は以上の四軒で成り
立っている。
この四軒がゴチャゴチャと何かと揉めるのは、寒さを動機に最北
の一軒が動くのがもっぱらである。
のちに大和家とイワン家が、一家を挙げての大喧嘩に発展する。
たとえを歴史に直せば日露戦争の原因も同様であった。
たとえ話は、その日露戦争の前、更にその前の日清戦争の辺り
から始まる。
この四軒以外にも 〈 地球町 〉 には当然に他にも家はあって、
漢さんが住みつく前の清 ( しん ) さんの時代に、これを攻めた
ものがある。
イギリスであり、歴史で見れば阿片戦争で、ま、チャーチル家と
しておく。
阿片戦争は二度もあって、あとの方には、ドゴール家( フランス
ですね ) もしゃしゃり出て清さんから多額の賠償金をせしめた。
この時、戦争には加わらなかったが、ルーズベルト家( アメリカ )
この時、戦争には加わらなかったが、ルーズベルト家( アメリカ )
もイワン家もドサクサに紛れて清さんに対し様々な特権と土地の
一部の割譲を認めさせた。
特にヒドイのはチャーチル家で、この海賊のやり口としか思えない
暴挙を知った大和家は大騒ぎとなった。
彼等の手口には法も正義もあったものではない。
圧倒的な武力、もとい、腕力でチャーチル家は清さんを、一方的
にぶん殴り、家財は強奪するワ、土地は分捕るワで、まるで強盗
そのもの。
困惑の余り、大和家内で大揉めに揉めているところへ、ルーズベ
ルト家の使者としてペリーがやってきて、閉め切った雨戸を激しく
叩いて開けろとわめく。
大和家では、当時の家長( 徳川である )が取り替わる事態にまで
発展する。
再出発を決めた大和家では、家訓も単なる大和魂に、和魂洋才を
加え、何んとかチャーチルや、ルーズベルトにぶん殴られる事態
だけは避けることができたが、奇妙な約束だけは押しつけられた。
長く悩むことになる不平等条約である。
清さんも金さんも殴られるだけ殴られて、血だらけでもはや歩行も
困難な有様。
チャーチルに加えてドゴールやハンス( ドイツ )までが見ならって
三軒を狙って遠くから押し寄せる。
あのですね、いちいち律儀に譬えるのも煩雑に過ぎるし、書くべき
ことは他にあって、かといって譬え終わらないと先に進めないので
表記がところどころ継ぎ接ぎになる点はご寛恕 ( かんじょ ) を願う。
チャーチル家、ドゴール家、ハンス家など西欧列強の帝国主義的
なアジア戦略に対して、勝海舟や西郷隆盛は対抗策として、神戸、
対馬、釜山、天津などに海軍の本拠地を置き、日、韓、清の三国
による合従連衡 ( がっしょうれんこう ) を構想するに至る。
チャーチル家、ドゴール家、ハンス家が組んだ白人強盗団に対し、
大和家、金家、清家で対抗せんとのアイデアを提案した訳である。
この三家の合従連衡案は、大和家以外の理解力と能力の不足に
よって頓挫する。
能力に含まれるものかは考えようだが、当時の金家の、大和家に
対する非礼は度が過ぎた。
要は夜郎自大 ( やろうじだい ) にして、世間知らずの田舎者という
ことなのだが、一家の上から下までがそうなのだから特に誇り高き
武士 ( もののふ ) 出身の新たな指導者で占められた大和家では、
耐え難い屈辱として受け取った。
金家の最上位にある大院君からして、大和家が新政府樹立を報せ
る国書を送った際には、この受け取りを拒否するという無礼で応え
ている。
如何に前近代的にして外交に無知とは言え、品無きを通り越した
蛮族の所業である。
上が上なら下も下で、以後金家では根拠もなく
「 大和家は禽獣 ( きんじゅう ) にも劣る 」
として、大和家よりの正式な使節を粗末な小屋に待たせてみたり、
公衆の面前ではずかしめるような高圧的な態度を取り続ける。
かの民族の、いや金家の家風であるか、調子に乗り易いというか、
発想が幼稚なのか、大和家の公館への正当な食料の供給を拒否
してみたり、門前に謂 ( いわ ) れなき侮辱を書き連ねた文書を貼
り出したりと、愚行は止まらない。
現在の慰安婦とやらの像の設置によく似たり。
やはり家風であるか。
そんな折、つまり明治6年(1873 )に、明治新政府内に於いて、
政変が勃発する。
遣欧使節として欧米視察から帰国した、大久保利通、岩倉具視、
伊藤博文、木戸孝允 ( たかよし ) らと、留守政府側の西郷隆盛、
板垣退助、江藤新平、副島種臣らが対立したいわゆる
「 征韓論政変 」 である。
この後に述べる日清戦争同様に、西郷の 「 征韓論 」 を、今も
多くの日本人が誤解したままであるようだ。
朝鮮やシナの本質見抜いた西郷
誤解のもつぱらは、士族の不平不満の解消策としての朝鮮との
開戦であり、そのきっかけとして西郷自らが殺されての口実作り
の二点であり、後者は板垣宛西郷の文面を証拠とするが、強硬
派を諫 ( いさ ) める為の方便であることは明白である。
他の単純な征韓論者の中味と西郷のそれとは性格が異なる。
西郷は既に側近を朝鮮に派遣して情報収集まで行っていた。
その上で 「 本当の文明ならば、未開の国に対しては慈愛を本と
し、開国に導くべきだが、欧米列強は未開蒙昧 ( もうまい ) の国
に対するほど、むごく残忍なことをして自らを利している 」 と西洋
文明の本質を説き、正道、有道 ( ゆうどう ) を踏むべき方向を指
し示し、アジア諸国と結んで、西欧列強に対抗すべきであると、
あの 「 一日会えば一日分惚れられる人 」 と言わしめた西郷が出
向いて説いていれば、いっかな頑陋 ( がんろう ) 不明な朝鮮とい
えども、もしやと思わせるが、大和家に於いては征韓論は容れら
れず西郷達は下野することとなる。
その後の日韓の不幸を避けられたかもしれないひとつのチャンス
はここに失われた。
西郷の正しさは二年後の日本軍艦、雲揚 ( うんよう ) 号を朝鮮が
砲撃した江華島 ( こうかとう ) 事件で証明される。
正当防衛ではあったが、結果としてペリーがやった砲艦外交に、
日本も愚を重ねた。
骨のある抵抗なら続ければ良いと思うが、元より先の嫌がらせ同
様に思い付きの砲撃であったから、掌 (てのひら ) を返すように
日朝修好条規が締結されることになる。
これを知った西郷は、「 天理に於いてまさに恥ずべき 」 と、ペリー
同様の軍事的威嚇は断じて避けるべきであったと叱る。
ここにも西郷の征韓論の本質が覗く。
福沢も 「 大久保らの、かつての征韓論反対は何んであったのか 」
福沢も 「 大久保らの、かつての征韓論反対は何んであったのか 」
と批判した。
朝鮮側は自らが先に砲撃したことには頬被 ( ほおかぶ ) りを決め
込み、砲艦外交をやられた屈辱感だけを忘れないという、今に変わ
らぬ例の癖を見せる。
清家も金家も、やる気が無いどころか、事態の重大さに気付かず、
洋の技術を最短で学習して、対抗せんと焦る大和家を、やれ洋夷
じゃ、それ裏切りよと的外れに罵 ( のの ) しる始末。
清家には〈 華夷 ( かい ) 秩序 〉なる家訓があって、つまり自らは
中華帝国として君臨し、一夷 ( えびす ) ( 蛮族 )とする周辺国は
朝貢し我が保護下にあるべきだと勝手に思い込んでいる。
特に朝鮮は属国と見做 ( みな ) してそのままにして、本来の敵が
西欧列強であるのに日本叩きに出る清家の時代音痴ぶりは如何
んともし難い。
いつまでも属国と見做される金家も金家で、元は清家の庇護の元
にあり、その期間は二千年もの長きにわたっているから、宗主国、
いや、親分のいう事に、つい従いたくなるのは、刷り込まれた下僕
根性という他はない。
ここまでも、たとえは乱れに乱れたが、四つの国の立場を手ばやく
説明する役目は一応終えたとして、ここから通常の表記に戻す。
日清戦争は野蛮に対する文明の義務
ついに、日清戦争が勃発する。
三国で組んで西欧列強に対抗する筈が、組むべき三国の二国が
戦うというのだから、欧米から見ればアジアの同志討ち、内部紛争
の如きに見てとって嗤 ( わら ) った。
嗤われようとも怒るべきときは怒るべきである。
福沢諭吉も怒った。
「 悪友を親しむ者は、共に悪名を免 ( まぬ ) かるべからず。
「 かの頑陋不明なるシナ人の為に戦さを挑まれ、わが日本国民は
自国の栄誉の為、東洋文明の先導者として、これに応ぜざるを得ず 」
と、日清戦争について記す。
福沢の論に内村鑑三も
「 日清間の戦いは、野蛮に対する文明の義務である 」
と筆先を揃 (そろ) えた。
清側の言い分は、属国朝鮮の独立など認めてたまるものかと、あくま
で前近代的で、ついにはヒステリックに軍事力に頼ったものである。
朝鮮に頼まれた訳でもなく、良かれと思った理想の元が、自国の危機
脱出であってみれば、代理戦争の性格についての説明を加えても虚
しい。
日本の誇る英傑、かの西郷までが西南戦争で命を落とした理由が
朝鮮問題と縁浅からずと呟いても、今となってはこれも虚しい。
正道、有道なる理想の道を貫き、西欧による植民地化の怖れはあっ
たとしても、日本一国で立つべきであった。
何故か、西郷も福沢も、隣国二つが、まさかそこまでの腑抜けとは、
知らず判らず、人好しにもつい同じアジアと期待し、仲間と見た。
学習しさえすれば、日本がそうであったように、朝鮮もきっとそうなる
と考えたが、国柄というものを見落とした。
朝鮮にも、金玉均や朴泳孝という西欧列強の横暴に危機感を募らせ
て、日本と結んで近代化を画策した若手改革派が、いない訳ではな
かった。
福沢は自らの慶應義塾に多くの朝鮮人、清国人の留学生を受け入
れたり、先を見越してハングル表記の新聞発刊の為の印刷機を贈っ
たりと、物心両面の援助を惜しまなかったが、清国によって、多くの
進歩派は弾圧され続ける。
およそ世界状勢の変化と、自国に対する危機感に関して当時のこの
二国の理解力はゼロであったと言い切って良い。
朝鮮政府による刺客によって金玉均が暗殺され、その遺体が切り刻
まれて晒 ( さら ) されるという無惨を知るに及んで福沢が書いたのが
『 脱亜論 』 であった。
「 悪友を親しむ者は、共に悪名を免 ( まぬ ) かるべからず。
我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり 」
福沢は因循固陋 ( いんじゅんころう ) なる清国や朝鮮の思考と体質
に協力と努力を重ねた揚句、心底絶望したのである。
両国の本質は今も変わっていないように思うが、どうか。
弱体化の止まらない清国に、さすがに鈍感な朝鮮も気付きはしたが、
彼の国らしいといえばそれ迄だが、奇天烈なアイデアを思い付く。
何んと最大の脅威である筈のロシアに対して、不凍港の租借を代償
に、軍事的保護を求めるというスットコドッコイ振りに、あの清国すら
も慌て、日本は更に驚いた。
日清戦争に至る要因の専らは、そも不凍港を獲得したく思うロシア
の南下政策にあった。
不凍港の次は、朝鮮半島がターゲットになるのは赤児にも判る予測
であろうに、はたして後先を考えずに泣きわめいて、敵の懐ろに飛び
込むというあはれ。
半島がロシアの手に落ちれば、次なる目標は海を挟んだ日本である。
これを危うしと感じたのも、自国の都合よと言われればそれ迄だが、
世界の構図など元は国々の勝手な都合で成り立ってきた。
滅茶苦茶な都合で、朝鮮が他国を危機に陥 ( おとしい ) れるなら、
これを阻止するのもこっちの都合だろう。