22.恋慕の終焉
その瞬間、それまで順当に老人の力を削いでいた金の竜は目を見開いた。
カチ、と、時計の針が時を刻む。
杖をつき、力を削がれ続けたしわがれた老人の手には、骨董品である懐中時計がある。
文字盤をカバーするケースには赤い宝石がはめ込まれており、老人のぼそぼそとした呪文に呼応するように艶やかに瞬く。
秒針が音を立てて左回りに時を遡り始めたとき、老人が築いた結界の中のすべてのものは時を逆行し始めた。ただひとつ、竜を除いて。
少女も、青年も、もちろん、老人自身も。目まぐるしい速度で回転する針が辿るままに時を遡り、少女と青年は産まれる前へと還り、老人は老人でなくなっていた。
『これは……』
思わずそうこぼした金色の竜の前には、いつかの男が立っている。
先ほどまで老人だった男は、五十年逆行した時の、齢三十前後の姿でそこに立っていた。
竜が男と出会ったのもこのくらいの年齢であったが、あの頃と違うのは、その顔に浮かぶのが邪悪そのものの笑みであること。
男が全身全霊をかけて竜を呪った日。竜にとっても、男にとっても忘れ難いあの日に、すべてが還ったのだ。
男は感慨深く自分の腕を持ち上げた。今この時は無用となった杖を手放したその手に黒い炎が宿る。今では燃え尽きたかつての灯火も、全盛期の男には扱うことができた。
竜はかつて、あの炎に焼かれた。
あの黒炎はこの世の地獄そのものだ。その苦痛を、冷たさを、竜は憶えている。その炎に込められた叫び声も。
あの炎は、奈落だ。
「長年かけて編み出したよ。お前は弱ったまま、私はあの頃と同じように力を振るうことができる術だ」
『……そこまで、準備をしていましたか』
「そうとも。お前のため捧げた五十年だった」
五十年忘れられることのなかった男の想いは最悪の形で実った。
竜は束の間自分の考えの浅さを思った。男の執念を測り違えていたことを思った。
このまま順当に力を削ればあるいは…。それは思い違いだった。
竜は弱った現在のまま、結界内の他のすべてのものが五十年の時を遡る。自分が若返る。そうすれば今の弱った竜を手に入れることは可能だろうと男は見ていた。すべては男の目論見通りだった。その執念は形になった。
できればこの術を温存したままにしたかったが仕方がない。あとはこの魔術の効力が切れる前に竜を仕留めるだけだ。
かつては並ぶ者がいないほどの才能に溢れていた男は、魔術師として誰からも一目置かれるような、そんな存在だった。
しかし、天才は現状で満足などはせず、人間の器に限界を感じ、自分よりも優れた存在を探し求めた。
そうして出会った金色の竜は、男にとって己のなりたい姿そのものであった。
その美しい金色から溢れる気品に見惚れ、何者にも縛られないその在り方に憧れた男は、しかし、足元から這い寄る己の影に気付かなかった。
最初は竜という存在への憧れから始まった男の想いは日ごとに大きくなり、膨らみすぎて、その煌めきは欲望という泥に落ちた。
男は竜に惚れていた。その存在に心を奪われていた。
竜になりたい。そう思った。竜で在りたい。そう願った。
竜になれないのならせめて、竜を手に入れたい。手元に置きたい。その存在に認められたい。
重すぎた願いは埋もれ埋もれて、眩しかったモノは泥にまみれた。泥の底の闇に染まった。
憧れるものが手に入らない焦燥。
己がソレになることはないという絶望。
どんな魔術を披露しても、竜の意識にはかすりもしない。
どうやっても竜には届かないという現実が、天才故に挫折を知らなかった男のすべてを叩きのめした。
男が一人の人間として金色の竜に想いを吐露したその日。
応えない竜に、男は、刃を向ける。
応えないのなら、手に入らないのなら、いっそのこと壊してやろうと、天才と呼ばれていた魔術師は全身全霊をかけて竜と対峙し、その身を滅ぼす呪いをかけることに成功する……。

金色の竜は、凪いだ瞳で目前の男を見つめた。己を黒き炎で焼き尽くさんとしている男のことを眺めた。
竜故に長い寿命を約束されて生きてきた彼女には、目前に迫る死を忌避する心はなかった。来るべき時が来た。竜はただそう納得した。
だが、ふと。ふと、目の前に懐かしい皺だらけの顔が浮かんだ。ノアの祖父だ。カウンターでコーヒーを淹れている。…その香ばしさが鼻腔をくすぐる。
皺だらけの見慣れた顔は、凹凸がない黒髪の青年の顔へと変わっていく。…ノアだ。今日もコーヒーを淹れている。不器用な笑顔を浮かべて白いカップをこちらへと差し出している。
ああ、彼が淹れたコーヒーが飲みたい。
竜はふとそんなことを思う。あの、苦くて、最初は毒みたいだと思った茶色い飲み物を、もう一度飲みたい。ふとそんなことを思ってしまう。
受け入れていた死に対する拒絶の心が生まれる。
(私は、まだ)
まだ、死を、受け入れることは、できない。
しかし、竜の想いも虚しく、男の手にある黒い炎は竜を焼いた。容赦はなかった。情けもなかった。冷たい黒い火は金色の竜を呑み込んだ。
焼かれる痛みは氷で刺し貫かれるよりも鋭く冷たい。
金色の抗う光はすぐに小さくなり、竜の長き生にピリオドが打たれる……。竜も、男も、そう思っていた。
『それじゃあ困るんだよ』
あるはずのない第三者の声がするまでは。
男が反射的に黒い炎を向けた先にあったのは、漆黒。暗闇そのもの。男が操る昏い炎よりも一段と黒く、見通せない人型の闇がゆらゆらと揺れている。
その闇は男の炎を余すところなく吸収した。竜を焼いていた炎も残らず吸い込んだ。「…馬鹿な」竜でさえ焼くことができる炎が通じない何かに思わずたじろぐ男と、皮一枚で命を繋いだ竜が地面に落ちる。
かつての天才が、考えられるすべての方法でもって漆黒を退けようとするが、黒い何かは男のすべての術を呑み込んだ。『おいしいなぁ。甘いキャンディのデザートだ』と声だけで嗤いながら。
ゆらゆらと近づく漆黒を、男は遠ざけることができない。
闇が這い寄ってくる。この五十年間で従えたどの闇とも違う、それは耐え難い寒気を引き連れてゆらりゆらりとやってくる。
『ほら、ほら、どうした? 天才。そう呼ばれていたんだろう?
才能の方向を間違えて、かわいそうになぁ』
魔法陣を本来の目的通り結界として発動させた男は束の間冷静になるが、しかし、ゆらゆらと伸びた漆黒が薄氷を割るように結界を破壊したのを見て目を剥いた。
確かに即席の結界だ。だが、死霊や悪魔からの防衛にこれほど適したものはないというのに。
『人に惹かれず、竜に惹かれた孤独な男。お前の五十年の恋慕もここで尽きる』
男は、迫る漆黒を前に覚悟を決めた。
五十年かけて竜を葬る。願いが叶ったそのあとは心穏やかに暮らそうと思っていた。
だが、そんな贅沢は望めまい。
竜を屠り、自分も尽きる。そうなる運命なら、血術を用いることにも抵抗はない。
この肉体にはどうということはない負荷も、いずれ戻った時間にある老いた体では、血術の負担は相当なものとなるだろう。最悪死もありうる。
(何をためらうことがあるのか。このために生きてきた)
自らの腕を切り落とし、噴き出す血のすべてを武器とし、用いれる限りの強力な武器、己の肉体でもって漆黒を切り裂こうとした男は、そこに、大きく開いた口を見た。それはまるで巨人の口のようにも見えるし、空中にぽっかりと出現した地獄への入り口のようにも見えた。
男が手にした血色の剣も、血の弾丸も、槍も、斧も、すべて等しく大きな黒い口に吸い込まれて消える。
ガリ、ゴリ、バリ。咀嚼する音を響かせながら、漆黒は収束して人型の形に戻っていく。
かつては天才と呼ばれ、竜に焦がれた男は、こうして尽きた。
『報われない恋だったな。甘くてほろ苦い、おいしいキャンディだったよ』
漆黒は顔だろう部分で弱って動けない竜を見下ろした。『生きてる?』『………』『ああ、お前には興味はないよ。どうせつまらない味しかしない』手、と思われる部分をゆらゆらさせる漆黒が懐中時計を噛み砕いたことで、この場を覆っていた黒い結界が砕け、敷かれていた魔法陣が弾け飛んだ。空を覆っていた黒い魔術もぐずぐずと崩れ始め、少女と青年が無から産まれて急速に成長し、あるべき姿に戻っていく。
降り注ぐ黒い破片の中で、漆黒はすぅっと薄くなり、言葉もなく倒れた。
霞む視界で、竜は彼を見る。
漆黒を纏っていたノア・ステュアート・オブ・ダーンリーは、日本人の色を濃く継いだ見知った姿でそこに倒れている。
22話めです! 先月更新忘れてました…書き溜めていたのに。。
何を言ってもネタバレ的な感じになっちゃうのでとくにあとがきありません(
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
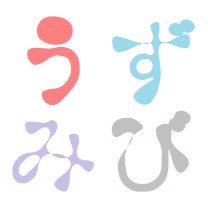






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません