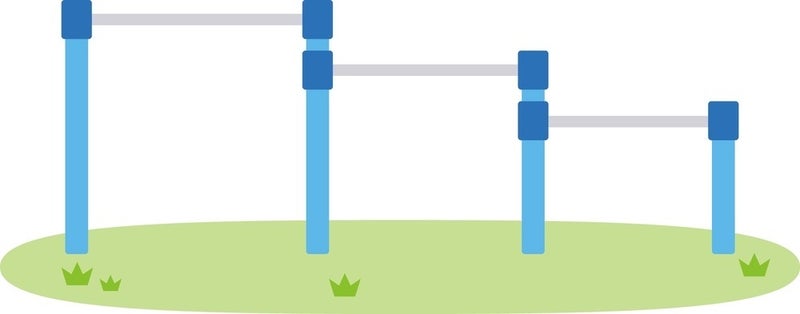こんにちは。
本日もお越しくださってありがとうございます
今回は、以前に引き続き、僕の書いた物語を紹介したいと思います
「刻(とき)のエンピツと木の精ポチカ」といいます。
読み聞かせをしていただくには長めの作品になるかと思いますが、
お子様も読みやすいように考えて書いています☆
もしよろしければ、ぜひお読みになってみてくださいね(^^♪
それでは、始まります~
↓↓↓
刻のエンピツと木の精ポチカ
もちろんガンバりたいけれど、集中できなくて、消しゴムや定規で自分だけの机上バトルをやるのがいちばん楽しいんだ。
この端っこの欠けたにおい消しゴムは重たいから、陣地の入り口にセットしよう。
三角定規は攻撃の要。とがった角でやわらかい消しゴムを迎え撃つ。
「台形の面積の求め方は、ね、ここにまっすぐ線を引けば、三角形がふたつだから」
ミユ先生がいつものように算数を教えてくれている。先生の指先はチョークの粉で白やピンクになっていて、カツカツカツと黒板から音が響く。
真琴は前の生徒の背中でちょうど手元が見えないようにして、消しゴムや定規を設置し終えてから、教室を見わたした。
熱心に先生の話を聴いている子もいれば、ひじをついてウトウトしている子もいる。体育の次の授業だから、体操着から着替えないまま半ズボンで脚をぶらぶらさせている子もいる。
ほとんど全開にしてある窓から、そっと風が吹き込む午後の時間だ。
外に目をやれば、ぼんやりした白い雲がいくつか青い空にただよって、太陽の光を集めているみたい。
「ねえ」
何とはなしに空と雲とを眺めたまま、音楽が聞こえるような心地でいると、真琴は背中をつつかれるのを感じた。
「ん」
ときどき授業中にちょっかいを出してくるので、真琴は先生にばれないようにうまく応答することにしている。
ほんの少しだけ、首を斜め後ろにかしげるように動かすんだ。これで山田には真琴が反応したことが伝わる。
「これ」
山田は真琴の肩越しに、ノートの切れ端を差し出した。真琴が反対側の手でさりげなく受け取ると、そこには「放課後、鉄棒で」とだけ丸い字で書かれていた。
真琴はまた首をかしげて、オーケーの合図をした。それから、まず三角定規の攻撃。相手陣地の小さくなった消しゴムを弾き飛ばす。
三角定規の力が強すぎたのか、消しゴムは真琴の机から落っこちて、前の席のほう、黒板のほうへ転がっていってしまった。残念だけど、おまえのことは忘れないよ。
「真琴くん、消しゴムが落ちたよ」
教科書を読み上げていたミユ先生が、ピタリと中断していった。
「はい、あり、がとうございます」
予想外だったので真琴は慌てて椅子から立って、みんなの視線を浴びながら消しゴムを拾った。ミユ先生はそれ以上何もいわなかったけれど、その目はきらりと光っているようだった。
授業が終わると、後ろの山田はさっさと教科書や筆箱、体操着などをランドセルに詰めこんで、真琴の顔を見もせず教室を出ていった。
「真琴、野球行こうぜ」
「いや、今日だめ、ちょっと用事あって」
同級生の何人かは、よく近くの公園で野球をしている。真琴も加わったり、そうでなかったりしているのだ。
「そっか、じゃあまたな」
「真琴くん」
真琴もランドセルの準備をしようとすると、入れ替わりでミユ先生がそばへやってきた。先生のワイシャツの胸ポケットには、いつものように青と赤のサインペンが差さっていた。
「最近、あんまり勉強に身が入っていないみたいですね。どうかしたのかな。何かつらいことあった」
ミユ先生は笑顔でいった。さっき真琴が机上バトルをしていたのにもおそらく気づいていたから、わざとこういう訊き方をしてくれたのだろう。
真琴もこれといってつらいことはないので、「ないです」とだけ答えると、
「あのね、真琴くん、やりたくないのは分かるけど、今やっているところ、すごく大事なんだよ」
諭すような口調で、先生はつづけた。真琴も帰る準備の手を止めて、素直に耳をかたむける。
「これからもっと難しくなるし、その土台として今の部分が必要になるし」
「はい」
勉強をしたくないわけではないけれど、どうにも取り組めなくて、真琴も困っているところなのだ。でも、自分でもどうしてなのか分からない。
真琴はだんだんとうつむき加減になった。
「先生ね、真琴くんはすごくできる子だと思うんだ。だから応援したくなる」
他の生徒たちはばらばらと教室を出ていって、残っているのはミユ先生と真琴、あと数人がところどころでかたまっておしゃべりしているくらいだ。
校庭からは放課後の遊びを始めたみんなの歓声が聞こえる。
「どこかつまづいたりしても、真琴くんならすぐに取り戻せるよ。先生も協力するから、悩みごととか、分からないこととか、あったらすぐにいってね」
ミユ先生はさらに笑顔でいった。これまでにも何度か同じ話をされているけれど、真琴としてはつまづいている感じもしないので、応答が難しい。
真琴は「はい、ありがとうございます」と返事をして、机の中に忘れ物がないか確認すると、ランドセルをかついだ。
「さようなら」
「うん、さようなら、気をつけてね」
先生が見送ってくれる視線を背中に受けながら、真琴は教室を出た。
***
大きな木の内側で、身体を丸めて眠っている。
これまでもそこにあり、これからも長く長くそこにあるもの。
かすかに聞こえてくるだけで、明らかではないのかな。
じかに触れることを求めても、叶うことはないのかな。
見てみたい。感じてみたい。
「ポチカ、ポチカ」
聴くことはできないのに、呼びかける声がする。だれ。
ずっと眠っているから、確かめることもできない。身体を動かすことができるのかどうかも、分からない。
水分がみたされていること、しなやかに密度をもった場所。ゆっくりゆっくりと流れている。
木の中は豊かで、刻にあふれている。ポチカは全身でそれを感じて、溶けあって、おぼろげなまま過ごすのだ。
そうあるものとしてだけ存在してきたから、自分の姿かたちさえも定かではなくて、けれど、そこにポチカはいる。
「ポチカ、ポチカ」
***
ミユ先生につかまっていたので、山田との約束に遅れている気がして、真琴は急いで校庭へ向かった。
階段を一段飛ばしで駆け下りたら、昇降口で上履きを自分の靴箱に投げ入れ、外履きに足をつっこんだ。正面玄関を出て、右手に、校舎の裏側へまわると校庭だ。
途中、植えてある木が明るい緑色の葉をつけているのが見えた。ちらちらと葉が風にゆれて、水をまいたばかりらしい花壇から来る土の香りと混ざりあっている。
校庭に出てみると、みんなが思い思いに遊んでいた。
サッカーや野球をしていたり、名前のついていない遊びを作り出していたり、どこかでは小さなケンカの声もする。
生徒たちが蹴り上げる砂ぼこりが舞う中、真琴は校庭の端の鉄棒のところへ到着した。
この端っこの欠けたにおい消しゴムは重たいから、陣地の入り口にセットしよう。
三角定規は攻撃の要。とがった角でやわらかい消しゴムを迎え撃つ。
「台形の面積の求め方は、ね、ここにまっすぐ線を引けば、三角形がふたつだから」
ミユ先生がいつものように算数を教えてくれている。先生の指先はチョークの粉で白やピンクになっていて、カツカツカツと黒板から音が響く。
真琴は前の生徒の背中でちょうど手元が見えないようにして、消しゴムや定規を設置し終えてから、教室を見わたした。
熱心に先生の話を聴いている子もいれば、ひじをついてウトウトしている子もいる。体育の次の授業だから、体操着から着替えないまま半ズボンで脚をぶらぶらさせている子もいる。
ほとんど全開にしてある窓から、そっと風が吹き込む午後の時間だ。
外に目をやれば、ぼんやりした白い雲がいくつか青い空にただよって、太陽の光を集めているみたい。
「ねえ」
何とはなしに空と雲とを眺めたまま、音楽が聞こえるような心地でいると、真琴は背中をつつかれるのを感じた。
「ん」
ときどき授業中にちょっかいを出してくるので、真琴は先生にばれないようにうまく応答することにしている。
ほんの少しだけ、首を斜め後ろにかしげるように動かすんだ。これで山田には真琴が反応したことが伝わる。
「これ」
山田は真琴の肩越しに、ノートの切れ端を差し出した。真琴が反対側の手でさりげなく受け取ると、そこには「放課後、鉄棒で」とだけ丸い字で書かれていた。
真琴はまた首をかしげて、オーケーの合図をした。それから、まず三角定規の攻撃。相手陣地の小さくなった消しゴムを弾き飛ばす。
三角定規の力が強すぎたのか、消しゴムは真琴の机から落っこちて、前の席のほう、黒板のほうへ転がっていってしまった。残念だけど、おまえのことは忘れないよ。
「真琴くん、消しゴムが落ちたよ」
教科書を読み上げていたミユ先生が、ピタリと中断していった。
「はい、あり、がとうございます」
予想外だったので真琴は慌てて椅子から立って、みんなの視線を浴びながら消しゴムを拾った。ミユ先生はそれ以上何もいわなかったけれど、その目はきらりと光っているようだった。
授業が終わると、後ろの山田はさっさと教科書や筆箱、体操着などをランドセルに詰めこんで、真琴の顔を見もせず教室を出ていった。
「真琴、野球行こうぜ」
「いや、今日だめ、ちょっと用事あって」
同級生の何人かは、よく近くの公園で野球をしている。真琴も加わったり、そうでなかったりしているのだ。
「そっか、じゃあまたな」
「真琴くん」
真琴もランドセルの準備をしようとすると、入れ替わりでミユ先生がそばへやってきた。先生のワイシャツの胸ポケットには、いつものように青と赤のサインペンが差さっていた。
「最近、あんまり勉強に身が入っていないみたいですね。どうかしたのかな。何かつらいことあった」
ミユ先生は笑顔でいった。さっき真琴が机上バトルをしていたのにもおそらく気づいていたから、わざとこういう訊き方をしてくれたのだろう。
真琴もこれといってつらいことはないので、「ないです」とだけ答えると、
「あのね、真琴くん、やりたくないのは分かるけど、今やっているところ、すごく大事なんだよ」
諭すような口調で、先生はつづけた。真琴も帰る準備の手を止めて、素直に耳をかたむける。
「これからもっと難しくなるし、その土台として今の部分が必要になるし」
「はい」
勉強をしたくないわけではないけれど、どうにも取り組めなくて、真琴も困っているところなのだ。でも、自分でもどうしてなのか分からない。
真琴はだんだんとうつむき加減になった。
「先生ね、真琴くんはすごくできる子だと思うんだ。だから応援したくなる」
他の生徒たちはばらばらと教室を出ていって、残っているのはミユ先生と真琴、あと数人がところどころでかたまっておしゃべりしているくらいだ。
校庭からは放課後の遊びを始めたみんなの歓声が聞こえる。
「どこかつまづいたりしても、真琴くんならすぐに取り戻せるよ。先生も協力するから、悩みごととか、分からないこととか、あったらすぐにいってね」
ミユ先生はさらに笑顔でいった。これまでにも何度か同じ話をされているけれど、真琴としてはつまづいている感じもしないので、応答が難しい。
真琴は「はい、ありがとうございます」と返事をして、机の中に忘れ物がないか確認すると、ランドセルをかついだ。
「さようなら」
「うん、さようなら、気をつけてね」
先生が見送ってくれる視線を背中に受けながら、真琴は教室を出た。
***
大きな木の内側で、身体を丸めて眠っている。
これまでもそこにあり、これからも長く長くそこにあるもの。
かすかに聞こえてくるだけで、明らかではないのかな。
じかに触れることを求めても、叶うことはないのかな。
見てみたい。感じてみたい。
「ポチカ、ポチカ」
聴くことはできないのに、呼びかける声がする。だれ。
ずっと眠っているから、確かめることもできない。身体を動かすことができるのかどうかも、分からない。
水分がみたされていること、しなやかに密度をもった場所。ゆっくりゆっくりと流れている。
木の中は豊かで、刻にあふれている。ポチカは全身でそれを感じて、溶けあって、おぼろげなまま過ごすのだ。
そうあるものとしてだけ存在してきたから、自分の姿かたちさえも定かではなくて、けれど、そこにポチカはいる。
「ポチカ、ポチカ」
***
ミユ先生につかまっていたので、山田との約束に遅れている気がして、真琴は急いで校庭へ向かった。
階段を一段飛ばしで駆け下りたら、昇降口で上履きを自分の靴箱に投げ入れ、外履きに足をつっこんだ。正面玄関を出て、右手に、校舎の裏側へまわると校庭だ。
途中、植えてある木が明るい緑色の葉をつけているのが見えた。ちらちらと葉が風にゆれて、水をまいたばかりらしい花壇から来る土の香りと混ざりあっている。
校庭に出てみると、みんなが思い思いに遊んでいた。
サッカーや野球をしていたり、名前のついていない遊びを作り出していたり、どこかでは小さなケンカの声もする。
生徒たちが蹴り上げる砂ぼこりが舞う中、真琴は校庭の端の鉄棒のところへ到着した。
「やっと来た」
大きな声ではないけれど、真琴は山田の言葉を聴きとることができた。
山田はどちらかといえば活発な女子なのに、いつも声が小さいのだ。
「ミユ先生」
「ああ、ミユちゃんか」
鉄棒に寄りかかりながら、よくあることだという顔をして、山田はすぐ本題に入った。
「こないだいってたあれ、どう」
「なかなか見つからない、家の庭とか公園とか、いろいろ掘ってみてるんだけど」
「きっとあるはずなんだ」
山田の声が少し高くなった。何があるのかは定かではないけれど、山田の頭の中ではしっかりと存在するらしい。
「もっと特徴とか教えてくれよ」
真琴は自分がこの活動に駆り出されていることに疑問も感じているが、それでも参加してしまっていることにも謎な気分だった。もちろん山田のことが好きというわけでもない。
校庭から楽しそうに遊ぶ声が響いてくる。山田がちょっと必死な様子なのも相まって、ここは場違いなくらい深刻な空気を作り出している気がする。
「特徴っていわれても」
山田はあごに手を当てて空を見上げたあと、つぶやいた。
「エンピツの形。エンピツだから」
「こないだは木の枝っていってたじゃん」
真琴は困ってしまった。
「それは、枝のはずだから」
話が右左に行っているようにも思えたけれど、真琴はそれ以上いわず、「土に埋まってるのかなあ」とだけ感想を述べた。
山田は痛いところを突かれたようで、「んん」といってしばらくの間口を閉じていた。
「でも、そういうものなんだと思う。不思議なものなんだもん」
「なんでそれ探してるの」
一緒にこの「エンピツ」を探し始めてもう一か月ほどになる。でも、真琴はどうして山田がそんなに求めているのか知らなかった。
山田は一瞬赤くなって、くるりと真琴に背を向けて鉄棒につかまった。腕を伸ばしては曲げて、身体を前後させている。
「言いたくないー」
「ええ、けど、それだとおれもなんか」
理由も分からず使われているのも、真琴は不満といえば不満だ。家に帰れば遊びたいゲームもあるし、読みたいマンガもある。案外、本も読む。
「どうしようもないなんて、いいたくない」
「そこまではいわないけどさ」
すぐ悲しそうな顔になるのも山田の特徴で、そのせいで真琴も何となく協力してあげたくなってしまうのかもしれない。
山田との集まりでは、この「エンピツ」のこと以外ではあまり話すことがない。今日のように放課後に会うことが多いけれど、一緒に帰ることもない。
でも、なぜだか真琴も山田が探しているものに興味をそそられてきているのは確かだ。土に埋まっているエンピツって何だろう。
「今日もういいの」
山田が何もいわないので、真琴は手持ちぶさたになって、ランドセルの肩ベルトを手でいじりながらたずねた。
向こうで同じクラスの男子がボールを投げているのが見える。
「次、どうする」
鉄棒を揺らすのを止め、山田がいった。
「そうだなあ、やっぱりもうちょい、いろんなとこ掘ってみるのでいいんじゃない」
大きな声ではないけれど、真琴は山田の言葉を聴きとることができた。
山田はどちらかといえば活発な女子なのに、いつも声が小さいのだ。
「ミユ先生」
「ああ、ミユちゃんか」
鉄棒に寄りかかりながら、よくあることだという顔をして、山田はすぐ本題に入った。
「こないだいってたあれ、どう」
「なかなか見つからない、家の庭とか公園とか、いろいろ掘ってみてるんだけど」
「きっとあるはずなんだ」
山田の声が少し高くなった。何があるのかは定かではないけれど、山田の頭の中ではしっかりと存在するらしい。
「もっと特徴とか教えてくれよ」
真琴は自分がこの活動に駆り出されていることに疑問も感じているが、それでも参加してしまっていることにも謎な気分だった。もちろん山田のことが好きというわけでもない。
校庭から楽しそうに遊ぶ声が響いてくる。山田がちょっと必死な様子なのも相まって、ここは場違いなくらい深刻な空気を作り出している気がする。
「特徴っていわれても」
山田はあごに手を当てて空を見上げたあと、つぶやいた。
「エンピツの形。エンピツだから」
「こないだは木の枝っていってたじゃん」
真琴は困ってしまった。
「それは、枝のはずだから」
話が右左に行っているようにも思えたけれど、真琴はそれ以上いわず、「土に埋まってるのかなあ」とだけ感想を述べた。
山田は痛いところを突かれたようで、「んん」といってしばらくの間口を閉じていた。
「でも、そういうものなんだと思う。不思議なものなんだもん」
「なんでそれ探してるの」
一緒にこの「エンピツ」を探し始めてもう一か月ほどになる。でも、真琴はどうして山田がそんなに求めているのか知らなかった。
山田は一瞬赤くなって、くるりと真琴に背を向けて鉄棒につかまった。腕を伸ばしては曲げて、身体を前後させている。
「言いたくないー」
「ええ、けど、それだとおれもなんか」
理由も分からず使われているのも、真琴は不満といえば不満だ。家に帰れば遊びたいゲームもあるし、読みたいマンガもある。案外、本も読む。
「どうしようもないなんて、いいたくない」
「そこまではいわないけどさ」
すぐ悲しそうな顔になるのも山田の特徴で、そのせいで真琴も何となく協力してあげたくなってしまうのかもしれない。
山田との集まりでは、この「エンピツ」のこと以外ではあまり話すことがない。今日のように放課後に会うことが多いけれど、一緒に帰ることもない。
でも、なぜだか真琴も山田が探しているものに興味をそそられてきているのは確かだ。土に埋まっているエンピツって何だろう。
「今日もういいの」
山田が何もいわないので、真琴は手持ちぶさたになって、ランドセルの肩ベルトを手でいじりながらたずねた。
向こうで同じクラスの男子がボールを投げているのが見える。
「次、どうする」
鉄棒を揺らすのを止め、山田がいった。
「そうだなあ、やっぱりもうちょい、いろんなとこ掘ってみるのでいいんじゃない」