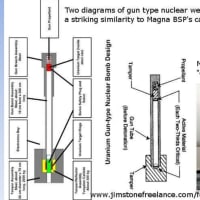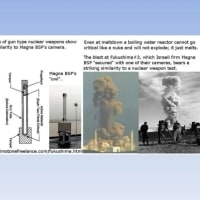この映画は日伊合作で、You tubeで見直してみると、舞台はフランスの有名な観光地でもあるモン・サンミッシェルやパリ。
背景の海や海岸、海岸に建つ小さな古城のような別荘やパリのオテル、エッフェル塔やセーヌ河など、映画全般が柔らかな美しい絵になっており、例えば海岸の風景を360度カメラをゆっくりと回して撮影するなど、観ていて(今どきの映画と違い)視覚的に非常にのんびりとしています。
物語りは、病院の診察室前の待合室でくたびれた中年男性の音楽家のリチャード(リチャード・ジョンソン)とボーイッシュでチャーミングな若い女の子ステラ(パメラ・ヴィロレージ)という親子ほども年のはなれた男女のふとした出会いから始まります。
物語りは、病院の診察室前の待合室でくたびれた中年男性の音楽家のリチャード(リチャード・ジョンソン)とボーイッシュでチャーミングな若い女の子ステラ(パメラ・ヴィロレージ)という親子ほども年のはなれた男女のふとした出会いから始まります。
映画の中で終始流れているBGMは有名な曲で、何処かで聴いたことがあると思われる方も多いのではないでしょうか。
上映当時、親友と二人で映画館で観ていた子供の私は、字幕スーパーについて行けずに、暗く沈み込んだ中年男性と、薔薇色の頬をしている美しい女の子の姿を対比して、冒頭のところで、診察室の中で医師から余命宣告をうけている中年男の方が病に冒されているものだとばかり思い込み、しばらく観ているうちに「逆だと気づいた」という記憶があります。
ややこしいのですが、リチャードが医師から「余命宣告」を告げられていたのは、付き添いの近親者のいないステラが、そのとき待合室にいたリチャードを適当に自分の父親だと口でまかせに言ったためで、医師はリチャードをステラの父親だと思いこみ、赤の他人にステラの病状説明をしてしまったということなのでした。
上映当時、親友と二人で映画館で観ていた子供の私は、字幕スーパーについて行けずに、暗く沈み込んだ中年男性と、薔薇色の頬をしている美しい女の子の姿を対比して、冒頭のところで、診察室の中で医師から余命宣告をうけている中年男の方が病に冒されているものだとばかり思い込み、しばらく観ているうちに「逆だと気づいた」という記憶があります。
ややこしいのですが、リチャードが医師から「余命宣告」を告げられていたのは、付き添いの近親者のいないステラが、そのとき待合室にいたリチャードを適当に自分の父親だと口でまかせに言ったためで、医師はリチャードをステラの父親だと思いこみ、赤の他人にステラの病状説明をしてしまったということなのでした。
つまり、深刻な病に侵されているのはステラの方で、リチャードはたんなる風邪か何かでたまたま病院に来ていただけ。
白血病に冒されているステラ本人もうすうす自分の余命を悟っており、残された時間の中で、生き別れになった実の父親を捜し出すものの、父親には既に再婚相手との間に設けた子供のいる家庭があり、ステラは窓の外からみつめるだけで再会も果たせず、父への「届かぬ想い」を目の前にいる親子ほど年のはなれた男性であるリチャードに向けることで、甘えられる対象としてステラが相手に引き寄せられて行く様子が描かれています。
一方、作曲家としてのリチャードは元々偏屈で他人との関りをなるべく最小限度にとどめるといった人物のようですが、ステラへの同情心や保護者的な立場から二人が男女の関係に発展していくことで、孤独な者同士、相手がかけがえのない、大切な存在となって行きます。
作曲や演奏家としてのピアノレッスンに没頭するリチャードと、次第に病魔に冒され衰えていくことで「足手まといになるまい」とするステラの心理描写が丁寧に描かれています。
「白血病」であっても、骨髄移植や化学療法などの医療を受けず、ごく普通の生活を送り(化学療法の副作用で髪が抜けてしまうでもなく、)つまり、まさしく「ナチュラルコース」でステラは「潔く」死を迎えるわけです。
最後はリチャードがステラの為にコンサートで自ら作曲した曲をピアノで弾いている姿を、ステージの袖で「白い花嫁衣装」を着たステラが、リチャードの音楽家としての再起をかけたコンサートの成功を祈りつつ息をひきとる、という定番のラスト。
作曲や演奏家としてのピアノレッスンに没頭するリチャードと、次第に病魔に冒され衰えていくことで「足手まといになるまい」とするステラの心理描写が丁寧に描かれています。
「白血病」であっても、骨髄移植や化学療法などの医療を受けず、ごく普通の生活を送り(化学療法の副作用で髪が抜けてしまうでもなく、)つまり、まさしく「ナチュラルコース」でステラは「潔く」死を迎えるわけです。
最後はリチャードがステラの為にコンサートで自ら作曲した曲をピアノで弾いている姿を、ステージの袖で「白い花嫁衣装」を着たステラが、リチャードの音楽家としての再起をかけたコンサートの成功を祈りつつ息をひきとる、という定番のラスト。
決して湿っぽくならずに気持ちよく、納得の涙を流せる映画だったように記憶しております。
「死」に抗うことなく、このくらいナチュラルコースだと、ある意味「潔く」もあり、好きなように最期を過ごせるのだということなのかもしれませんが、若い癌患者など、本人の意志はともかく、日本ではこのような「ナチュラルコース」は特に若い癌患者では殆どあり得ないようです。
「死」はなるべく先に引き延ばすべきもの、特に若い命が奪われることは悲劇であるという固定観念。果たしてそうでしょうか。
因みに原題のDedicato a una stellaはイタリア語で「星に捧げられた(ピアノ協奏曲)」で、この場合の星は僅かの時間を共にすごして燃え尽きるステラを流れ星に例えているようです。
(ラストコンサート 日伊合作 1976 ルイジ・͡コッティ監督、パメラ・ヴィロレージ、リチャード・ジョンソン)