出版社は、Adamsmediaです。
================
「運命の人を探して」
by 魔法のネコ。
================
天野さくら、年齢65歳。年金と蓄えで生計を立てている。
仕事はフリーランサーの小説家だ。趣味は
新聞の告知欄を読むこと。決して、
贅沢は出来ないが、毎日幸せな日々だった。彼女の日課は電車
で都内まで出かけること、その日は11月の中旬、
冬の匂いを感じるころだった。東武東上線に乗っていた電車は
ゆるやかに坂戸の駅に到着しようとしていた。
いつものように日課の池袋との往復をしていたころ、
彼女は新聞を読んでいた。
昔からさくらは日課は新聞の告知欄を見るのが趣味だった。
なぜ告知欄を見るのが好きなのだろうか。さくらは小学校の
頃から人の生活に首をつっこむのが好きだった。
「人生は小説より奇なり」これがさくらの母の口癖だった。
さくらは結婚して30年、素敵な夫もいるし、それなりに平和な人生を送っていた。さくらは広告を見ながら、いつもロマンチックな出来事を探していた。
告知欄というのは不思議なドラマがある。
人探しの欄が特に好きなのだ。あれを見ながら、この人はどんな想いで人を探しいるのか、ドラマを感じずにはいられない。そこで想像を広げるのだ。
その日も同じように告知欄を眺めていた。
「あ、これ面白い」とさくらは思わず口に出してしまった。
「これ本当なのかしら?」頭にかけた老眼鏡を思わず書け直した。
告知にはこう書いてあった。
「みほさん、あなたは私を覚えていますか?昭和39年に夏に一緒に
日光で行われたボーイスカウトのキャンプに参加しました。
私はあなたを忘れた時は一時もありません。どうか
お電話いただけないでしょうか?たかし。」
そこにはちゃんと電話番号を書いてある。
「これって本当なのかしらね」さくらは、改めてつぶやいた。
その日の夜、家に帰っても、あの告知のことが気になって仕方がない。
告知って結構お金もかかるのよね。
ふざけて冗談のためにわざわざ新聞にのせて告知するかしら?
翌日、さくらはどうしても気になったので、勇気を出して
告知の電話番号にかけた。
電話口の相手のトーンを聞いた時に、それがすべて悪ふざけでは
ないことが分かった。
その瞬間、この電話をかけた自分の疑いの気持ちに悔やんださくら
だった。
そして、次に考えたのは、
この電話によって、たかしさんが、間違えた期待を
抱いてしまうのではないかと考えたのだ。
さくらは電話口でこう言った。
「も、もしもし、私はあなたがお探しの「みほさん」では
ありません。すみません、どうしても告知の内容が気になって。
どういう経緯でお探しなのか差し支えなければ教えていただければと思って」
男性は紳士的な話口調で、快く応じてくれた。
さくらも、ほっとした気持ちだった。
「ええ、いいですよ。昭和39年、私は17歳でした。
私とみほさんは同じキャンプに参加しました。二人とも
リーダーになってお互いに助けあい、愛し合いました。
これこそ人生に一度の出会いと感じました。
みほさんに結婚を申し込んだのですが、相手方のご両親に
反対をされました。当時は彼女も17歳だったので、まだ若い
と判断されたようです。相手側の両親は私からみほさんを
離すために、海外に転校させてしまったのです。
そして彼女はアメリカで他の男性と出会い、結婚してしまいました。
私の心も身も引き裂かれそうな想いでした。私も数年後
には別の女性と出会い結婚をしました。
しかし、みほさんを愛したような愛情で妻と接することは
出来ませんでした。しかし妻とは平和な日々を過ごして幸せ
になることは出来ましたので感謝をしています。妻は3年前
に他界をして、私は現在、独り身です。
最近になって、みほさんはどうしたのか気になって仕方が
なく、思い切って告知を出したのです。今はまだ生きて
いるのか、まだ結婚されているのか?知りたくて仕方がなかったのです。
もちろんアメリカにまだいた場合は日本の新聞にのせても
意味がないですが、思い切って挑戦だけしようと考えたのです。
そしてもし彼女も独り身で、私のことを覚えていてくれて少し
でも私のことを気にしてくれているならもう一度あの情熱的な愛を取
り戻したいと考えたのです。
もちろんこの65歳の老人のたわごとを本気で相手にして
くれるかどうかは分かりません。しかし私は少しでも情熱
が残っているなら、死ぬまでにどうしてもこれだけは知りたいのです。」
ゆっくりだが、とても力強いこの男性のトーンに、
さくらはすっかり感心してしまった。人間の熱い情熱
というのは素晴らしいと心動かされた。
さくらは実はフリーランサーとして、小説を書いていたのだ。
いつも告知を物語のネタにしていた。
そこで、たかしさんから許可をとり、この題材をテーマに
小説を書き上げたいと考えて、早速出版社に連絡をした。
しかし編集者はこの意見に反対をしたので実現はしなかった。
さくらは、時折数ヶ月に一度、気になり、たかしに
連絡をして、あれから、みほさんから連絡が入ったの
かどうか確認をしたが、連絡は来なかった。
それから2年後、、、、
私はいつもどおり東武東上線に乗っていた。そこで、
今日はたかしさんの想いを感じながら、日光まで足
を伸ばそうと考えて、そのまま日光まで散歩に出かけた。
やはり、いつも通り、告知欄を広げながら、趣味にふけっていた。
すると、隣から、なにやら女性が声をかけたきた。
「どなたか、ボーイフレンドでも探してるの?」
隣の女性が笑いながら笑顔で声をかけてきた。
「失礼しました。とっても熱心に新聞を読んでいらっ
しゃるから、どなたかお探しなのかと思って。」
「あ、ええ、趣味なんですよ。告知を見るのが。良かったら見てみますか?」
「私はいいわ。人のお話を読むとつらくて、同情しちゃって
つらくなるのよ。」
どうやら同年代の女性のようだった。どこか人
なつっこくて、人好きのする感じの人だった。私は彼女と気があい、
そのまま席を彼女側へうつって話こんだ。
「で、日光には旅行で来てるの?」さくらは聞いた。
「ええ、思い出旅行かしら」女性は答えた。
「へえー、それは奇遇。私もある男性の思い出のためにここに来たの」
「それはめずらしいですわね。ご主人の思い出とかですか?」
「違うのよ。それがね、、、、」と、たかしさんの話を始めた。
この「たかしさん」の話を、女性は神妙な顔つきで聞いていた。
そして、最後に、さくらがこう切り出した。
「ね、というわけなの。残念ながら、この話はハッピー
エンディングじゃないのね。みほさんは最後まで現れなかった。
私が推測するに、みほさんはもうすでになくなったか、
告知を見ないか、もしくは幸せだから無視をしてるかのどれかね。」
すると女性はこう言った。
「その3つのどれでもないわね。」
と言って、そっと肩をたたいた。
そして彼女は、さくらにこう聞いた。
「ねえ、さくらさん、ところで、たかしさんの電話番号教え下さるかしら」
ちょうどそのとき、電車は日光駅の到着を車内に知らせていた。
いつも っとクリックありがとうございます。
っとクリックありがとうございます。
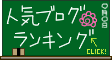 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ