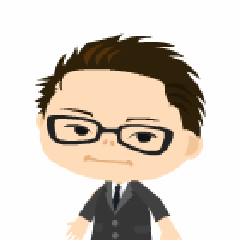基本的には、混雑している場所が苦手な私。
自分以外には周りに誰もいない神社や、静かな場所に置かれた等身大パネルや、なかなか電車の来ない無人駅の待合室に居心地の良さを感じる私が、都内でも屈指の観光客の多さを誇る場所に足を運んでみました。
もはや説明する必要も感じないほどの有名スポット、浅草寺の雷門です。
この日も国内外の観光客で大混雑。
前に進んでいくには、人を押し退けていかないといけないほど。
雷門の正式な名前は「風雷神門」。
奈良時代に浅草寺の総門として建てられ、鎌倉時代に現在の場所に移設された時に、門の左右に風神・雷神の像を設置したところから名付けられました。
風神と、
雷神。
江戸時代には何度も焼失して、また再建されることを繰り返した雷門ですが、幕末に火災に巻き込まれてしまうと、そこから95年間も再建されずに放置されました。
昭和35年、この門を寄進して再建させたのは、当時の松下電器の社長だった松下幸之助氏。
当時、関節痛に悩まされていた松下氏ですが、浅草寺の貫首の祈願によって快復。
その御礼のため、個人で門を寄進すると共に、雷門のシンボルともいえる大提灯も寄進しました。
門の表側を守っているのが風神・雷神なら、門を潜り抜けた裏側で左右に立っているのが、天龍と金龍。
男性の天龍と、
女性の金龍。
浅草寺の山号である「金龍山」にちなみ、水を司る龍神である二神は、昭和53年、松下グループの有志によって奉納されました。
雷門を抜けた先の参道は、
みっちりと密集した人々で埋め尽くされながら、ノロノロと前に進んでいました。
正直なところ、こういった人混みや長い行列に並ぶのは気が進まないのですが、ここまで来ておきながら引き返すわけにもいかないので、思い切って人混みに吞まれてみました。
様々な食べ物やお土産などの店が立ち並ぶ「仲見世」通り。
私も大好きな「人形焼」が欲しかったのですが、人の流れに逆らって立ち止まるのも面倒だったので、そのまま先へと進み続けます。
やがて、視線の先に門らしきものが見えてきました。
ふと左側に視線を向けてみると、
五重塔が姿を見せていました。
江戸時代に徳川家光公によって建てられた五重塔は、明治時代に国宝に指定されましたが、残念ながら昭和20年の東京大空襲によって焼失してしまいました。
現在の塔は昭和48年に再建された鉄筋コンクリート製。
正面に視線を戻してみると、
大きな宝蔵門。
この門を抜けたら、いよいよ本堂への参拝が近付いてきます。
(浅草寺 後編に続く)