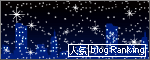この記事はひとつ前のこの記事の続きなので
↓
この記事を読んでいない人は、この記事を読んでからお読みください。<(_ _)>
光の速度を不変にしている自然法則(言い換えるなら、「秘められた自然の仕組み」)は二つあります。
その一つは、動いているものを流れている時間の経過速度は、静止しているものから見た場合、遅くなっているということです。
どれだけの速度で動くと、どれだけ時間が遅くなるかは、アインシュタインが発見した式で計算できます。
そして、その式を計算することによって導き出される通りの時間の遅れが現実の世界で起こっていることは、すでに多くの実験や観測で確かめられています。
例を挙げると、宇宙からは様々な高エネルギーの素粒子(宇宙線)が飛来していて、そうした宇宙線は大気と衝突することで散乱しエネルギーを失うため、私たちは健康に暮らすことが出来ているのですが、そうした宇宙線の中に多く含まれているものにミュー粒子という非常に寿命が短いものがあり、理論的には地上にたどり着くまでに放射性崩壊して他の物質に変わってしまい、地上で観測されることはないはずなのに、実際には地上で数多く観測されているということがあります。
これは光速に近い速度で飛来しているミュー粒子を流れている時間の経過速度が遅くなって、ミュー粒子の寿命が延びているからであると考えられています。
実験で確かめられている、動いているものの時間の遅れには、航空機で運んだ電子時計と、地上に置いてあった電子時計の間に発生する時間のずれが、理論と誤差の範囲内で一致するということがあります。
つまり、動いているものの時間が、静止しているものの時間に対して相対的に遅くなっていること(もう少しわかりやすく言うと、静止しているものを流れている時間が1秒経過したとき、動いているものを流れている時間はまだ1秒経過していないということ)は、疑いようがないということなのです。
ただし、たとえそうであっても、動いているものの時間の経過速度が遅くなるということだけでは、光の速度が不変であることを説明できません。
相対性理論によれば、光の速度を不変にしているものはもう一つあります。
それは、「静止したものから見た(測定した)動いているものの空間は(相対的に)縮んだり、伸びたりしている」ということです。
近付いている場合は縮み、遠ざかっている場合は伸びています。
こうした空間の伸び縮みが実際に起こっていることは、天文学の世界では、地球から遠ざかっている天体の光のスペクトルが赤の方にずれている(光の波長が空間の伸びによって引き延ばされている)という現象(赤方偏移)によって確認されています。
近づいている場合は、空間が縮むため、波長が短くなり、結果としてスペクトルは青の方にずれます。
この現象もまた、青方偏移として実際に起こっていることが天体観測で確認されています。
これから、この二つのことによって、「なぜ秒速1万キロメートルの速度で測定装置の方に走って来い車のライトの発している光の速度が、《光の速度》に《車の速度》を加えた秒速31万キロメートルではなく「なぜ秒速30万キロメートルと測定されるのか」を説明します。
話を分かりやすくするために、秒速の定義を、「何かが一秒間に進んだ距離」として話を藩士を進めていきます。
あなたは今、秒速1万キロメートルの速度であなたの方向に進んでいる車のライトから発せられている光の速度を測定しようとしています。
その光が、1秒間で何万キロメートル進むかというと、《車が進んだ距離1万キロメートル》に《光が進んだ距離30万キロメートル》を足した、31万キロメートル進むことになります。
これを速度にすると、秒速31万キロメートルということになるため、相対性理論の「いかなるものも光速を超えることはできない」ということに反してしまい、これはこれであり得ないおかしな話になってしまうのですが、ここで取り扱っている問題は別のことなので、ひとまずこの問題はスルーして先に進みます。
光の速度がなぜ不変なのかという謎を解いたとき、自動的にその答えは、この問題も解決していることになるので、ここではスルーしても大丈夫なのです。
この先を考えるうえで、非常に重要なことがあります。
それは、「たしかに、車のライトの光は、1秒間で31万キロメートル進んでいますが、それは、車の前で測定している人を流れている時間の1秒でも、車の前で測定している人から見た31万キロメートルでもない」ということです。
相対性理論によれば、動いている車や車のライトから発せられている光を流れている時間の経過速度は、それを測定している人や物を流れている1秒より遅くなっていて、空間は縮んでいるのです。
これによって具体的に何が起こるかというと、測定装置を流れる時間が1秒経過したとき、車と車のライトから発せられた光を流れている時間はまだ1秒経過していないことになり、その光は、想定装置の測定では31万キロメートルより短い距離しか進んでいないことになるのです。
つまり、測定装置が測定する光の速度は秒速31万キロメートルより遅くなるのです。
このときの光の速度が、どれくらい31万キロメートルより遅くなっているかは簡単には計算できませんが(ただし、それを計算する式はネットで拾えるし、計算はコンピューターがやってくれるので、やろうと思えばその正確な数値は誰にでも導き出せます)、一つだけ言えることは、秒速31万キロメートル以下になっているということです。
次に、走っている車とライトの光進んでいる空間の縮みに注目します。
車に乗っている人から見れば、光は1秒で31万キロメートルの距離を進んでいますが、その距離は、静止している人や測定装置から見れば縮んでいるため、測定装置は、車のライトの光が1秒間に進んだ距離を31万キロメートル以下と測定することになります。
このときの空間の縮みによってどれくらい車のライトの光の進む距離が短くなり、光の速度が遅くなっているかというと、前述している理由と同じ理由によって正確には言えませんが、一つだけ言えることは、時間の経過速度が遅くなったことで短くなった距離と、空間の縮みで短くなった距離を、31万キロメートルから引いたとき、きっちり本来の光速度である秒速30万キロメートルになるように短くなっているのです。
以下は、測定装置から遠ざかる方向に秒速1万キロメートルの速度で動いている車のライトが発している光の速度を測定したとき、《光の速度》ー《車の速度》=秒速29万キロメートルとならずに、なぜ秒速30万キロメートルになるのかということの説明です。
この場合は、車と車のライトの光を流れている時間の遅れによって、車があなたに近づいているときとはまったく逆の現象が起こり、あなたの測定装置が測定した、車のライトが発している光の速度は、秒速29万キロメートルより速くなります。
それだけでなく、車のライトから発せられた光の進んでいる空間は伸びているため、それによって光の進んでいる距離は引き延ばされていて、これによっても測定装置が測定するライトの光の速度は秒速29万キロメートル以上になります。
時間の遅れによってどれだけ速度が速くなり、空間の伸びによってどれだけ速度速くなっているかというと、その二つを秒速29万キロメートルに足すと、きっちり秒速30万キロメートルになるように速くなっているのです。
光源を固定しておいて、測定者が車に乗って光源に近づきながら光の速度を測定した場合も、光源から遠ざかりながら測定した場合も、測定者を流れる時間の遅れと、空間の伸び縮みによって、光の速度が秒速30万キロのまま、変化しないことを導き出せます。
以上が、前回の記事で読者の皆さんに問いかけていた問題の答えです。
自然は、こうした自然法則によって、宇宙を、宇宙に生み落とされた私たちを、完璧な秩序の中で育んでいるのです。
相対性理論や量子力学の解説だけでなく、量子力学を構築した物理学者たちの多くが傾倒した、ヒンドゥー教の聖典、ヴェーダ及びヴェーダーンタや仏教哲学に開示されている、宇宙論や生命論や神論の紹介と解説に焦点を当てて書いた、この本もよろしく。
一生懸命読まさせていただきました。コメント返信の丁寧なご説明の加筆ありがとうございます。
1、光のように高速で進んでいるものの中の時間は静止してるほうの観測者から見たらば、ゆっくりになり遅れる。2、観測者との間の空間は、近づく遠ざかるで、間に柔らかい風船があるように伸縮する。 3、時間の遅れと空間の伸縮のバランスが時空のセットの性質で保たれていて光の速さは一定に保たれている。 で良いですか?
このような光の速度が不変な仕組みを、ムラリー63さんは、完璧な秩序があるとおっしゃっていられるのですね。間違ってたらごめんなさい。
とても不思議で興味深い、光の性質を考えることができてうれしかったです。ありがとうございました。
>ストローさん
コメントありがとうございます。
非常にセンスのいい理解で、全体的に間違っていません。
ただ一つだけ、「ひょっとすると勘違いしていることがあるのかな?」と思ったのは、『光のように高速で進んでいるものの中の時間は静止してるほうの観測者から見たらば、ゆっくりになり遅れる』
という部分です。
光のように高速で進んでいるものの中の時間だけでなく、すとろさんの散歩ように、ゆっくり進んでいる人を流れている時間も、静止している人を流れている時間より遅れています。
ただその時間の遅れがほぼゼロに近いほど小さいので、誰も気づいていないだけです。
この後も、電子書籍からは割愛していた、相対性理論の興味深い話を紹介していきます。
なぜ電子書籍からは割愛していた、相対性理論の興味深い話を紹介しているかというと、電子書籍の宣伝のためです。(^^)/~~、
>murari63さん 早速のご返信ご教授ありがとうございます.光のような高速でなくても進んでいるものの時間が静止しているものよりゆっくりになる。けど、違いが時間が近すぎてわからないだけなのですか.だとしたら厳密に言うと、ジェット機のパイロットさんは長く勤務したらちりつもで、一般人より若いよ的な現象が起こりますよね。それでも理屈でってことですね!光の速さと比べると他はどんぐりせっくらべってことだけど時間の遅れはあると考えてて良いですね。
03月05日 19:03
>ストローさん
コメントに書いてある考えであっています。(*^▽^*)/
ただ、相対的な二者を流れている、一方の時間を遅らせているものには、速度とは別にもう一つ《重力》があって、重力はジェット機のパイロットより地上にいる人を流れている時間の速度を遅くしているので、(それを差し引いてもジェット機のパイロットを流れている時間の方が遅くなっているはずですが)地上にいる人とパイロットを流れている時間の進む速度の差は、小さくなっています。
それと、重力の影響は地面に近い方が大きいので、ストローさんの体の部位の中では、(物理的な)頭が一番年を取っていて、足の裏が一番若いことになります。![]()
03月06日 01:50