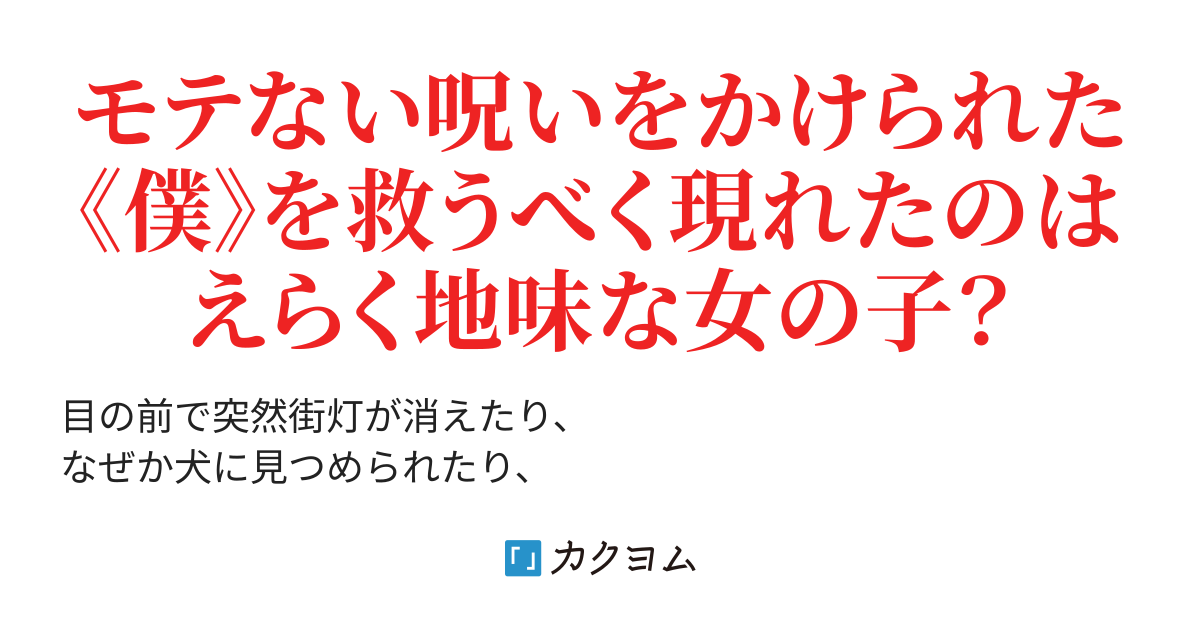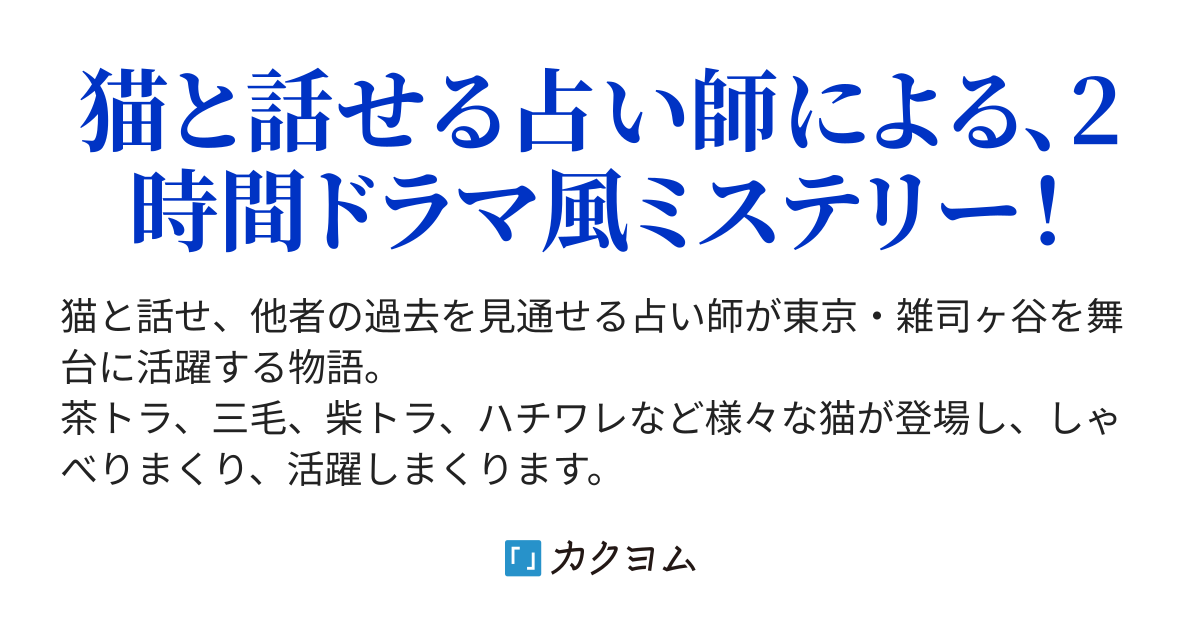次話へ→
― 1 ―
ただ、私は別に詩になんて興味がなかった。中学のとき仲の良かった子が文芸部に入りたいなんて言ったから、つきあいで入っただけだった。だから、その詩だって適当に書いたものだった。ほんとなんとなく思いついたのを書いただけなのだ。でも、高槻さんは読んだあとで溜息さえついた。教室全体を見渡し、紙を振りながら「これを書いた落合さんって?」と訊いてきた。
「え? あ、はい。私ですけど」
ガタッと椅子を鳴らし、私は立ちあがった。なにか気にくわないことがあったんじゃないかと若干だけビクビクしながらだ。
「ああ、あなたが書いたんですね。で、これは人称を『僕』としてますが、それはなにか意図があってのことですか?」
「意図?」
「ああ、いえ、なんとなくそうしたってのもありですよ。ただ、女の子が『僕』とするのには格段の意味があるのかと気になったものですから」
「あ、あの、なんとなくそうしただけです」
そうこたえると笑い声が聞こえてきた。私はうつむいてしまった。恥ずかしくなったのだ。
「そうでしたか。だけど、なかなかいいですね。いや、けっこういい。言葉の選び方が秀逸です。ひとつだけ言っておくと二回目に出てくる『分かれた』は『分かたれた』にした方がいいと思いますがね。しかし、うん、かなりいいですね。僕はこういうの好きですよ」
それから高槻さんは幾つかの詩を「なかなかいい」と言って、書いた者に質問した。そして、このように言った。
「いや、はじめにみなさんの書いたものを読みたいと思って詩にしてもらったんですが、実のところ僕は詩に詳しくないんですよ。ただ、小説もそうですが、こういったものに理解は不要だと思っています。絵なんかもそうですね。あれも理解するものじゃない。感じることが求められてるわけです。読んだり観たりしたときに一定の雰囲気を感じることってありますよね。それさえ受け取ればいいって考えています」
そこで言葉を切り、高槻さんは教室全体を見まわした。黒い縁の眼鏡の奥にある目は大きかった。背は高く、ひょろっと痩せていて、頬は完全に平面だった。
「ただ、今日は創作についての話なので少しだけ理屈っぽいことを言います。では、本題に入りましょう。これから十回に分けて『三四郎』を読んでいきます。その間にみなさんにはなんらかの創作をして頂きます。いえ、『三四郎』に絡めたりする必要はないですよ。これは僕が好きってだけで選んだものですから。――じゃあ、さっそく、」
そう言って、高槻さんは読みはじめた。声は高く、少年のもののようだった。それに、すこしだけうわずってもいた。
『うとうととして眼が覚めると女は何時の間にか、隣の爺さんと話を始めている。この爺さんは慥かに前の前の駅から乗った田舎者である。発車間際に頓狂な声を出して、馳け込んで来て、いきなり肌を抜いだと思ったら脊中に 御 灸の痕が一杯あったので、三四郎の記憶に残っている。爺さんが汗を拭いて、肌を入れて、女の隣りに腰を懸けたまでよく注意して見ていた位である。
女とは京都からの相乗である。乗った時から三四郎の眼に着いた。第一色が黒い。三四郎は九州から山陽線に移って、段々京大阪へ近付いてくるうちに、女の色が次第に白くなるので何時の間にか故郷を遠退くような憐れを感じていた。それでこの女が車室に這入って来た時は、何となく異性の味方を得た心持がした。この女の色は実際九州色であった』
教室は強い陽射しに白くぼやけてすらみえた。ふと顔を向けると未玖がノートになにか書いている。覗いて見るまでもなく、それは高槻さんの似顔だった。私は首を振り、窓の外を眺めた。バットに硬球のあたる音が聞こえた。歓声も聞こえてきた。
「『車が動き出して二分も立ったろうと思う頃例の女はすうと立って三四郎の横を通り越して車室の外へ出て行った。この時女の帯の色が始めて三四郎の眼に這入った。三四郎は鮎の煮浸しの頭を啣えたまま女の後姿を見送っていた――』」
しばらく読みすすめた後で「十六ページまで読んでください」と言い、高槻さんはノートへ目を落とした。私たちは歓声が洩れ聞こえる中で文庫本に向かっていた。風が通り抜け、毛先をすこしだけ揺らした。
「読めましたか? では、ちょっとだけ話しますね。まずここで漱石はひとりの女性との関わりを描いてます。これは三四郎の性格を端的にあらわすのに必要な部分なんですね。この女性に『あなたはよっぽど度胸のない方ですね』と言わせることで、彼の人となりが読者にすっと入っていくのです。『二十三年の弱点が一度に露見したような心持であった』というのも説明的になりすぎず彼をあらわしてます。どうでしょう? これをたとえば『小川三四郎という二十三歳の男が東京の大学に通うため故郷の福岡を出て汽車に乗っている。彼は子供の頃から度胸がなく、それを自分でも理解している』なんてふうに書いたら、わかりやすいけど面白くはないですよね」
私は顔をあげた。そのときに目が合った。なぜかわからないけど高槻さんはうなずいている。
「それに、この部分には予感がある。どういった運命が待ちかまえているかといった予感です。彼は素性のわからない女性と同じ部屋に泊まることになった。それもはっきりものを言えなかったからそうなってしまったんです。漱石はそういうシチュエーションを用意して読者の興味を惹くとともに、三四郎の性格を強調しています。ま、シーツを使って境界線をつくるというのは馬鹿げた感じですが、それも含めて彼の性格を物語ってますね。――で、予感ですが、のっけにこういう人物を登場させることで、三四郎の前途には女性に関わる問題が起こりそうだという雰囲気をにおわせているんです。そして、その直後には『髭のある男』というのを登場させています。これも予感を持たせる展開ですね。まあ、東京の大学へ通うのだから当然ともいえますが、三四郎の未来にふたつの世界があるのを示しています。後の方で漱石は『三つの世界』について書いてますが、そのひとつは故郷を含めた過去です。他のふたつは『現実世界の稲妻』である汽車の女性が指し示す世界でもあり、『髭のある男』が象徴する学問の世界というわけです。また、そうやって漱石はうまい具合にバランスをとってるんですね。これは下世話な小説でないというのを『髭のある男』との会話であらわしているんです」
高槻さんはまた顔をあげた。私はさっと教室を見まわした。だいたいの者は教卓の方を向いている。とはいっても九人しかいないけど。
「では、つづきを読みましょう。『髭を濃く生している、面長の瘠ぎすの』辺りからですね」
次話へ→
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》