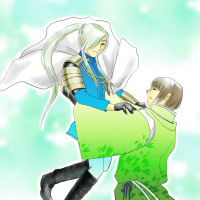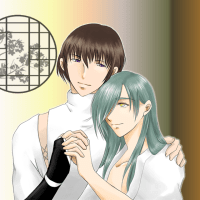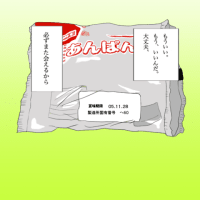新緑が、青天を受け止める様に枝葉を伸ばしている。
風は春のものだが、正午の日差しは既に初夏のそれを忍ばせる。
日差しが強くなる前に畑仕事を一段落させ、石切丸と小狐丸は並んで縁側に腰掛けていた。
視線の先には本丸の正門が見え、その前で後藤と厚がキャッチボールをしている。
のどかで平和過ぎる、本丸の昼前の光景だった。
「そういえば」
沈黙を破ったのは、小狐丸だった。
視線は庭へと向けたまま、言葉を続ける。
「あの頃は花水木が咲いていたのに、もう桜も終わりとは早いものですな」
石切丸はしばらく考え、花水木で思い出した。
自らの想いを託した花水木と歌を、彼に頼んで届けて貰ったのだった。
「青江の事かい」
「正直なところ、あの御仁のどこに惚れたのですか?」
「…随分な質問だなぁ」
「貴方から聞かされるのは愚痴か悩みばかり、不思議にもなります」
多少の呆れを含んだ声音で、小狐丸は横目見た。
「確かに青江殿はお美しいですが、見目良さだけの者なら幾らでもおりますし」
「うーん……どこから説明すればいいのかな……」
石切丸は腕を組むと、小難しい顔で首を捻った。
暫しの思案の後、ぽんと膝を打つ。
「まだ社にいた頃、虫干しついでに年に一度、皆に披露されてたろう」
「ああ、そう言えば。懐かしいですな」
「青江に一番最初に会った時、彼の私を見る目が、初めて私を見た子供達のそれにそっくりでねぇ…」
懐かしそうに石切丸は微笑んだ。
「何だか可愛いなと、印象に残ったよ…後で脇差だと聞いて、納得したけれど」
「私には驚愕しかありませんでしたが」
「確かに、あんな脇差がいるかと思うね」
微笑を苦笑に変え、頷く。
ふと笑みをおさめると、視線を空へと向けた。
「珍妙な振る舞いをするけれど、誰か笑わせなきゃいけない人がいる時だと気付いたし」
菫色の瞳を眩しげに細め、言葉を続ける。
「人一倍子供好きなのに、幼子の霊を斬った過去を今でも許せないでいる。その苦悩さえ何だか愛しくてね」
それがひとたび戦場に出れば。
たおやかな笑みを浮かべたまま、誰よりも速く敵を屠り、返り血一滴すら浴びはしない。
鮮やかなその剣閃に、見惚れる事もしばしばあった。
「その変り様がねぇ…」
「ギャップ萌という奴ですか」
「ぎゃっぷもえ?何だいそれは」
「話せば長くなります」
風で乱れてきた髪を手櫛で整え、小狐丸はちらりと隣を顧みた。
唇には意味深な笑みを浮かべている。
「しかし…それ位ではここまで彼に入れ込まないでしょう?」
「…分かるかい、やっぱり」
照れ臭げに頬を掻くと、石切丸は目を閉じた。
知らずの内に、口元を綻ばせて。
「見ているんだよ、私の事を」
金色の瞳が、時折覗く紅玉の瞳が、瞼の裏に鮮やかに思い出される。
穏やかに降る木漏れ日の中で、血煙りの去った戦場の跡で、宵闇が静かに包む本丸の縁側で。
いつも目が合うたびに、小さく微笑み手を振る姿。
「その時やっと自覚したよ。私も同じ位、ずっと彼を見ていたんだと」
「端から一目惚れの両想いというのは、まことでしたか」
「だ、誰から聞いたんだい!?」
「たまには三日月殿も、本当の事を言うのですねぇ」
頬を染めて頭を抱える石切丸を無視し、小狐丸は正門の方を注視した。
後藤達が、門の外に手を振っている。
「遠征組が戻ったようですよ」
「!」
はたと顔を上げると、石切丸は立ち上がった。
正門が見える場所に居たのは、これを待っていたからだ。
前田に大典太、山姥切に蜂須賀の姿が見える。
そしてその一番後ろから、のんびりとした歩調で、薫風に白装束をはためかせながら続く人影。
…相性の難しい人選の隊に、いつも放り込まれるのだと笑いながらぼやいていた。
その笑顔と柔軟な性格が、人をまとめる大きな要なのだと主が買っているのだから、仕方ない。
「ただいま戻りました!」
「おかえりー!どうだったー?」
皆の表情は明るい。
上手くいったのだろう。
「上々です!主君に報告してきますね」
足早に本丸へと向かう前田とすれ違いに、石切丸は歩み寄った。
銘々が労いの言葉を掛け合い、持ち帰った資材を納めに散ろうとしている。
近付いてきた石切丸の姿を認め、青江は足を止めて微笑んだ。
「おかえり、青江」
笑顔で当たり前のように、両腕を広げる。
この大胆さは天然なのか確信なのか、今だに青江にも分らない。
背後では、小狐丸が苦笑しつつ立ち上がろうとしていた。
「…ただいま。君が迎えにくるなんて、珍しいね」
さも平静を装いつつ、青江は石切丸の胸に身を委ねようとした。
と、不意にその膝がかくりと崩れた。
「青江!?」
咄嗟に抱き止めた腕に、脱力しきった重みがかかる。
つい先程まで微笑んでいた瞳は瞼に閉ざされ、呼び掛けに反応はない。
異変に気付いた小狐丸が、足を止めて振り返る。
石切丸の腕の中で、唐突に青江は意識を失っていた。
微かな呼吸の乱れを聴きとめ、石切丸は憔悴しきった顔を上げた。
褥に横たわったまま、青江が初めて小さく身動ぎした。
瞼が震え、ゆっくり開いてゆく。
その視界に一番に映ったのは、気遣わしげに覗き込む石切丸の顔だった。
「青江…見えるかい?聴こえるかい?」
「……」
瞳を石切丸に留めたまま、こくりと頷く。
やっと安堵の溜息を吐くと、石切丸は青磁色の髪を優しく撫でた。
「良かった…突然倒れたから、本当に心配したよ。どこか痛む所は?」
ゆっくり首を振るその表情に違和感を覚え、石切丸の顔から笑みが消える。
「…青江?」
「……それは、僕の名前?」
戸惑いに顔を曇らせ、青江は確かに青江の声で、言葉を続けた。
「君は……誰?」
西日が縁側へ柔らかに色づいた光を投げている。
その中に座って、青江は所なさげに足をぶらつかせていた。
夜着に、大き過ぎる羽織を着ただけの姿で、髪も無造作に流したままだ。
結い方を憶えていないのだから。
暗い面持ちでその後ろ姿を見つめた後、石切丸は視線を向いに座る長谷部へと戻した。
「まだ原因は判らない…ということだね」
「ああ。だがにっかり青江『本体』に、何らかの非物理的損傷が認められたそうだ」
「それは、直るのかい?」
「今、主が手を尽くしておられる。修復は可能だが、時間が要る」
縁側からちらちらと、青江が室内を伺っている気配がする。
本来の彼なら、こんな気配さえ空気のように消せるというのに。
「…今の青江は、己が刀剣男士である事も、刀としての記憶も全て忘れている」
それだけではない。
石切丸は胸の中で呟いた。
この本丸での暮らし、仲間達との思い出、そして愛する者の事も。
「石切丸、お前にしか奴の事は頼めない。当分付ききりになるだろうが、良いだろうか?」
「ああ、大丈夫だよ」
他の誰が、己の代わりができるというのか。
石切丸は力強く、はっきりと応えた。
「では頼んだ。出陣や内番からは外しておく。後、混乱を避ける為に出来る限り他との接触も避けてくれ」
「分った」
石切丸が頷くのを横目に、長谷部は立ち上がると素早く部屋を出て行った。
それを見届けてから浅く嘆息し、石切丸は縁側へと出た。
ずっと待っていたのだろう。
不安げな金色の瞳が、じっと見上げてくる。
「待たせたね、青江」
「ううん……僕の事を、話していたんだね」
無意識なのか、隣に腰かける石切丸に心持ち寄り添い、青江は首を振った。
「話半分も分らなかったよ…どうしたら良いんだろう」
「何も焦る事はないよ。時間が経てば、必ず元に戻るから」
慰める様に頭を撫で、はたと石切丸は気付いた。
完全に習慣付いてしまって、いつも通りに触れてしまった。
常と違うのは、青江が頬を染めて俯いている位か。
「あの……ずっと気になってたんだけど」
「な、何だい?」
「君…石、切丸は、よく僕に触るよね。それってつまり……」
恥しがり屋なのは元々の性格らしい。
そこまで言って、青江は両手で顔を覆ってしまった。
桃色に色付いた耳朶に口付けたい衝動を、石切丸は鋼の平常心でぐっと堪えた。
「……うん。私達は、恋人同士だよ」
「!」
掌の中で、青江が息を呑んだ気配がした。
山の端に傾きかけた夕日が、二人の影を寄り添わせている。
長い沈黙の中、石切丸はじっと待っていた。
やがて肩を落とすと、青江は顔を覆っていた手を下した。
まだ葛藤と躊躇に歪んだままの唇を噛み、首を振る。
「…ごめん。やっぱり思い出せない」
「良いんだよ」
「でもそんなに大事なことなのに…!」
「青江」
石切丸は、青江の肩にそっと手を乗せた。
それだけで、金色の瞳から焦燥の色が消えた。
「焦ってはいけないよ。不安だろうけれど、その時は私を頼りなさい」
「………」
「ところで、私に触れられるのは苦手かな?」
敢えて石切丸は話題を逸らした。
再び俯いてしまった青江の頬を染めているのは、恥じらいなのか夕日なのか分らない。
「……ううん、すごく安心する」
ああ、いつもの青江の口からは、こんな告白は聞けないだろう。
不謹慎と思いつつ、感激に拳を握る。
追い討つように、青江は上目遣いで石切丸を見上げ、はにかんだ笑顔を浮かべた。
「僕は本当に、君の事が大好きだったんだねぇ」
眩暈を覚え、危うく石切丸は上体を傾ぎかけた。
慌てて青江がその肩を支える。
「ど、どうしたんだい?大丈夫?」
「大丈夫…ああ、私はもういつ折れてもいい…」
「折れ…?」
「いや、何でもないよ…冷えてきたね、中へ戻ろうか」
夕日に負けぬほど上気しきった頬のまま、石切丸は勢い良く青江を横抱きに立ち上がった。
「一応、青江くんは体調不良で寝込んでる事になってるからね」
運んできた二人分の膳を置きながら、燭台切は穏やかな笑顔で言葉を続けた。
いつもの食堂ではなく、石切丸の部屋で夕餉を取る事になった。
必要最低限の者しか青江の件は知らないが、燭台切はそのうちの一人のようだった。
「でも遠征から帰ってきて、まともに食べてないよね?遅くなってごめん」
「…えっと…」
「僕は燭台切光忠。どちらで呼んでくれても構わないよ」
「光忠とは呼んでないからね、青江」
少々刺のある声で、ぽつりと石切丸は呟いた。
効いているのか、いないのか、燭台切はしみじみとした眼差しで青江の顔を見詰めている。
「何だか懐かしいなぁ…青江くんがこの本丸に来たばかりの時のようだよ。あ、石切丸さんはまだ居なかったね」
「………」
「ちょうど僕が近侍の頃だったから、色々案内したり、教えてあげたりしたね。君は本当に好奇心旺盛で…」
「燭台切君!今は私がいるから!」
「うん、石切丸さんに色々教えて貰うといいよ。彼なら安心して任せて大丈夫」
鮮やかな笑顔で石切丸の言葉をかわすと、燭台切は立ち上がった。
「お膳は石切丸さんが戻しに来てくれると助かるな。それじゃあ」
手を振る燭台切に、青江は微笑を浮かべてぺこりと頭を下げた。
その仕草が愛らしいだけに、石切丸の心中はますます穏やかさを失った。
「燭台切さんって、良い人だね」
「…そうだね」
「色々親切にして貰ってるんだろうなぁ…僕と、仲良かったのかなぁ」
「…そうかもしれないね」
「石切丸って、顔に似合わずやきもち焼きなんだね」
「その通りだよ……って」
思わず目を丸くする石切丸の顔を眺めながら、青江はくすくす笑っている。
内心大きく嘆息しつつ、石切丸は手を合わせた。
元の青江が聞けば、鼻で笑われるか白い目で見られるか。
少なくとも今の青江の様に、手離しの笑顔で喜んだりはしないだろう。
あくまで表向きは。
「ふふっ…愛されてるって、嬉しいな」
箸を動かしながら、青江はまだ微笑っている。
愛くるしさで胸が詰まって、なかなか石切丸の食は進まない。
今の青江は、素直過ぎるのだ。
人を煙に巻くあの態度は、絶妙な緩衝材になっていたのだろう。
時として石切丸さえ苛立たせるものではあったが、今のままでは逆に嫉妬で胃に穴が開きかねない。
「…石切丸?」
悶々とした思考から我に返ると、不安気な目で青江が覗き込んでいる。
「まだ……怒ってる?」
声には、微かに怯えが伺える。
その意味を察して、石切丸は何ともやるせない気持ちになった。
記憶を失くした青江には、石切丸は唯一の「自分を愛し、頼る事が出来る他人」に過ぎないのだ。
「怒ってないよ。ただ、神というものは嫉妬深くてね」
「神?」
「あ……そうか」
それさえも説明しなければいけない。
早く記憶が戻るよう、耐えなければならないのは石切丸も同じだった。
厨から戻って襖を開けた石切丸の眼に、床の間の前に座る青江の後姿が映った。
手には白鞘の大太刀がある。
もしや、と色めきたった石切丸の期待は、振り向いた青江の表情に萎れた。
戸惑いに似た複雑な表情で、青江は手にした大太刀を見下ろした。
「これ……刀だね」
「うん、私の物だよ」
刀剣男士について説明する事は、止める事にしていた。
人の身と心しか持たない今の青江には、混乱しか招かないだろう。
「血の臭いがする」
ぽつりと、青江は呟いた。
血を忌み、極力その穢れを除いているはずの大太刀からそれを感じ取るとは、本能なのか。
「石切丸は、戦っているの?」
「…ああ。ここにいる者は皆、戦う為に存在している」
「僕も?」
「君は誰よりも疾く、美しく戦っていたよ」
青江は手にした大太刀を、ぎゅっと胸に抱き締めた。
石切丸『本体』から、青江の感情が伝わってくる。
不安と焦燥と、何よりも大きな怯え。
戦う事へではなく、戦えない事への怯えが。
「今の僕は、刀の握り方さえ分らない…」
「大丈夫だよ。記憶が戻れば…」
「でももし、戻らなかったら!?」
突然の強い口調に、石切丸は言葉を呑んだ。
悲愴な表情で、青江は石切丸を見上げて訴えた。
「嫌だよ!君だけ戦場に出て、待っているだけだなんて。僕も戦いたい!」
「……戦う事が、怖くはないのかい?」
一寸の躊躇いなく、青江は頷いた。
改めて、石切丸は心の中で感嘆した。
これが『にっかり青江』の本質なのだ。
実を以て名を成してきた、生粋の戦刀。
たとえ記憶がなかろうと、その本質は変わりない。
何と潔く、清廉なことか。
「青江」
石切丸は腕を伸ばすと、大太刀ごと青江を胸に抱き寄せた。
驚きの表情で見上げる金色の瞳に、心の底から愛しさを込めて、頷きかける。
「たとえ記憶が戻らなくても、私が戦い方を教えるよ。幾ら時間がかかろうと、必ず」
「…石切丸…」
「私は戦の専門家ではないし、君の方が余程筋は良いのだから、すぐに同じ戦場に立てる様になる」
「ありがとう、石切丸」
「……許しておくれ、青江」
「え?」
突然の謝罪に首を傾げる青江の髪に、石切丸は己の表情を隠すように深く顔を埋めた。
「…私は、君がこのまま戦に出なければ良いと思っていた」
「……」
「私は戦が嫌いでね。君が傷つくのを見るのが、本当に辛かった」
思い出しても心が震える。
石切丸は、思いの丈のまま、抱いた腕に力を込めた。
「それでも君は、戦うという。今ならもう、傷つかない生き方も選べるというのに…」
無言のまま、青江は石切丸の胸に顔を埋め、首を振った。
抱き締めたままの大太刀が、かちりと鳴る。
「青江は本当に、強い子だ」
「……君を、守りたいから」
「以前も、同じ事を言ってくれたね」
「!」
はっと顔を上げる青江の額に、石切丸は掠めるだけの口付けを落とした。
「愛しているよ、青江」
見開いた金色の瞳に、石切丸の微笑が映る。
それがじわりと、滲んで流れた。
「あ、れ……」
溢れ出した涙を、戸惑いながら青江は拭った。
それでも後から後から、雫が頬を伝う。
「どうしてだろ……悲しくなんか、ないのに」
落ちた雫が一筋、抱いた大太刀に触れる。
その瞬間、石切丸の脳裏に声が聴こえた。
青江にも聴こえていない、青江自身の心の声が。
『何度折れようと、何度忘れてしまったとしても、僕は君を必ず好きになる』
寝返りを打った拍子にこつりと、額に固いものが当たった。
その慣れない感触に、青江はゆっくり眼を開いた。
まるで添い寝でもするように、太い柄が目の前に横たわっている。
そう言えば昨夜は、石切丸の大太刀を腕に抱いたまま、眠りこんでしまったのだった。
自らの体温で温もったそれを抱えて、青江は褥から身を起こした。
枕元には、大きめの夜着がきちんと畳んで置いてある。
障子越しの朝の光が差し込む室内に、青江は一人だった。
朝の勤めもそこそこに、石切丸は足早に自室へと戻ろうとしていた。
青江を一人にするのが不安で仕方ない。
目が覚めて、もし自分がいない事に気付いたら青江はどうなるだろうか。
石切丸の懸念は、大太刀をしっかり抱いたまま、自室の前に立ち尽くす青江の姿を見て、一気に爆発した。
裾を絡ませながらも駆け寄り、今にも泣き出しそうな青江をしっかと抱き締めた。
「済まない青江、一人にして本当に済まなかった…」
「……」
腕の中で、青江は小さく震えている。
申し訳なさと愛しさが込み上げ、思わず髪に何度も頬擦りした。
「……ふふっ」
「!?」
不意に耳元を擽った笑いに、石切丸は硬直した。
今では隠しようもない位、青江は肩を震わせて笑っている。
「あ~、やっぱり無理。あの真似は出来ないねぇ」
「…あ、あ…」
「どうしたんだい?僕の名前を忘れちゃった?」
へなへなとその場に崩折れる石切丸の前に、青江は一緒にしゃがみ込んで顔を覗いた。
さも楽しげな笑顔は、見慣れた、癖のあるにっかりとした…。
「記憶が戻ったのかい!?」
「うん、寝て起きたらね。もちろん、記憶がなかった頃の事も覚えているよ」
皮肉たっぷりに唇を歪め、青江は青褪めた石切丸の頬をつついた。
「ねぇ、素直な僕はさぞ可愛かったろう?」
「…止めなさい。記憶が薄れる…」
「君が燭台切に嫉妬してたとは、さすがに気付かなかったなぁー」
「青江!」
珍しく厳しい声で諌められ、青江は肩を竦めた。
これ見よがしに大きく溜息を吐くと、石切丸は強く、しっかりと青江の背を抱き寄せた。
「……良かった、本当に……」
しみじみとした安堵の囁きに、青江は静かに目を閉じ、微笑んだ。
大太刀をそっと置くと、広い背一杯に両腕を回す。
「愛してるよ、石切丸」
長らく培ってきた想いと、昨日生まれたばかりの想いを込めて、応える。
無言のまま、ゆっくり石切丸は頷いた。
顔を覗かせたばかりの穏やかな朝日が、固く抱き合う二人を優しく包んでいた。
**********************************************************
初めて書いたかもしれない、ほのぼの甘々プチシリアス石かり小説。
プライベッターに置くとR18とごっちゃになるので、全年齢ものはブログに載せてゆきます。
次は、また怪異ものの小話を書きたいなぁ~。
ネタに困っているんですけどね!