
こんにちは。RIYOです。
今回の作品はこちらです。

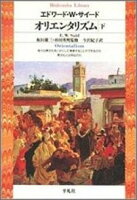
「オリエンタリズム」とは東洋趣味という意味合いを持つ言葉でした。西洋側から見た場合の異国性、異文化性を魅力的に捉え、憧憬や情緒を感じる「特異な地」を表すものです。しかしながら現在においては、「オリエント」(東洋)という言葉から紋切型の凝り固まったイメージを連想させられます。この連想イメージは如何にして与えられるのかを追究し、紐解こうとしたのがエドワード・ワディン・サイード(1935-2003)です。彼自身、イギリス帝国の支配下であったパレスチナにて生を受けており、その生い立ちもこの研究へと没頭した原動力の一つです。
ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地である最古の都市エルサレムは、アレクサンドロス大王、ユダヤ戦争、十字軍の進軍、オスマン帝国による占領など、信仰と争いの中心として2000年以上も土地を脅かされ続けました。西洋諸国の迫害を受け続けたユダヤ人はこのエルサレムに対して、1890年代に「故郷を再建しよう」というシオニズム(シオン運動)を起こします。オーストリアのユダヤ系思想家ナータン・ビルンバウムが提唱したもので、「シオン」(聖地エルサレムと同義)へと移住し、自らの故郷を再建しようとする運動でした。ユダヤ人を民族と定義した彼は、西洋に住む「虐げられていた」ユダヤ人から強い支持を受けており、この運動に賛同してエルサレムへと移住する人々が増加します。その後、第一次世界大戦争にてオスマン帝国が崩壊すると、国際連盟によってパレスチナのイギリスによる委任統治が認められ、新たな支配が始まりました。そして、1947年にエルサレムを含むパレスチナは国際連合による分割協議を受けて、イスラエルというシオニズムが目指したユダヤ教国家がようやく誕生しました。サイードはこのイギリスによる委任統治の時期にエルサレムの地で暮らしました。アメリカ退役軍人であった父親の影響によって、彼自身もアメリカ国民となり、文芸理論、文芸批評などを中心に文学研究の道へと進みます。文化的批評眼を持った西洋文学(主に英仏)への視線は、東洋への偏向的な描写に気付きを与えます。サイードは、オリエント(東洋)とオクシデント(西洋)には、心象地理としての大きな隔たりがあり、これらが交わることのない決定的な境界線が引かれているとする考えを持ちます。この境界を心象に齎しているものが何かを、本書『オリエンタリズム』の中で紐解いていきます。そして、オリエント(東洋)とオリエンタリスト(東洋研究者)の関係性と研究成果、及び東洋人への目線と印象、といったものを、まとめて「オリエンタリズム」としています。
第一に、「オリエンタリズム」は本来的に客観的な研究分野でなければならないなかで、西洋による東洋の政治的な支配を正当化するために利用されてきました。サイードは、哲学者ミシェル・フーコーの唱える「言説」(ディスクール)の理論を用いて、支配者側の支配的言説利用を唱えています。植民地に対しての姿勢を表現した演説、植民地の住民を紋切型に示した文学作品など、言語で表されたものが印象を植え付け、その印象こそが真であるという認識へと繋げていきます。これらの紋切型には、東洋は西洋より劣っているという「西洋優位」が如実に盛り込まれ、東洋の本質からかけ離れた劣等な印象を聴衆や読者へ与えていきます。これにより、劣っている民族は先進的な思考を持つ西洋が導かなければならない、だからこそ占領して支配しているのだ、という説得性を与える一翼を担っていると考えられます。
第二に、「オリエンタリズム」は、東洋を客観的に捉えるというよりも、オリエンタリストが東洋という対照的な鏡を通して自らを定義(正当化)することに重点を置いていました。そのために、西洋は自己のイメージを構築するために対極的他者としてオリエント(東洋)を構築します。このオリエントには真実を照らそうという意思は介在せず、「与えたいイメージを先行させた」研究手法で構築されています。現実とは掛け離れた西洋にとって都合の良い存在です。言い換えれば、オリエンタリストが(西洋の)先人たちの業績を受け、現地へと向かい生活を過ごすことによる研究を、(西洋にとって)より意義のある成果を生み、(西洋にとって)より自身の存在価値を高めようとすることに利用されたという側面が見えてきます。
第三に、東洋(東洋人)を均質な民衆として捉えることで、劣勢な民族性が強調されます。十把一絡げに括りあげた民衆像は、愚鈍であり無知であり、欲に塗れた集団であるという印象を与えます。これにより、西洋側の文化が正であり、東洋人には秀でた人間の存在など考えられないという凝り固められた分析を押し付けられます。これは認識論的、存在論的であり、真の東洋を支配あるいは破壊して、西洋の思惑通りに存在を構築するという作業です。西洋による固定観念と差別意識によって東洋の存在を支配し、東洋(オリエント)に真の自身を語る言説を奪う行為こそが、西洋の目的であり思想であると言えます。
こういった占領者たちの価値観、または目線によって綴られ、後世に受け継がれた考え方は、西洋人にとって当然の知識と価値観となり、そこからも新たに西洋優位の言説が紡がれることになります。この言説の連なりをサイードは、文学研究者として、東洋で育ったパレスチナ系アメリカ人として、独特の目線と鋭い観察眼で指摘を繰り返していきます。本来の文学研究(英語や比較文学)、歴史学、宗教学、人類学、社会学などに照らし合わせ、実際的な「オリエンタリズム」を提唱しようと試みます。特に現象学、実存主義、フランス構造主義の原理を文学作品から読み取り、これらの作品と政治的支配とのつながりを見出します。
「書く」という行動が生み出す民衆への影響力は、書物という媒体によって後世まで幅広く読み継がれます。そして作品のなかに含まれる政治的、権力的、文化的な著述は、「事実としての価値観」を帯びて伝わっていきます。西洋のジャーナリストが執筆すれば政治的事実として、西洋の小説家が執筆すれば風俗的事実として、東洋の劣等性を読者に伝えます。こうして生み出された作品群が与えるイメージの蓄積が、現代において「オリエント」(東洋)という言葉から紋切型の劣等民族を連想させています。
ここには西洋側(オリエンタリストたち)の自覚が見られます。西洋の帝国主義政策による中東への侵略を「文化的に正当化」するという目的です。特に利用されたのは文学で、描く作品こそフィクショナルでありながら、そこに込める東洋の描写は強調されていながらも「事実に基づいた誇張」であるかのような描き方がなされます。読者は、ここまで極端ではないであろうが、「印象は近しいものであろう」という受け止め方をしてしまいます。これらの作品群が西洋の大衆へ「西洋優位の正当性」を齎し、東洋への植民地支配を道理的であると理解させた一助となりました。そして本書では、裏付けるようにイギリス、フランス、アメリカの研究者、作家、ジャーナリスト、政治家などのオリエンタリストを一八世紀から遡って詳細に引用を繰り返しながら紐解いています。
このように「オリエンタリズム」は、ポストコロニアル(植民地支配による負の遺産)について言及しているという側面がありますが、重きを置くべきは「西洋優位によって東洋に対する歪んだ価値観を生み、それを東洋の概観へと植え付けたこと」が主眼となります。これらを実行したオリエンタリストたちが持っている前提は、「自分たちの方がオリエント(東洋人)自身よりも深くオリエント(東洋)を理解している」という傲慢さを持っているということです。こういった父権主義的思考は、当然ながら西洋の帝国主義による植民地支配が齎したものであり、西洋にとって当然のことと受け止められる広範な差別意識のなすものです。そうして創り上げられた虚構の「東洋」は、民族的、特異的、性欲的、暗愚的、強固的、悲観的、狡猾的といったイメージを強固なものとして構築し、現代の「東洋趣味」に繋がっています。オリエントに対する異国情緒溢れる憧憬的な眼差しは、根底に西洋の帝国主義による侵略の齎した差別意識が通底していると言えます。
また、芸術全般で用いられる逆進性への憧れを表現する「プリミティヴィスム」はユートピア性を持った真の憧憬に感じられます。確かにオリエンタリストによって齎された要素は少ないかもしれません。しかしながら、非西洋的原始というイメージは確実に植民地支配を行った西洋(オクシデント)の目線であり、通底する西洋の帝国主義による侵略の影響は否定できません。「プリミティブ」の持つ自然性は「非文明」という意味が無意識に含まれ、その憧憬に含まれる感情の根源には西洋優位、東洋蔑視の価値観が存在しています。そうでありながら、偉大な「反植民地主義」の芸術家たちがプリミティブを追い求めて表現を試みるという点に、芸術における真のオリエンタリズムの恐ろしさが見えるように感じます。

サイードは、西洋が東洋侵略を正当化するために「オリエンタリズム」を生んだと概説しています。この発端は十字軍にまで遡り、東洋が秘めていた政治的な熱量を圧倒的な支配をもって自らのものとして征服します。西洋優位によって東洋の価値観は破壊され、西洋が押し付けた価値観を広められた東洋は「言説」を取り上げられます。長年の西洋による支配は東洋の口を閉ざし続けました。作られた歴史の上に立たされているオリエント(東洋)が、どのようにすれば言葉を発することができるのか、民族としての声を他者がどのようにして受け止めることができるのか、シオニズムの運動、イスラエル建国を真の意味で理解することができるのか、改めて考える必要があります。サイードの最後の著作『オスロからイラクへ』で息子ワディ・E・サイードが語るあとがきでも、彼の意志と望みが強く感じられます。
父は自分の書くものに、生涯にわたって培った博識を注ぎ込みました。そのトピックは多岐にわたり、文芸批評から、オペラ、歴史、そしてもちろん政治にもまたがっています。父の政治評論の説得力と力強さに萎縮させられてしまって、わたしはパレスチナ人の置かれたありさまを記録することに、自分も貢献しようという気にはなれませんでした。少なくとも父のような厳格さと一貫性をもってそうすることは、はなからあきらめていました。そんなわたしのためらいを聞かされたなら、父はきっと不満に思ったことでしょう。本書のいたるところで父が熱心に勧めているのは、パレスチナや他のアラブ世界の生活の真の姿を歪めている巨大なプロパガンダ機構から道徳的な優位性を取り戻すために、思い切って発言することなのですから。
『オスロからイラクへ』あとがき
無意識に刻まれた価値観の根源を覆すことは容易なことではありません。ですが、「本当の価値」という見方が重要であることは間違いがなく、そうしなければならないということも事実です。自身の持つ物事の目線や事実の理解を省みることが必要であると感じました。かなり辛辣な表現も多く、好きな作家を取り上げられていると不快な思いをするかもしれませんが、それでも重要な作品であると感じます。未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。