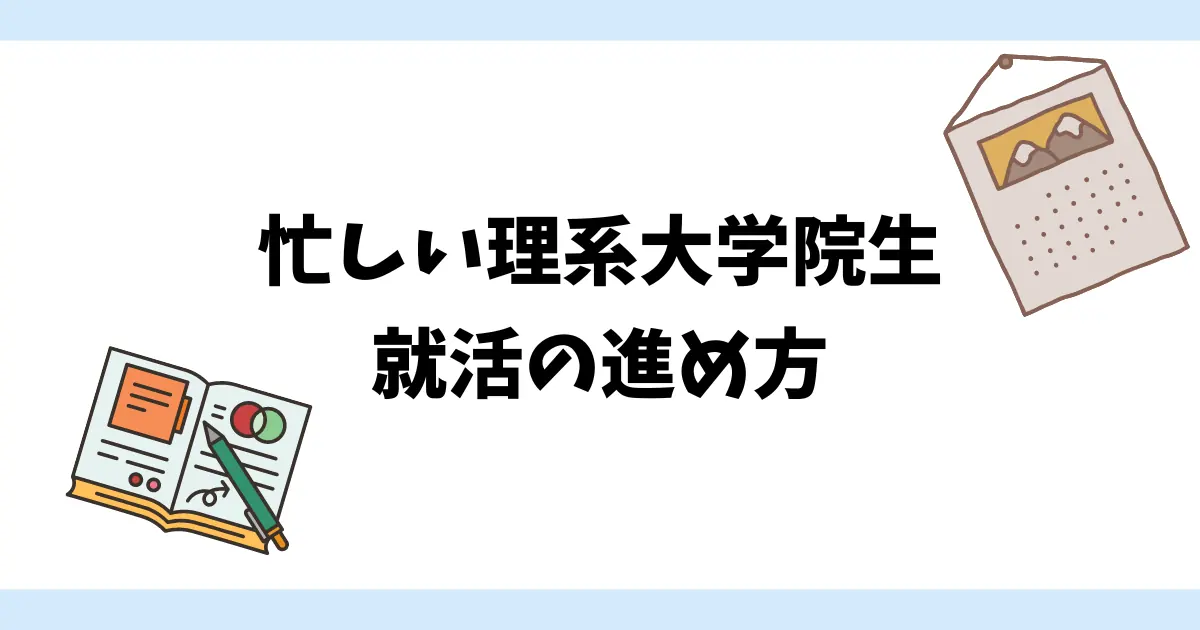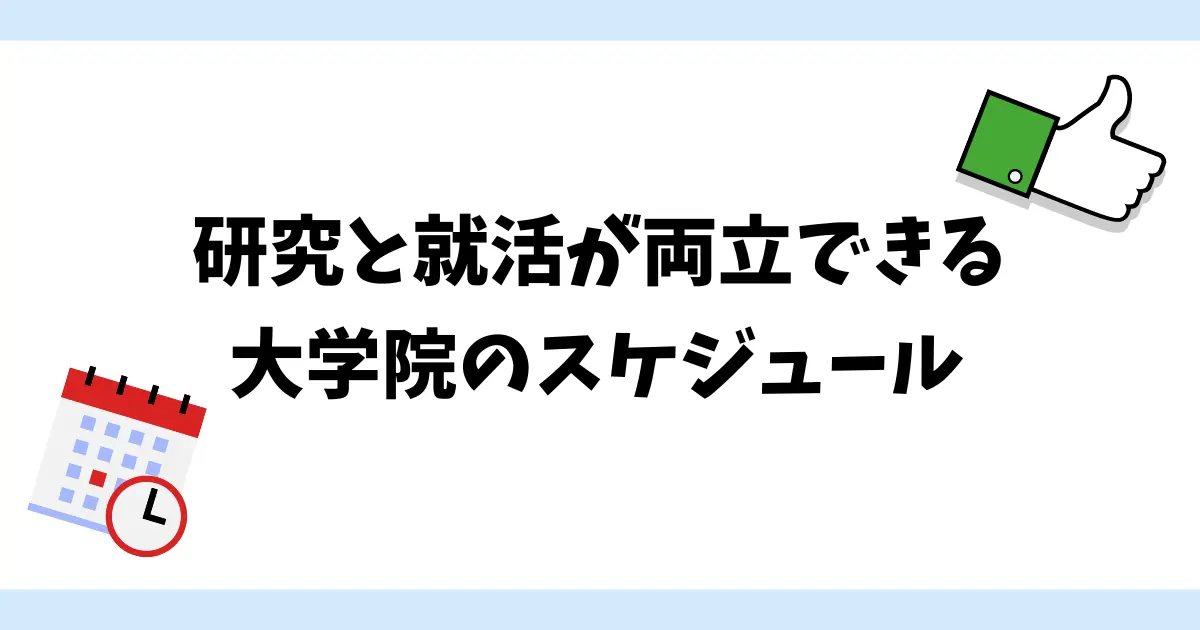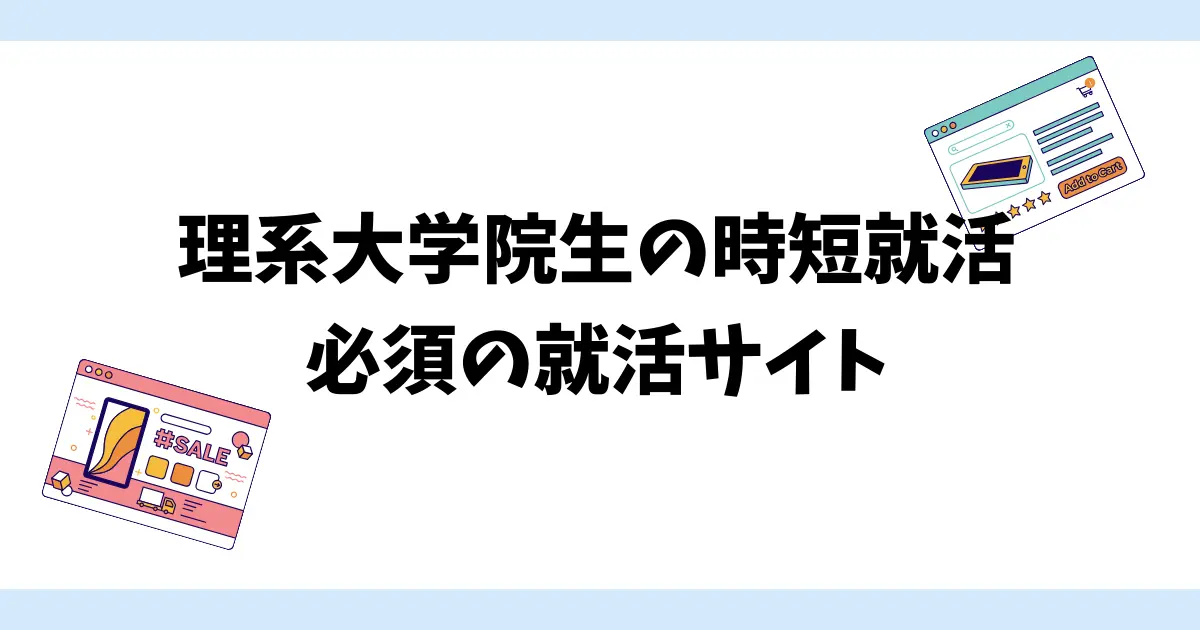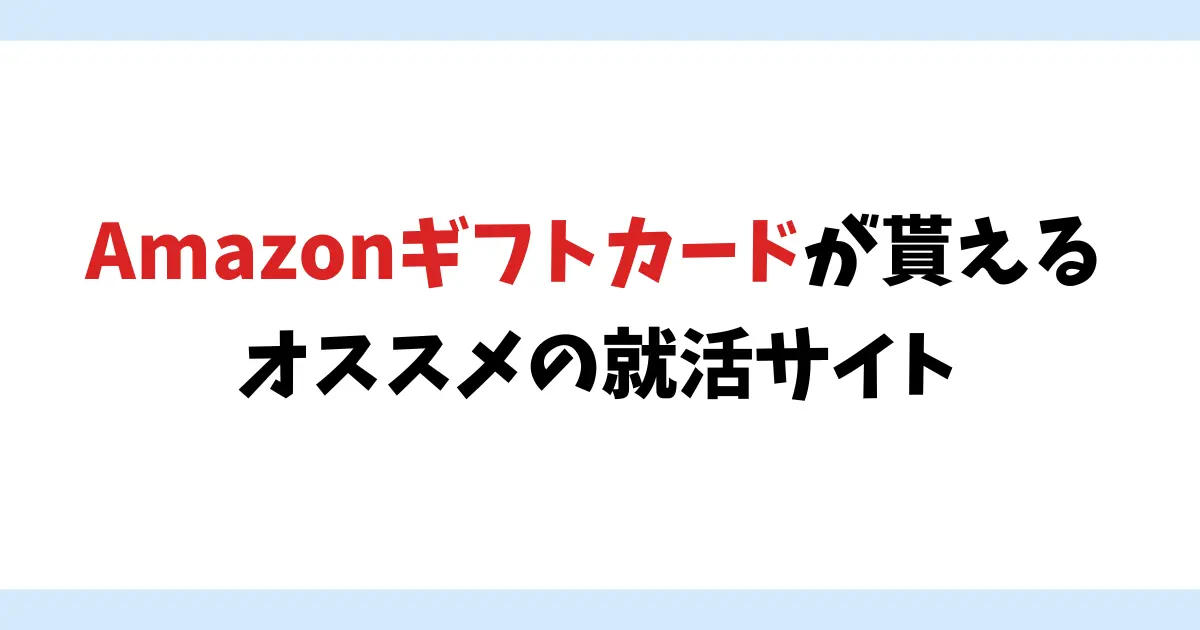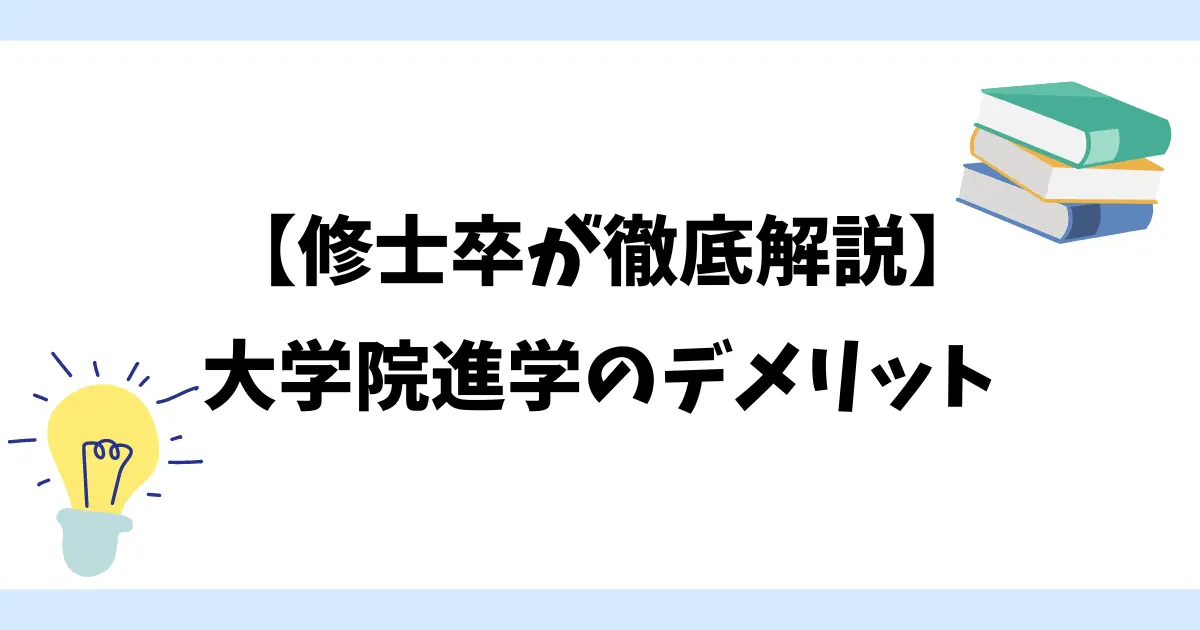- 大学院に進学したいけど大変そう
- 大学院に進学するデメリットは?
- 大学院に進学するか迷っている
大学院に進学したいけどデメリットは?大変?大学院に進学する前は、大学院についてよくわからなくて不安ですよね。
筆者も大学院に進学するか否かを最後の最後まで悩んだ経験があります。
この記事では、筆者の大学院に進学した経験を踏まえて、大学院に進学するデメリットについてご紹介します。
この記事を読めば、大学院に進学するデメリットを知れるだけでなく、大学院でどのように過ごせば良いのかを知ることができます。

<プロフィール>
✔2024年修士卒
✔学会発表2回、原著論文投稿2本
✔早期選考で国内大手企業複数内定
✔現在、国内大手企業で勤務
大学院に進学するデメリット
大学院に進学して感じたデメリットは、下記の通りです。
- 忙しい
- 精神的に辛い
- 就職が2年遅れる
大学院生は、後輩指導をしながら研究、就活、講義などのやることが多いため、非常に忙しいです。
全国大学院生生活実態調査によると下記のような大学院生の声が掲載されています。
アルバイトもできず収入もないのに家事もまともにできないほど研究に長い時間を割かなければならない状況です。将来は貸与型奨学金の返済に追われ、学部時代に頑張っていた貯金も底をつき、土曜日も平日扱いで人権のない生活です。(理工系/修士/2年/男/自宅)
第12回全国院生生活実態調査 概要報告 |全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連) (univcoop.or.jp)
現状、研究室に入ると研究室に1日の大半を費やし、バイトなどする時間もありません。毎日ギリギリの生活を送っており、切羽詰まっています。その上、研究は手を抜けない状況で、中途半端な結果を出せません。(理工系/修士/2年/男/自宅外・下宿)
第12回全国院生生活実態調査 概要報告 |全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連) (univcoop.or.jp)
研究と就職活動の両立が難しく、どちらとも中途半端になってしまうのではという不安はある。(理工系/修士/1年/男/自宅)
第12回全国院生生活実態調査 概要報告 |全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連) (univcoop.or.jp)
大学院生の皆さんは研究の時間が長くなるため、就活やアルバイトが思うようにできていないことがわかります。
大学院に進学するとメリットも多くあります。しかし、その反面、デメリットも多く存在するため注意が必要です。
大学院生は忙しい

大学院生は本業が研究活動ですが、就活やアルバイトなどのやらなければいけないことが多くあります。
大学院生のやるべきことをまとめると下記の通りです。
- 研究活動
- 講義
- 実験補助(TA)
- 後輩指導(研究室運営)
- アルバイト
- 就職活動
- インターン など
大学院生は、人それぞれ何を重視して進学したかによってこれらの比重が異なりますが、一般的に研究活動が本業になりますので、研究活動の時間が7~8割程占めるのが一般的であると思います。
大学院に進学まで私は、オンラインゲームを友達と一緒にプレイすることが好きでした。しかし、大学院進学後は、友達と一緒にプレイする時間がないことやプレイする時間帯が合わないことから、ほとんどゲームすることがなくなりました。
このように、大学院に在学中は、趣味に時間を費やすことが難しくなる場合があります。(研究室によって大きく異なる)
筆者の大学院時代の1日のスケジュール例(平日)
大学院生の生活は、ゼミやアルバイト、実験補助がある日によって大きく異なります。今回は、研究以外に予定がない日の例を紹介します。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:00 | 起床 |
| 9:00 | 研究室に到着 講義 or 研究作業 |
| 12:00 | 昼食 研究室でパスタ |
| 13:00 | 研究作業 or ゼミ or 就活 |
| 18:00 | 夕ご飯 学食orパスタ |
| 18:30 | ゼミ or 研究作業 |
| 22:00 | 研究室を出発 |
| 22:30 | 帰宅 |
| 23:00 | お風呂 夕ご飯 |
| 25:00 | 就寝 |
この日は、ゼミがないため、午前中にTOEICの勉強を行い、午後に研究活動を行っています。お昼ごはんや夕ご飯の時間は、定まっていないため、お腹が減ったタイミングで食べるようにしています。
上記のスケジュールの中でも、随時後輩の研究指導をすることが多くあります。
例えば、後輩の研究指導は、
- 研究の進捗相談
- プログラミングに関する相談
- ゼミ資料のまとめ方の相談
などが挙げられます。
もし、大学院生の生活の実態について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
大学院生の多忙なスケジュールによって得られるメリット
大学院生は、研究や実験補助、アルバイト、就活などのタスクに追われることで、非常に大変な時期です。この忙しさは、スケジュール管理能力の向上に繋がります。
 はやとん
はやとん研究の合間を縫って就活をすることが多いね。
時間を積極的に作る能力やタスクの優先順位をつける能力が高めることができます。
精神的に辛い場面がある


大学院生は、常に研究成果が求められるため、研究成果が芳しくない場合にとても辛い思いをします。
例えば、2ヶ月後に修士論文なのに良い結果がでていないようなことがあります。
私の専攻では、基本的に提案手法の良い結果が得られていることや新たな知見が出たことなどが卒業の要件でしたので、卒論シーズンでは、みんな必死に研究していました。
特に私が所属していた研究室は、研究室配属された学生がそのまま研究室で卒業できる割合が約50%ほどでした。
この傾向を踏まえると、研究室に配属されている大学生や大学院生は、高負荷な精神的ダメージを受けていることがわかります。
辛い道を乗り越えた先にあるメリット
理系の大学や大学院を卒業した人は、精神的にタフな人が多いです。精神的にタフな人は、研究室に配属されていた時代に辛い経験をしているので、少し嫌なことがあっても心が折れない人が多いです。
筆者の周りでも、研究室で研究していたときよりも社会に出て働いたほうがラクに感じる人がほとんどです。
就職が2年遅れる


大学院に進学する上でデメリットとしてよく挙げられるのが、就職が2年遅れることです。就職が2年遅れると、2年間分の生涯賃金が下がることが懸念されています。
しかし、大学院卒は、初任給が学部卒と比べて2万~3万ほど高く設定されていることが一般的です。このため、大学院進学で就職が2年遅れて生涯賃金が下がる可能性は低いと考えられます。
また、大学院に進学することによって就職が遅れることは、就職活動においてプラスになります。自分が修士卒で就活する場合、学部卒で就職した人が先に働いているため、友人から就職活動に関するアドバイスが貰えます。
就職が遅れることのメリット
友人は先に社会に出ているので、学部卒で先に就職した友人から様々なことが勉強できます。
学部卒で就職した友人から勉強できることは下記の通りです。
- 働いている会社や業界の評判を聞ける
- 就活の失敗談を参考にできる
- 就活のアドバイスが聞ける
このように、先に出た社会の先輩ですので、様々なことを友人に聞くことが、就職が遅れることで生じるメリットになります。
大学院進学を悩んでいる学生に向けた5つのアドバイス


大学院は長時間の研究活動が求められるため、軽い気持ちで進学すると辛い思いをする可能性があります。
筆者の同期や先輩、後輩にはこんな人がいます。
- 大学4年生後期で進学する研究室を変えた学生
- 修士2年生で博士課程に進学を取り消し、就活浪人
- 大学院入学1日目で退学届けを提出
- 修士2年生後期でも内定が決まらない
- 研究が辛くて退学
このような人は少なくありません。
私は、皆さんにこのような思いをしてほしくないため、大学院進学を悩んでいる方に向けて僭越ながらアドバイスさせて頂きます。
大学院卒から、大学院進学に悩んでいる学生に向けたアドバイスは下記の通りです。
- 研究室の先輩に相談しよう
- 早めに就活をしておこう
- 研究室の雰囲気や指導教員との相性は重要
- 大学院に進学する理由や目的を明確に
- 進学したらなんとかなるが、自分を大切に
それぞれのアドバイスについて解説します。
研究室の先輩に相談しよう
研究室について一番知っている人は、研究室の院生です。
院生の先輩に大学院進学に関する不安要素を聞いておくことがオススメです。
研究室の先輩に相談できる内容は、
- 研究の忙しさ
- 就活と研究は両立できるのか
- 大学院進学して後悔してないか
- 自分でも大学院進学してやっていけるのか
- 大学院への進学理由
があります。
これらの相談内容は、研究室に在籍している大学院生にしか答えられないことが多いです。
もし、悩んでいることがあるのであれば、研究室の先輩に質問してみましょう。
大学院生に対する質問例
進学前に大学院生に不安なことを質問すると不安要素が解消できます。
しかし、進学前に大学院生に質問することは、何を聞けばよいのかよくわからない人も多いと思います。
そこで、大学院生に対する質問例を下記にまとめたので参考にしてください。
| 研究の忙しさ | ・TAやゼミの頻度 ・研究室の滞在時間 ・1日の作業時間 |
|---|---|
| 進学理由 | ・大学院へ進学した目的 |
| 研究と就活の両立 | ・研究室の就活に対する理解 ・インターンに参加できているか ・OBやOGの就職先 |
| 進学して後悔ないか | ・生活に関すること ・しんどくないか ・人間関係 |
| その他 | ・研究についていけるか ・体力面に関すること ・精神面に関すること |
研究室の先輩にたくさん質問をして、大学院進学前に不安要素を解消してください。
早めに就活をしておこう
大学院に進学するか検討している学生には、早めに就活をしておくことがオススメです。
大学院に進学予定の学生に就活をオススメする理由は下記のとおりです。
- 有名企業や大手企業から内定が貰いやすくなる
- 急に大学院進学を辞めた場合でも就活にすぐ復帰できる
それぞれの理由についてご説明します。
有名企業や大手企業から内定が貰いやすくなる
有名企業や大手企業に内定を貰うためには、早めの就活対策が重要となります。
大学院に進学する理由が有名企業や大企業に就職するためであれば、大学4年生から就活を意識しておくことがオススメです。
大学院進学する予定の大学生がやるべき就活は、オファー型就活サイトに登録することだけです。
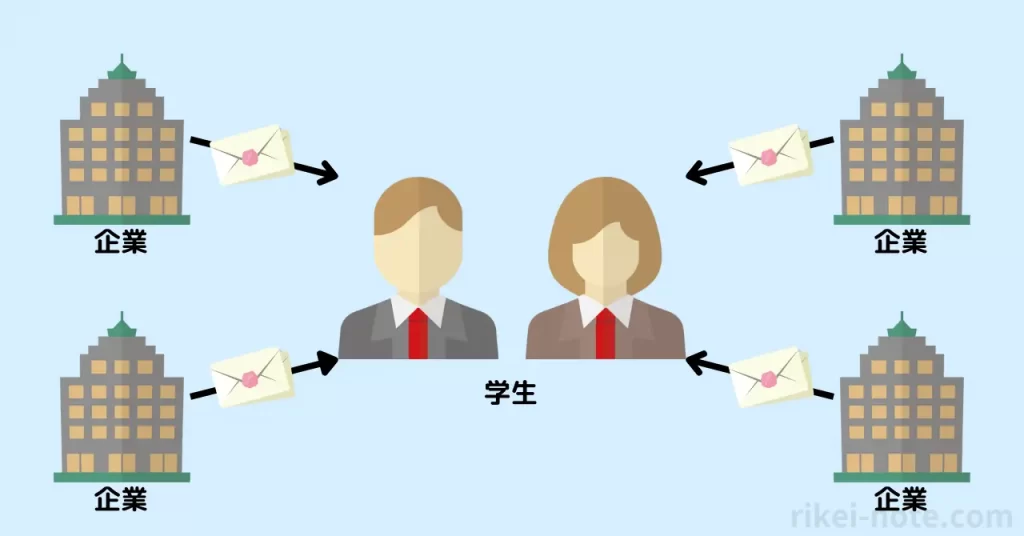
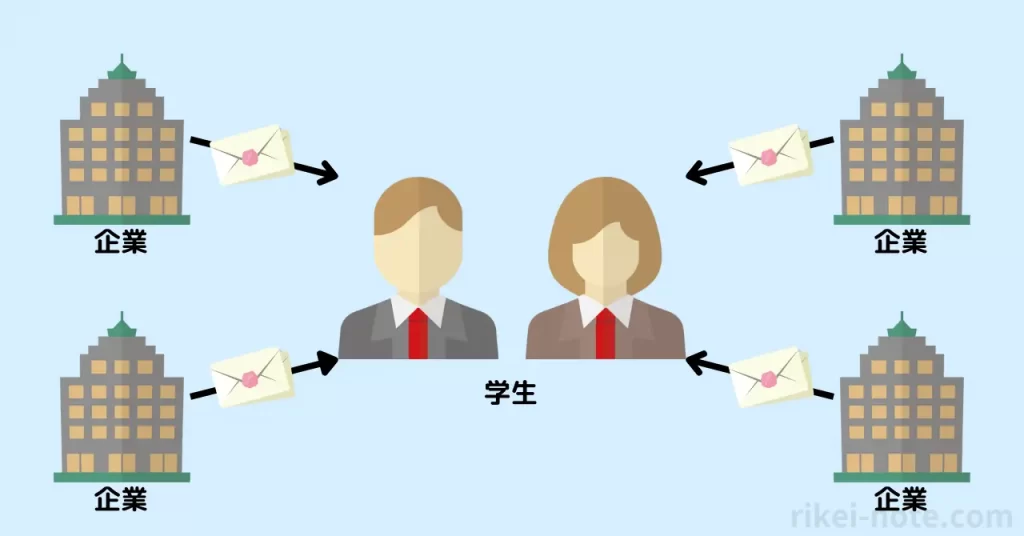
オファー型就活サイトは、登録だけで企業から選考免除などの特典付きのスカウトが届くサービスです。
筆者も大学院生時代にオファー型就活サイトで数多くのスカウトを貰えるだけでなく、就活を効率的に進めることができました。
大学院に進学予定の大学生がオファー型就活サイトに登録するメリットは、
- 選考免除などのスカウトが届く
- 早めに登録することで多くのスカウトが届く
- 進学しなくても納得する企業からスカウトが届く可能性
- 登録しておけば大学院に進学したあとも引き継げる
があります。
大学院に進学予定の大学生、大学院生にオススメのオファー型就活サイトは、下記のとおりです。
この3つのオファー型就活サイトは、実際に筆者が利用した上でオススメできるサービスです。
それぞれのオファー型就活サイトを通じてスカウトが貰えた企業名や大企業の割合は、下記の記事でまとめています。
研究室の雰囲気や指導教員との相性は重要
大学院に進学すると一日中研究室で生活することになるため、研究室の同期や指導教員と一緒に過ごす時間が非常に長いことが多いです。
研究室のメンバーや雰囲気との相性が良ければ、長時間研究室で過ごしていても問題がありません。
一方で、研究室のメンバーや雰囲気との相性が悪い場合、長時間研究室で過ごすのは非常に辛いです。
このため、大学院に進学するときは研究室の相性を意識して検討してみてください。
大学院に進学する理由や目的を明確に
大学院に進学すると研究や就活、バイトで忙しくなります。
このとき、なんのために大学院大学院に進学したのかを明確にしておくことで、忙しい生活に耐えることができます。
大学院進学のよくある目的は、
- 大企業(優良企業)に就職するため
- 研究職に就きたいため
などがあります。
このなかでも、大企業や優良企業に就職するために大学院に進学する人は非常に多いです。
大企業や優良企業に就職したい人は、大学院に進学することをオススメします。



筆者も大学院での多忙な研究生活を乗り越えたおかげで、納得する企業に就職することができました。
進学したらなんとかなるが、自分を大切に
大学院に進学する前は、大学院生活をやっていけるか、修了することができるのかなどの不安要素が多くあると思います。
結論から言えば、進学してちゃんと研究活動をしていれば大学院を修了することができると思います。
ただし、自分の体調が悪くなってしまった場合は無理せずに自分を大切に過ごしてください。
すぐに家族や友達に相談するだけでなく、お医者さんに診てもらうなどの行動を取ることがオススメです。
自分を大切にしたうえで、大学院に進学して研究と就活をがんばってください。



病まない程度に頑張ろう
まとめ
筆者が感じたことや一般的に言われている大学院進学のデメリットをまとめましたが、考え方を変えればメリットにもなります。
本記事で取り上げた大学院進学のデメリットは、配属する研究室によって大きく異なる場合があります。
もし、研究室に配属された学生は、検討するときに研究室の修士や博士の先輩によく話を聞いておくことをおすすめします。
まだ研究室に配属されていない学生は、実験補助などで関わる大学院の先輩に聞くことをおすすめします。