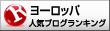そんなわけで読み始めたのが
『No Place to Call Home』。
いや、読みたかったんですよ。
読みたかったんです、
読みたかったんですけど
・・・これ、英書で、
日本語訳が
(たぶん)出ていなくて・・・
自慢じゃありませんが
私はこういう
社会学系っていうか
学術系っていうか
とにかく『小説』、
『フィクション』じゃない本を
英語で読んだのは
学生時代が最後なので。
(本当に自慢じゃない)
ちなみにその学生時代の
『英文読書』も、あれ、
どこかにレジュメを
仕舞ってあるんですけど、
ゼミとか有志とかで
持ち回りで英書を和訳していく、
みたいな勉強会で、私の
担当した箇所の訳文は
本当にひどかったですからね。
当時の私は思い込みと勢いで
訳を進めるところがあり、
結果として壮大な誤訳に
堂々とたどり着いてしまう。
(この悪癖は
今も残っています)
そりゃ私は今年に入って
某ミステリ小説を
英文で読みましたよ?
でもあれは本当に前もって
和文名訳を読んでいたからこそ
理解できた側面が強くてですね。
今回は、この
『No Place to Call Home』は、
取り上げられている事件についても
私はほとんど知識がないし・・・
いざという時に盗み読みできる
和文文献も存在しないし・・・
数ページ読んで
「歯が立ちませんでした、
すみません、読めません」は
悔しいし悲しいな、と
試合前から敗戦気分、
みたいな状態で本を開き
・・・ところがどっこい。
あの、これ、この本の
この英語、
非常に読みやすいです!
比較しちゃうのは
失礼かもしれませんけど
M.クレイヴン氏の英語より
数段意思の疎通が図れる感じ!
『No Place to Call Home』、
これ、この英語、たぶん
『新聞で使われる英語』なんです。
それも大衆紙ではなく
(大衆紙の英語は
私には本当に難しい)
『テレグラフ』とか
『フィナンシャル・
タイムズ』とかの
いわゆる高級紙の英語。
ニュース文体というか・・・
勿論単語は辞書を
引かなくちゃ
仕方ないんですけど、
文法が『学校で
習った通り』なんです。
だから読解に躓いても
「はい大丈夫大丈夫、
落ち着け落ち着け、
まず主語がここ、述語がここ、
目的語がここ、まずは
主語と述語だけで訳して、
そこに目的語を追加して、
はいそれから副詞を入れて」って
順番にやっていくとちゃんと
『意味が通る』んです・・・!
でもこんなことを書いていますが
私は英文を読んで
『これが動詞』とか
『これが目的語扱いの名詞』とか
そういうのはわかったんですが
その動詞と名詞の意味を
『わかる』には辞書が必要で・・・
というわけで久々に
作りましたよ『単語帳』。
本の内容がどうこうの前に
自分に割と向学心的なことに
驚いた英文読書でございました。
続く。
『No Place to Call Home』で
扱われている
『デール・ファーム事件』は
「日本などからも
報道陣が来たくらい
世界的に注目された」って
こっちでは言われるんですが
私は全然記憶になく
後述しますがこれ
2011年10月に
起きた話なんですよ
・・・2011年は
我々にとっては
東北大震災の年ですものね・・・
報道陣が現場入りしても
番組や紙面に枠が
とれなかった可能性も
ゼロではないだろうし・・・
そんなわけで
明日よりいよいよ
『No Place to Call Home』の
内容に触れてまいります
壮大な誤訳を
かましたらすみません
お帰りの前に1クリックを
↓