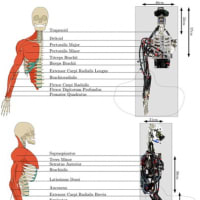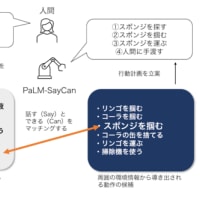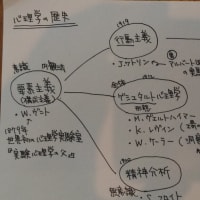以下の記事を備忘録として保存する。
----------
連載の第1回から第3回では、DNA(デオキシリボ核酸)を素材にして様々な構造物をつくる「DNAオリガミ」という技術を紹介しました。そして第4回から第6回では、そのDNAオリガミに、微小管とキネシンというタンパク質を組み合わせて、群れをつくるナノサイズのロボットや、人工筋肉をつくる技術にスポットを当てました。
これらのDNAやタンパク質は、生体内で遺伝情報を伝えたり、様々な物質を運ぶのが本来の役目です。それを人間が、全く別の形で利用しようとしているわけです。
あまり目立たないのですが、私たちの体には、もう1つ「リン脂質」という重要な物質があります。それはDNAやタンパク質の器である「細胞膜」の材料です。最近は中身のない膜だけでも、変形したり分裂したりできることがわかってきました。今回からは「生命の起源」に関する研究でも注目されている、リン脂質に秘められた可能性を見ていきましょう。
----------
細胞膜は洗剤に似た物質でできている
虹色のシャボン玉 photo by gettyimages
「細胞膜はシャボン玉のようなものだ」と言ったら驚くでしょうか。空中を漂い、屋根まで飛んで壊れて消えてしまう、あのシャボン玉です。そんな頼りないものが私たちの体を構成しているとは、ちょっと思えませんよね。しかし化学的に見ると、どちらも「両親媒性分子」でできた「二分子膜」であるという意味で同じなのです。 両親媒性分子とは、水にも油にも溶ける分子で「界面活性剤」とも呼ばれます。つまり洗剤です。ご存知の通り水と油は通常、お互いに混じり合いません。しかし両親媒性分子があると、それが仲立ちをして水と油は混じり合います。食器についた油汚れが水と洗剤で落とせるのは、そのためです。 そして二分子膜というのは、この両親媒性分子が二層(二重)に並んでできた膜という意味です。シャボン玉の膜は1マイクロメートル(1000分の1ミリメートル)前後の厚みしかありませんが、実は2枚の膜からできており、その隙間には水が入っています。それに光が当たると1枚目の膜で反射する光と2枚目の膜で反射する光とに分かれ、お互いに強め合ったり弱め合ったりする(干渉する)ため、虹のような模様が浮かび上がるのです。 シャボン玉に使われるのは石鹸水や台所洗剤などですが、さすがに細胞膜を構成するのは、そのような洗剤ではありません。いくつか種類があって、ひとくくりにする場合は「リン脂質」と呼ばれています。大雑把には名前の通り「リンを含んでいる脂」と捉えておけばいいでしょう。ただ「脂」というと固体のイメージですが、リン脂質は液体に近い性質を示す場合もあります。
分子が縦にぎっしり並んで膜になる
リン脂質の分子が2列にぎっしり並んで細胞膜(脂質二重層)になる illustration by iStock
両親媒性分子を模式的に表すと、丸い「頭」に細長い「足」が直接、生えたような形になっています。頭は水になじむ部分で「親水基」とも呼ばれます。足は水になじまない部分(すなわち油になじむ部分)で「疎水基」とも呼ばれます。洗剤に使われる分子の足はたいてい1本ですが、リン脂質には2本あります。 両親媒性分子が膜をつくった状態というのは、頭を水のある方に向けて(あるいは足を油のある方に向けて)縦にぎっしりと並んだ状態です。満員電車に押しこめられている人々を、思い浮かべてもいいでしょう。 シャボン玉の場合、膜と膜との間に水があるので、頭はそちらを向いています。つまり水の層をはさんで、分子が頭を突き合わせつつ2列に並んでいるのが、シャボン玉の二分子膜なのです。 一方で細胞は、細菌やアメーバなどを思い浮かべた場合、たいてい水の中を漂っています。人間の体も50~80%が水ですから、その細胞も水の中といっていい状態でしょう。となると細胞膜の両親媒性分子、すなわちリン脂質は、どちらに頭を向けているでしょうか? 二分子膜ですから、まず外側の膜は頭を周囲にある水の方へ向けていなければなりません。そして内側の膜ですが、細胞内も基本的には水で満たされているので、そちらへ頭を向けていることになります。なのでシャボン玉とは逆に、足側を突き合わせながら2列に並んでいるわけです。そして膜と膜との間は、水になじまない領域になっています。
脂質二重層の袋は「ベシクル」
脂質二重層のベシクルを半分に割った状態の模式図 illustration by gettyimages
実はリン脂質でできた二分子膜――「脂質二重層」とも呼ばれます――の「玉」は、シャボン玉ほどではありませんが、わりと簡単につくることができます。スーパーや100円ショップなどに売っている材料を使って、皆さんがキッチンでつくることも可能です。詳しくは筆者が以前に連載していた「生命1.0への道」の第7回2ページ目(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55034? page=2)を参照してください。 水中にある脂質二重層でできた玉や袋は「ベシクル」とも呼ばれます。つまり細胞膜もベシクルです。脂質二重層の厚みはシャボン玉の膜より薄く、4~5ナノメートル(1ナノメートルは100万分の1ミリメートル)しかありません。もし私たちの細胞が直径1メートルに巨大化しても、膜は0.5ミリメートルほどしかないという計算です。 ベシクルは球形とは限らず、ぶよぶよと不定形だったり、長ネギのように細長かったりもします。大きさは100ナノメートル以下のウイルスサイズから、1マイクロメートルを超える細胞サイズまで様々です。細胞サイズのベシクルは、とくに「ジャイアントベシクル」とも呼ばれます。 また、いくつかのベシクルが入れ子状態になっているものもあります。シャボン玉でも、うまくつくれば玉の中に玉を入れ、その玉の中にまた玉を入れたりできますが、それと同じ状態です。脂質二重層では、むしろ入れ子になっていないベシクルをつくるほうが難しかったりします。
ビニール袋も「生き物っぽい」?
豊田太郎さん(左)と杉山博紀さん(右) photo by Shingo Fujisaki
ここでベシクル、とくにジャイアントベシクルをこよなく愛している2人の研究者に登場してもらいましょう。東京大学大学院 総合文化研究科 准教授の豊田太郎(とよた・たろう)さんと、そのお弟子さんで今は自然科学研究機構 生命創成探究センター 博士研究員の杉山博紀(すぎやま・ひろのり)さんです。 お2人とも化学者ですが、共通の専門分野を一つ挙げるとすれば「合成生物学」です。どちらかというと今はバイオテクノロジーに近い分野と思われがちですが、ここでは字面から想像される通り、化学的に生物(らしきもの)を合成しようとする分野と捉えてください。 目的は従来の「観察」や「解析」といった手法だけではなく「つくってみる」ことで「生命とは何か」を理解することです。また、生き物っぽいロボットや人工知能(AI)をつくろうとする「分子ロボティクス」や「分子サイバネティクス」といった分野とも重なり合っています。 子供のころの豊田さんは化学実験や工作が好きだった一方、医師を志していたこともあって人体には早くから興味を持っていました。また親戚の死などに接して「命のはかなさ」を深く感じる早熟さもあったようです。 高校時代は動画に興味を持ち、自主映画制作をするサークルを自ら立ち上げました。映画の内容としては、学園を舞台にしたラブコメが多かったそうです。そのような体験を背景に、今では顕微鏡下で様々な物質が生き物のように変化したり、動きまわったりする様子を動画で撮影しながら、研究を進めています。 片や杉山さんは子供のころ、自宅前の道路に捨てられていたビニール袋が風で揺れているのを見て「車に轢かれちゃう、助けなきゃ」とお母さんに訴えたことがあるそうです。「あれは、ただのゴミよ」との返事にも「だけど生き物っぽいじゃん」と食い下がりました。それ以来「生命とは何か」を、漠然と考えるようになったそうです。 また高校時代にカエルの解剖をして、その「生々しさ」と、当時、生命について感じていた「機械のような精緻さ」との間に、大きな隔たりを感じました。いわゆる「生物と無生物の間」を再認識した、ということかもしれません。以来、その間を埋める研究をしたいと思い始め、大学では豊田さんの研究室に入りました。
分子だけでも勝手に「細胞」化する
細胞膜の詳細な模式図。これ自体が精密な機械のようでもある illustration by gettyimages
ジャイアントベシクルは、言わば空っぽの細胞です。細かいことを言えば、本物の細胞の膜にはコレステロールなどとともに、様々なタンパク質が埋めこまれています。これらの「膜タンパク質」には細胞の構造を支えたり、細胞の内外で特定の物質をやり取りしたり、外から来る情報を受け取ったり、といった役目を果たすものがあります。とはいえベースは、リン脂質の二分子膜であることに変わりはありません。 生命が誕生した40億年前ごろの細胞は、おそらく脂質の袋に核酸やタンパク質のもとになる物質が入っている程度の原始的なものだったでしょう。それが、いかにして今の複雑な構造や機能を持つ細胞に進化していけるのか――その解明に興味を抱いた杉山さんは、とりあえず「膜」に注目してみようと考えて、ジャイアントベシクルの研究を始めたそうです。 一方で豊田さんがジャイアントベシクルにのめりこんだきっかけは、大学院生時代の印象的な実験でした。それは当時の主要な研究テーマではなく、言わば「裏実験」としてやったことでしたが、結局、論文にもなりました。 その実験で使ったのはリン脂質ではなく、豊田さんが自分で設計してつくりだした両親媒性分子でした。それは水を加えると化学反応によって、頭(親水基)を含む部分と足(疎水基)を含む部分とに、分解してしまう性質を持っています。実験としてやったのは、その分子を水中に溶かして観察するだけでした。 すると初めは「ミセル」と呼ばれる両親媒性分子の集団が、あちこちにできました。これも球形をしているのですが、中に空洞はありません。無数の分子が頭を水のある外に向け、足を中心方向に延ばしています。身近なところではネギ坊主とか、タンポポの綿毛が玉のように集まっている状態をイメージしてもらえればいいでしょう。 化学反応が進んで両親媒性分子の頭が徐々にとれていくと、なぜかミセルは集まって細長い紐のようになっていきます。さらに反応が進むと、紐が束になって餃子の皮のように平たい膜ができます。それが次第に丸まって、ついには袋状のジャイアントベシクルになります。しかし変化は止まらず、ベシクルはチューブ状になり、その一部がえぐれて最終的には入れ子状のジャイアントベシクルになることがわかりました。 どうしてそうなるのか、仮説はありますが、まだ完全にはわかっていません。ただ大事なのは、単なる分子の集まりが、このように自らダイナミックな変化をしていくことです。見かけだけではあるものの、最初はただの油の粒のようなものだったのが、最後は内部に構造をもつ細胞のような姿になったのです。 「タンパク質とか遺伝子とかがあれば、そういうこともあるでしょうって思うかもしれません」と豊田さんは言います。「だけど膜だけで、しかも自分で設計してつくった分子が、水中でみるみるうちに構造化していくっていうのが見えたんです。これは自分がやってみたいなと、漠然と思っていたことができた瞬間とも言えるので、がぜん面白さが実感できました。それで愛着が一気にわいたという感じですかね」
子供にDNAを渡したベシクル
ジャイアントベシクルにコブができて(出芽)、それが子供ベシクルとして離れていくまでの様子を示した顕微鏡画像。Hに示した白い線の長さは10マイクロメートル photo by Juan M. Castro
どんなに複雑な機械も、たいてい最初のうちはシンプルでした。例えば航空機は複雑な機械の代表格みたいなものですが、19世紀末、ドイツの技師オットー・リリエンタール(1848~1896)が乗った航空機にエンジンはありませんでした。つまり翼だけのグライダーです。それでも「空を飛ぶ」という最低限の目的は果たしました。 生物の細胞も、今でこそDNAや様々なタンパク質がぎっしり詰まっている精密機械のようなものですが、40億年前には脂質二重層に毛が生えた程度のものだったかもしれません。それでも生命として最低限、必要な機能は持っていたと考えられます。 豊田さんと杉山さんは、情報科学芸術大学院大学 メディア表現研究科 准教授のホアン・マヌエル・カストロさんとともに、それを彷彿とさせる実験にも成功しました。 生命の基本機能の一つに「増殖する」を挙げる人は多いでしょう。その増殖には「次世代に自分の(遺伝)情報を伝える」という過程も含まれていると考えられます。増殖する時に、まず必要なのは膜を増やすことです。増やさずに分裂すれば、どんどん細胞が小さくなってしまうからです。 実験で使われたジャイアントベシクルは、細胞膜と同じようにリン脂質でできていました。放っておけば、ただの水中シャボン玉です。豊田さんらは、このベシクルに「餌」を与えてみることにしました。つまりリン脂質になる部品と、それを組み立ててくれる「触媒」(銅イオン)です。 実際の細胞では20種類くらいの「酵素」を使って、多くの細かい部品からリン脂質を組み立てています。しかし人為的にそれを再現するのは非常に難しいので、実験ではもっと単純化しました。 まず片方の足だけがちょっと短い「リン脂質の未完成品(前駆体)」を用意します。それだけだとベシクルの膜にはなりません。そこに足の部品を触媒の作用でカチャッとつけてやれば、ちゃんとしたリン脂質ができるようにするのです。つまり実際の細胞で行われている工程の、最終段階くらいを再現したわけです。 この前駆体と足の部品、そして触媒をジャイアントベシクルに振りかけてやったところ、ベシクルはそれらを取りこんで(食べて)、どんどん膜を増やしていきました。すると、ある段階でプクッとコブのようなものができました。そのコブは次第にくびれていき、最後にはちぎれました。つまり、もう一つのベシクルになったのです。 ジャイアントベシクルには、あらかじめ「ラムダファージ」と呼ばれるウイルスのDNAを入れてありました。入れてあるだけで、実際に遺伝情報の媒体としては機能していません。ただコブになって分かれていった子供ベシクルにも、ちゃんとそのDNAは分配されていたことがわかりました。 つまりジャイアントベシクルは、少なくとも形の上では、増殖して次世代に情報を伝えるという機能を果たしたことになります。
原核細胞の分裂を再現した?
Aは餌を与える前のジャイアントベシクル、Bは餌を与えた後、コブができた状態のジャイアントベシクル。左側は通常の白色光で、右側は蛍光で見た顕微鏡画像。DNAは緑色に光らせている
この実験で最も興味深いのは、DNAの渡されかたでした。実験前、豊田さんらはDNAが分配されることがあっても、それは親ベシクルのDNAが子供ベシクルの方へ薄まりながら広がっていく、つまり拡散していく形ではないかと予想していました。 ところが、やってみるとDNAはベシクルが餌を与えられた後、ものの数分で膜の内側に全部、引き寄せられていったのです。そしてコブができると、その内側にもすでにDNAが張りついていました。子供ベシクルは、そのままDNAを引き連れる形で分かれていったのです。触媒とDNAの電荷が関係していると推定されますが、その仕組みも、まだ完全には解明されていません。 「細菌のような原核細胞の多くは、分裂する前に必ず1回、膜にぺちょっとDNAの一部をつけるんですね」と豊田さんは言います。「それでDNAを複製していくんですが、分裂する時には、その複製されたDNAが、ずるっと膜に引きずられて二つになっていきます」 豊田さんらの実験は、そのようなメカニズムが原始細胞でどのように進化していったのかを、垣間見せてくれているのかもしれません。
増殖するロボットやAIの実現へ
ナノサイズのロボットが細胞のように増殖していく未来のイメージ illustration by iStock
このように生命の起源や進化について、多くの示唆を与えてくれるジャイアントベシクルですが、工学的にも様々な利用が考えられます。 ロボットにしろ、コンピューターやAIにしろ、中身がむきだしで置かれていることは、ほとんどありません。たいていは金属やプラスチックの筐体に覆われて、保護されています。DNAやタンパク質でできたロボットやAIでも、同様に保護する必要がある場合は、ジャイアントベシクルが使えるでしょう。 豊田さんも参加している「科研費学術変革領域研究(A)分子サイバネティクス」というプロジェクトでは、2020年からの約5年間で、化学的なAIを開発しようとしています。現在のイメージでは情報を受取る「センサー」と、それを処理する「プロセッサー」、その処理結果をもとに変形する(動く)「アクチュエーター」という、3種類のユニットを組み合わせて、脳のような構造をつくることになっています。 これらのユニットは、いずれもDNAやタンパク質などを材料に構成され、それぞれがジャイアントベシクルで覆われる予定です。3種類の玉をつなげるので、仲間内では「団子3兄弟」などと呼ばれています。 実際にAIを組み立てる時には、たくさんの団子をつくることになるでしょう。その中には、どうしても一定の割合で不良品が混じってくると思われます。それは人間が取り除いていけばいいのですが、それなりに手間がかかります。そこで出来のいい団子だけを分裂・増殖させれば、かなり効率がよくなるのではないでしょうか。 この場合、ベシクルだけではなく中身も増えなければなりませんので、技術的なハードルは上がります。しかし不可能ではありません。細胞のように自分をコピーして増えていくロボットやAIの実現――ちょっと怖い気もしますが、夢は広がります。 第8回は2月28日公開予定です ---------- このコンテンツは、科研費学術変革領域研究(A) 分子サイバネティクス(https://molcyber.org)の支援を受け、ジャーナリストが研究者に長期取材する「ジャーナリスト・イン・レジデンス(JIR)」の一環として制作されたものです。 ---------- 好評連載【脳に迫る「化学人工知能」の夜明け】のこれまでの記事は、https://gendai.ismedia.jp/list/series/molecular_cybernetics からどうぞ